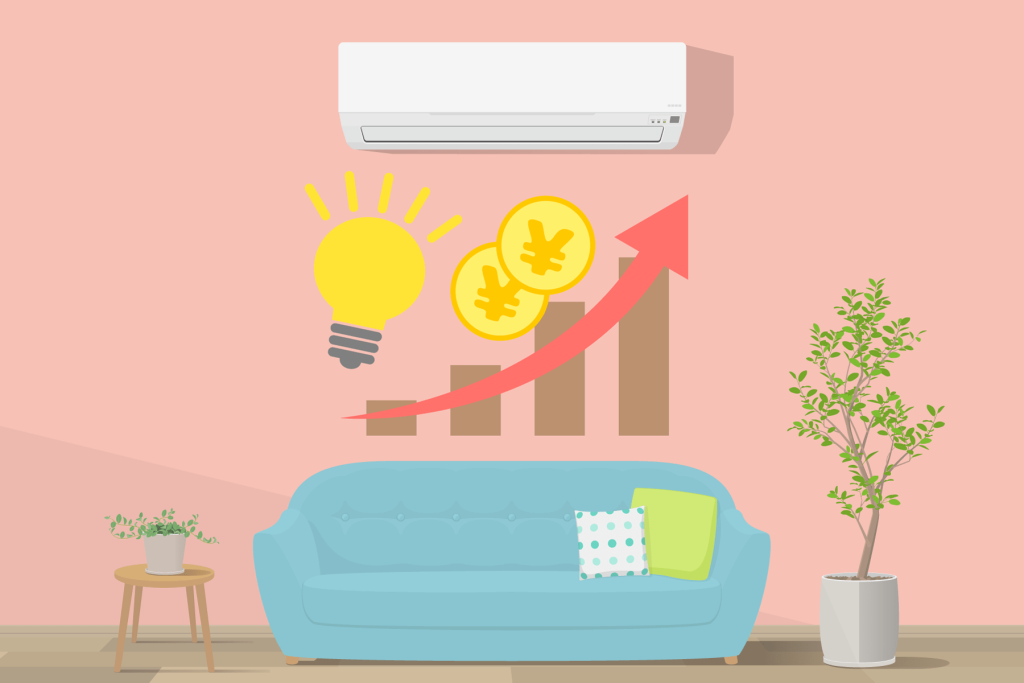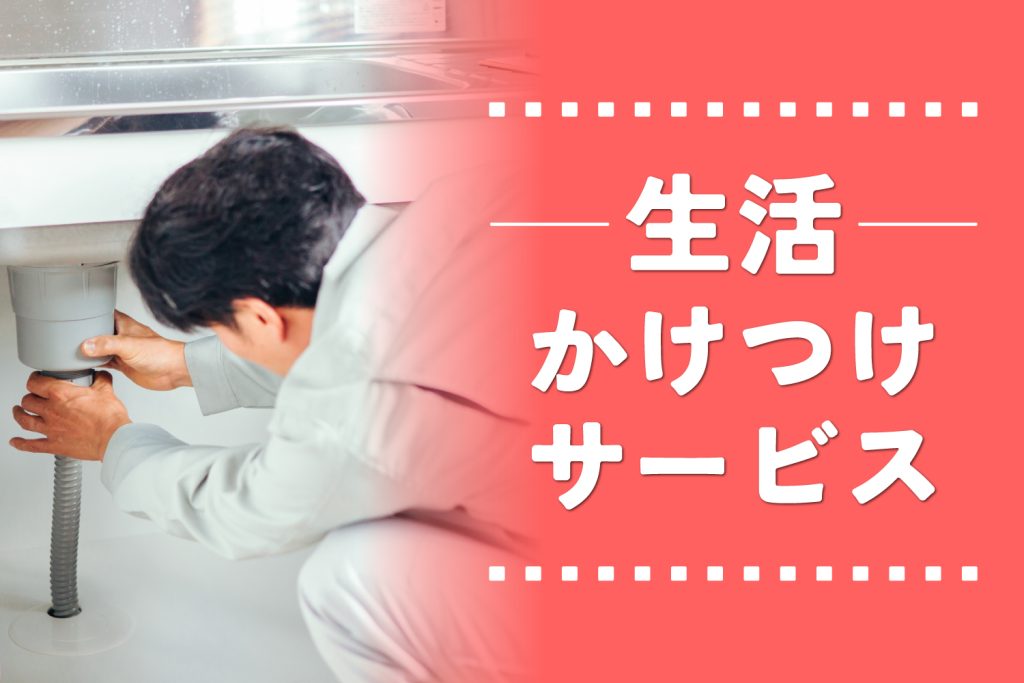【家電別】電気代の節約方法16選!チェックリスト付き
この記事では、主な家電の電気代の節約方法について解説します。家庭ですぐに実践できる内容を紹介しますので、ぜひ今日から取り組んでみてください。
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

目次
【世帯人数別】1か月の電気代の平均はどのくらい?
2025年に総務省が公表した調査によると、世帯人数別の1か月の電気代の平均は、以下の表のとおりです。
| 世帯人数 | 1か月の電気代平均額 |
|---|---|
| 1人 | 6,756円 |
| 2人 | 10,878円 |
| 3人 | 12,651円 |
| 4人 | 12,805円 |
| 5人 | 14,413円 |
家電の使い方やライフスタイルを見直すことで、電気代は節約できます。ここからは、主な家電の電気代の節約方法について解説しますので、できるところから実践してみてください。
エアコンの電気代節約方法
エアコンは、適切な設定をすることで運転効率が向上し、電気代の節約につながります。節約のためにできることがたくさんあるので、できることから始めてみてください。
- ▼フィルターを定期的に掃除する
- ▼設定温度を1℃変更する
- ▼風量を「自動」に設定する
- ▼風向を調節する
- ▼サーキュレーターを使い、空気を循環させる
- ▼室外機に直射日光を当てない
- ▼室外機の周りは整理整頓する
フィルターを定期的に掃除する
エアコンのフィルターは、2週間に1度のペースで掃除するようにしましょう。フィルターにホコリが溜まって目詰まりを起こすと、エアコンの効率が悪くなり、その分電力消費が増えてしまいます。
経済産業省も月に1~2回程度のフィルター掃除を推奨しており、フィルターが目詰まりした状態のエアコン(2.2kW)と、フィルターを清掃したエアコンを比較すると、年間で約31.95kWhの電気を節約でき、金額にすると約990円の節約につながるとしています[2]。
また、自分では手入れが難しいエアコン内部にもホコリは蓄積していきます。定期的に専門業者にクリーニングを依頼することで、余分な電力の使用を防げます。
設定温度を1℃変更する
エアコンの設定温度を1℃調整するだけで、消費電力を抑えられます。環境省の発表によると、夏は設定温度を1℃高くすることで約13%、冬は1℃低くすることで約10%の消費電力量を削減できるとされています[3]。
設定温度を変更するときは、外気温と室内温度の差が少なくなるように、設定温度を調整するのがポイントです。ただし、設定を抑えすぎると体調に影響するため、後述する風向の調整やサーキュレーターの併用などにより、快適さを維持しましょう。
風量を「自動」に設定する
エアコンの風量を「自動」に設定しておくと、余分な電力の消費を抑えられます。風量の自動運転モードは、室温に合わせて風量を自動的に調整する仕組みです。
この自動運転を利用することで、エアコンは室温に応じた最適な風量で稼働し、冷房・暖房のどちらにおいても効率的に運転します。手動で風量を調整する手間もなくなり、冷暖房効率の向上にもつながります。
風向を調節する
空気は、暖まると上に、冷えると下に移動する性質があります。そのため、暖房時には風向きを下向きに、冷房時には上向きに設定すると、空気が部屋全体にバランスよく循環し、室温を均一に保てます。これにより、不要な温度調整が減り、結果的に電気代の節約にもつながります。
ただし、エアコンの風が直接肌に当たると乾燥の原因になるため、風が体に当たらないように角度を調整しましょう。
サーキュレーターを使い、空気を循環させる
サーキュレーターとエアコンを併用すると、空気を部屋全体に効率よく循環でき、設定温度を緩めても快適に過ごせるようになります。これにより、エアコンの負担が軽減され、電気代の節約にもつながります。
暖房時はサーキュレーターを部屋の中心に設置して、風向きを天井に向けると良いでしょう。冷房時はエアコンの向かい側へ設置し、風向きはエアコンに向けるように斜め上に設定すると効果的です。
室外機に直射日光を当てない
室外機には日除けを設けるか日陰に設置して直射日光を避けることが大切です。室外機が高温になると、室内の熱をうまく排出できず、余分な電力を消費してしまいます。日陰の確保や遮熱対策を行うことで、エアコンの運転効率を高め、電気代の節約につながります。
室外機の周りは整理整頓する
室外機のまわりに物が置かれていると排熱の効率が低下し、余分な電力を消費します。落ち葉や雪、植木鉢などの障害物を避け、風通しを良くすることが大切です。
とくに冬の時期は、積雪や凍結によって室外機の吹き出し口付近が覆われないよう注意し、定期的に状態を確認することで暖房の効率を保てます。
冷蔵庫の電気代節約方法
冷蔵庫の電気代節約方法は、以下の5つです。
冷蔵室内に食材を詰め込みすぎない
冷蔵室内に食材を詰め込みすぎないことは、節約の第一歩です。冷蔵室にぎゅうぎゅうに食材を詰め込むと、冷気循環効率が下がって冷えにくくなり、余計な電力を消費します。庫内は1段ごとにスペースを開けて、冷気の通り道を作りましょう。
なお、冷蔵室に適切なスペースを作るためには整理整頓が必須です。整理をすることで、「目の届かないところにあったせいで食材が消費できなくなる」というあるあるを防ぐことにもつながります。
一方、冷凍室は逆に食材をぎっしり詰めた方が効率的です。冷凍された食品が保冷材の役割を果たし、温度変化を防ぎます。
設定温度を調整する
多くの冷蔵庫には温度を調整できるスイッチが搭載されており、冷却力を弱めるほど電気代の節約になります。冷蔵庫周辺の室温や食材の量によって適した強さは異なるため、状況に合わせて「強・中・弱」の設定を調整することが大切です。不必要に冷やしすぎないよう、庫内の状態を見ながら適切な温度にしておきましょう。
目安として、外気温の高い夏は「中」に、反対に外気温が低い冬は「弱」に設定するのがおすすめです。ただし、食材の量が多かったり、傷みやすい生ものを冷やしたりする場合には、庫内を適切な温度に維持できるように調整する必要があります。
ムダな開け閉めをしない
ムダな開け閉めをしないことも大切です。冷蔵庫の扉を頻繁に開け閉めしていると、庫内の温度が上がり、再度庫内を冷却するために余分に電力を消費します。
扉の開閉頻度を減らすためにも、取り出したらすぐに閉め、扉が開いている時間をなるべく少なくすることがポイントです。食材を整理整頓し、必要なものをすぐに取り出せるようにしておきましょう。
温かいものは冷めてから冷蔵庫に入れる
温かいものは、冷めてから冷蔵庫に入れるようにしましょう。温かい状態の食べ物をそのまま入れると庫内の温度が上昇し、温度を戻すために余分な電力を消費します。さらに、温度の上昇によって、他の食品・食材にも影響を及ぼすおそれがあります。
調理したばかりの食べ物はすぐに冷蔵庫に入れず、しっかりと冷ましてから入れるよう習慣化しましょう。
壁と適切な距離を離して冷蔵庫を設置する
冷蔵庫を設置するときは、壁と適切な距離を離してください。冷蔵庫と隣り合う家電や壁などの間にスペースを作ることで熱を効率よく放出でき、節電につながります。
冷蔵庫の周囲に適切な隙間がないと放熱できず、庫内に熱がこもり、冷やすために余計な電力を消費してしまいます。機種によっては、冷蔵庫の背面にもスペースが必要な場合がありますので、説明書やカタログでしっかりと確認しましょう。
洗濯機の電気代節約方法
洗濯機の電気代節約方法のポイントは、以下の3つです。
容量80%をめどにまとめ洗いをする
洗濯物はなるべくまとめて洗い、洗濯回数を減らしましょう。洗濯物の量が少ない日は洗濯機を回さず、翌日分あるいは数日分まとめて一緒に洗うのがおすすめです。ただし、詰め込みすぎると汚れが落ちにくくなるため、洗濯機の容量に対して80%を目安にしてください。
家族や着替える機会が多く、毎日洗濯せざるを得ないときは、洗剤を必要以上に入れない、風呂の残り湯を使う、といった工夫がおすすめです。さらに、洗濯物は重いものから順に入れるなど、入れ方を工夫するだけでも節電につながります。
「おいそぎコース」や「省エネコース」で洗う
洗濯機に搭載されている「省エネコース」「おいそぎコース」で洗うのもおすすめです。省エネコースは標準モードよりも消費電力を抑えて洗濯できます。
おいそぎコースは洗濯・乾燥時間を短くすることで消費電力を抑えます。機種によって「スピードコース」「倍速モード」「時短モード」など名称が異なるため、お手持ちの機種の表示を確認してください。
ただし、「省エネコース」は乾燥時間が長くなる、「おいそぎコース」はすすぎや脱水の回数が減る、など標準モードと運転内容が変わります。頑固な汚れやニオイが気になるときは標準コースでしっかり洗うようにしましょう。

脱水をしてから乾燥機を使う
乾燥機を使用する場合は、洗濯物をしっかりと脱水してから乾燥機に入れることが大切です。脱水しきれずに水分が多く残ってしまうと、乾燥時間が長くなり、電気代が余計にかかります。
とくに、タオルやデニムといった厚手の生地は水分を含みやすいため、他の衣類よりもしっかり脱水することで、乾燥時間を短縮できるでしょう。
また、すすいだだけの濡れた衣類を乾燥機にかけるよりも、脱水してから乾燥機にかける方がモーターにかかる負荷を軽減できます。洗濯機の寿命をのばし長く使用するためにも、脱水が不十分な状態の衣類をそのまま乾燥機にかけることは避けてください。
その他の家電の電気代節約方法
その他の家電にも、節約方法はあります。今回紹介するのは、以下の家電です。
- ▼テレビの節電方法
- ▼トイレ(温水洗浄便座)の節電方法
- ▼IHコンロ(クッキングヒーター)の節電方法
- ▼電子レンジの節電方法
- ▼炊飯器の節電方法
- ▼加湿器の節電方法
- ▼照明の節電方法
- ▼こたつ・ホットカーペットの節電方法
各家電の節約方法を詳しく解説します。
テレビの節電方法
テレビは「〇〇しすぎない」ことが節約のポイントです。
- 画面を明るくしすぎない
- 画面が明るくなるほど、消費電力が上がります。また、暗い部屋で明るい画面を見続けると目に負担がかかるので、適度な明るさに調整しましょう。
- 音量を大きくしすぎない
- 音量を上げると、消費電力が上がります。同居人や近隣住人に配慮し、適度な音量に調整しましょう。
- 見ないときは消す
- つけっぱなしはムダに電力を消費しますので、見たい番組がないときはテレビを消しましょう。

トイレ(温水洗浄便座)の節電方法
トイレは、機能を調整・制限することで節電できます。
- 洗浄水や暖房便座の設定温度を低めに
- 常に高温設定だと消費電力が上がります。夏場はオフにする、寒い時期も設定温度を上げすぎない、など季節や室温に合わせて設定します。
- 使用後にフタを閉める
- 暖房便座機能を使っている場合、フタを開けっ放しにすると便座が冷えやすくなり、温度を保つために余計な電力がかかります。使用後にフタを閉めると便座の熱が逃げにくくなり、節電につながります。
IHコンロ(クッキングヒーター)の節電方法
IHコンロはガスではなく電気で鍋やフライパンを温めます。電子レンジで下ごしらえをしてから調理する、など時短を意識することで節電につながります。
- 調理器具の水滴を拭き取る
- 鍋やフライパンが濡れた状態でIHコンロにかけると、その水分を蒸発させることにも電力が消費されてしまいます。調理器具についた水滴は、あらかじめ丁寧に拭き取っておくことで、ムダな電力消費を防いで効率良く加熱できます。
- 余熱で保温調理をする
- 時間と手間はかかりますが、火を止めたあとの余熱を活用することでIHコンロの使用時間が減り、節電につながります。時間はかかりますが、味がよく染みこみ、さらにおいしい仕上がりが期待できるでしょう。
- 圧力鍋や無水調理鍋を使う
- 圧力鍋は鍋を密閉することで通常よりも高温で加熱できるため、時短調理が可能です。また、無水調理鍋は食材から出た水分のみで調理する仕組みで、お湯を沸かす必要がなく、節電にも効果的です。
電子レンジの節電方法
電子レンジは、使用回数や加熱時間を抑えることで節電に繋がります。
- 冷凍した食材は自然解凍する
- 先に自然解凍しておくと、加熱時間の削減につながります。ただし、生肉の自然解凍は望ましくありませんので、注意してください。
- ラップや耐熱容器のフタを使用
- 熱が逃げにくくなり、節電につながります。電子レンジ調理の際、食材が重ならないように並べるのもポイントです。
炊飯器の節電方法
炊飯器でご飯を炊く際は、こまめに少量ずつ炊くよりも、1度にたくさん炊いた方が節電効果は高いです。
- まとめて炊いて冷凍保存する
- 1度にまとめて炊き、小分けにして冷凍保存することで、節電・節水につながります。
- 未使用時は電源プラグを抜く
- コンセントに電源プラグをつないだままだと、炊飯時や保温時以外にも待機電力がかかってしまいます。炊飯器を使わないときは、電源を抜いておきましょう。
- エコモードやタイマーを活用する
- エコモードが搭載された炊飯器は、通常モードよりも電気代を抑えて炊飯できます。また、タイマー機能があると食事の時間に合わせて炊き上がるようにセットできるため、保温時間の削減とともに電気代の節約も可能です。
- 9時間以上の保温を避ける
- 保温を9時間以上続けると、電気代は炊飯1回分とほぼ同じになります。保温時間が長いと食感や風味にも影響しますので、長時間の保温は避けましょう。
加湿器の節電方法
加湿器の節電には、置く場所や使い方の工夫が効果的です。
- 床から70~100cm高い場所に設置
- 温かい空気は上に、冷たい空気は下に溜まる性質があり、床から離して設置することで効果的に使用できます。
- タイマー機能を使用する
- 設定した時刻になると自動的に電源がオフまたはオンになるタイマー機能を活用すると、つけっぱなしによるムダな電力消費を防げます。
- 濡らしたバスタオルを干す
- バスタオルの水分が蒸発して室内の湿度が上がるため、加湿器などの家電の使用時間を抑えられます。
照明の節電方法
照明は使用頻度が高い必需品ですが、少しの工夫が節電につながります。
- 定期的に掃除する
- ホコリが溜まると暗く感じて、明るさを上げがちです。定期的に掃除をすれば設定を変えずに明るさをキープできます。
- 使わないときは消す
- つけっぱなしはムダな電力を消費するので、使わないときはこまめに電気を消す習慣をつけましょう。家族がいる場合は、なるべく同じ場所に集まって過ごすことで、使用する照明の数を減らせます。
- 調光機能つきのモデルに買い替える
- 調光機能つきの照明器具は、明るさを1段階下げるだけでも節電効果が期待できます。
- LED電球に替える
- 例えば、54Wの白熱電球から7.5Wの電球形LEDランプに替えた場合、年間で約2,883円の電気代を節約できます[4]。LED電球は従来型の白熱電球よりも購入費用は高いものの、寿命が長いため、頻繁に交換する必要がなく、交換の手間やコストも抑えられます。

こたつ・ホットカーペットの節電方法
部分暖房としてはとてもコスパが良い暖房器具のこたつとホットカーペットですが、使い方を工夫することでさらなる節電が可能です。
- 断熱マットを活用する
- 床とこたつ、または床とホットカーペットの間に断熱マットを敷くと、床からの冷気が遮断されて熱を逃がしにくくなり、必要以上の電力消費を防げます。
- 設定温度を調整する
- はじめは「強」に設定しておき、ある程度温まってきたら「中」や「弱」に切り替えると、節電効果が期待できます。温める範囲を設定できるホットカーペットなら、半面のみを温めるのもおすすめです。残りの半面には電力を消費しないので、節約につながります。
【この機会に見直したい】電気代の節約につながる行動
ここからは電気代に直結する電気料金の契約、家電の買い替え、待機電力の見直しについてご紹介します。ここを再検討し、コストを抑える行動が、電気代の節約につながります。
契約している電気料金の契約プランを見直す
最適な電気料金プランは、家族の人数や生活リズム、使用している家電の種類や使い方によって異なります。例えば、同時に使用する家電の数が少ない家庭では、契約するアンペア数を下げることで基本料金を抑えられる場合があります。自分の家庭に合ったプランを選ぶことで、無理なく効率的に電気代を節約できます。
また、契約中の電力会社がプラン内容を変更したり、新しいおトクなプランを提供したりしている可能性もあるため、定期的に契約内容を見直すことをおすすめします。
省エネ性能の高い最新家電に買い替える
家電の省エネ性能は年々向上しています。そのため、古い家電を使い続けるよりも、省エネ性能の高い新しい製品に買い替えることで、長期的に見れば電力消費を抑え、節電につながる場合があります。
参考として、主な大型家電の平均使用年数は以下のとおりです。
| 家電の品目 | 平均使用年数 |
|---|---|
| 電気冷蔵庫 | 13.5年 |
| 電気洗濯機 | 10.0年 |
| 電気掃除機 | 7.2年 |
| ルームエアコン | 14.2年 |
| カラーテレビ | 10.5年 |
待機電力を見直す
家庭で消費される電力のうち、およそ5.1%が「待機電力」とされています[6]。
待機電力とは、電気製品を使用していなくても、コンセントにプラグが差し込まれていることで消費される電力のことです。とくに、ガス給湯器の操作パネルやテレビ、温水洗浄便座(暖房便座)などは待機電力が比較的大きいため、使用していないときは電源を切るか、コンセントを抜くことで節電効果が期待できます。
ただし、コンセントを頻繁に抜き差しするとプラグの劣化や故障につながるおそれがあります。個別スイッチ付きの電源タップを活用すれば、コンセントを抜かずに電源をOFFにできるため、安全かつ効率的です。
まとめ
電気代の節約は、普段の生活の合間にできる小さな意識や工夫が大切です。例えば、エアコンは設定温度の見直しや定期的なフィルター掃除、冷蔵庫は庫内整理と開け閉めを減らすこと、洗濯はまとめ洗いを意識することで、節電に繋がります。その他の家電も、設定の見直しや待機電力を切るだけで節電効果が期待できます。
この記事を参考に、できることから電気代の節約を始めてみてください。
- 総務省統計局:
「家計調査 / 家計収支編 / 二人以上の世帯 / 第2-7表 / 4人世帯(有業者1人)年間収入階級別1世帯当たり1か月間の収入と支出」[2024年調査、2025年2月7日公開] - 経済産業省 資源エネルギー庁:
空調|無理のない省エネ節約 - 環境省:
エアコンの使い方について - 経済産業省 資源エネルギー庁:
照明 | 無理のない省エネ節約 - 内閣府経済社会総合研究所景気統計部:
消費動向調査(令和7年3月実施調査結果) - 一般財団法人 関東電気保安協会:
待機時消費電力とは
この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事


![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)
![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)