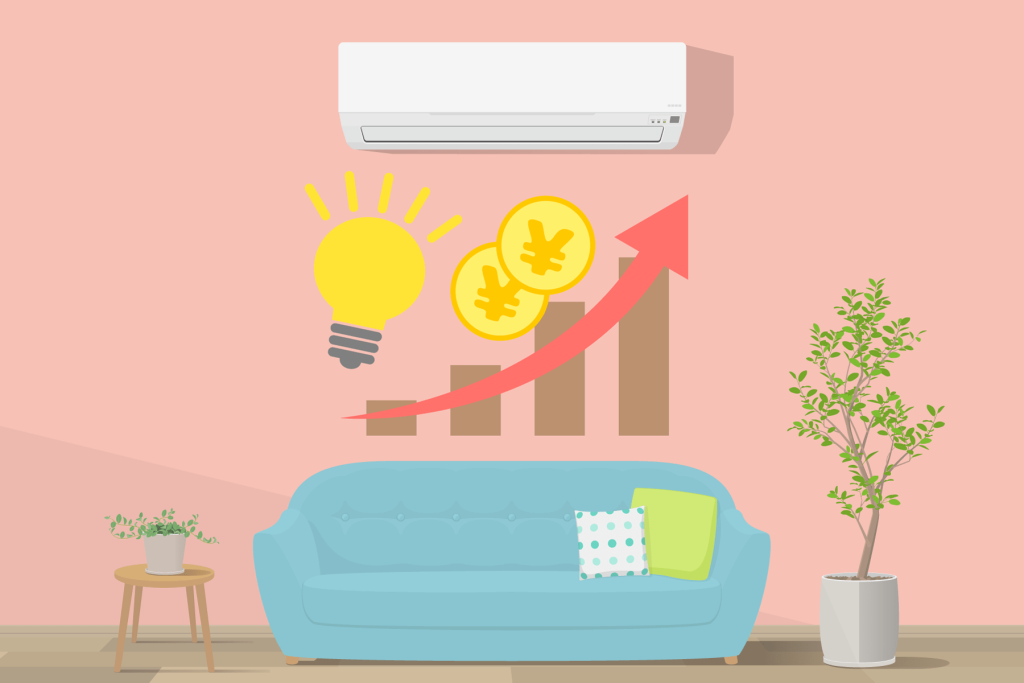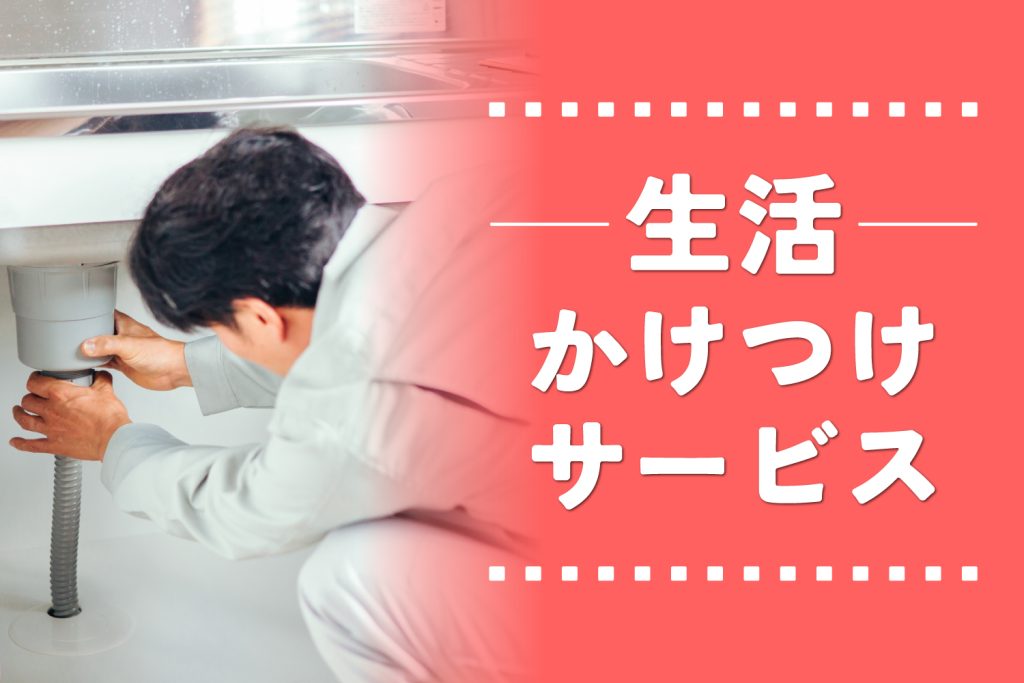冷凍庫の適正温度は-18℃以下!温度が高くなる原因や対処法を解説
JIS規格によると、冷凍庫の適温は-18℃以下です。しかし、さまざまな原因で冷凍庫の温度が適温よりも高くなってしまう場合があります。
冷凍庫の温度が高くなると、食品の品質が低下したり、微生物が繁殖したりするため、注意が必要です。今回の記事では、冷凍庫の温度が高くなる原因や高くなってしまったときの具体的な対処法まで詳しく解説します。
目次
冷凍庫の適正温度は-18℃以下
冷凍庫の適正温度は、国家規格であるJIS規格によって-18℃以下と定められています[1]。-18℃に定められている理由としては、微生物が繁殖しづらく、食品の品質や安全性が保たれるからです。
ただし、開封して以下の状態になっているものは、品質が損なわれている可能性があるため注意が必要です。
- 乾燥が進んでいる
- 変色している
- 霜が極端に付着している
- 固まりになっている
また、冷凍庫のドアポケットは開閉時に外の気温の影響を受けやすいため、ドアポケットに収納した食品は通常よりも品質が保たれる期間が短くなることも覚えておきましょう。

冷凍庫の温度が高くなる原因と対処法
冷凍庫の温度が高くなる原因には、頻繁に扉を開閉したり、温かいものをすぐに入れてしまったりなどの「習慣によるもの」と、コンプレッサーの力の低下などの「冷蔵庫自体の問題」の2つが挙げられます。
ここからは、冷凍庫の温度が高くなる原因と対処法を解説します。
扉の開閉頻度が高い
冷凍庫の扉を頻繁に開閉すると、庫内の冷気が逃げやすくなり、温度が上昇する原因になります。そのため、対策として、どこに何を保存したかを把握しておく工夫が有効です。
冷凍用保存袋や透明な容器などに食品を入れて保存することで、冷凍庫を開けたときに場所と中身が一目で判断できます。これにより、開閉の頻度を減らしたり、ドアを開けている時間を短くしたりすることができ、温度の上昇を防げます。
扉が閉まりきっていない
冷凍庫の扉が完全に閉じていないと、隙間から冷気が逃げ、庫内の温度が上昇してしまいます。原因としては、食品や容器が扉に引っかかっていることが多いです。そのため、食品を冷凍庫に入れる際には整理整頓を心掛けましょう。
また、閉めた際に軽くドアを押してきちんと扉が閉まっているか確認することをおすすめします。
冷蔵庫が壁に近すぎる
冷蔵庫を壁に近づけすぎると、背面や側面からうまく放熱できず、庫内の温度が上昇する原因になります。正常な放熱ができないと、冷却機能が低下し、保存している食品の品質が悪化する可能性があります。
冷蔵庫と壁の正しい設置距離は、取扱説明書で確認してください。機種にもよりますが、一般的な設置距離の目安は、背面は5〜10cm以上、側面は5cm以上、上部は5cm以上です。
霜がついた状態
冷凍庫内に霜がついていると、庫内の冷気が循環しなくなり、冷却能力が落ちてしまいます。冷却能力が落ちると冷凍庫の温度が徐々に上昇し、食品の品質が悪くなる原因になります。
冷凍庫の霜は以下の手順で取り除けます。
- 冷蔵庫の中身をすべて取り出し、クーラーボックスや発泡スチロールに移す。
- 冷蔵庫の電源を切る。
- 扉を開けたままにし、霜を溶かす。空けておく時間の目安は、夏は約10時間、冬は約15時間。
- 霜を取り除いたら、冷凍庫の中を乾燥させ、食品を戻す。
霜は冷凍庫の内と外の温度差が大きいほど発生しやすくなります。とくに、夏場は室温が高く、冷凍庫内との温度差が大きくなりやすいです。定期的に庫内を確認し、霜取りを行いましょう。

料理を温かいまま冷凍庫に入れている
料理を温かいままの状態で冷凍庫に入れると、庫内の温度が上昇してしまいます。そのため、料理を冷凍庫に入れるときは、粗熱を取ってから入れましょう。
また、食品を冷凍するときは、熱伝導率が高い金属製トレイを活用すると、効率的に冷やせます。
パッキンの異常
冷凍庫の扉に付いているパッキンが劣化すると、隙間ができ、扉が正常に閉まらない場合があります。また、パッキンは気づかないうちに食品の小さなごみやホコリが溜まって汚れやすい場所のため、定期的に確認して掃除する必要があります。
劣化したパッキンを放置して使い続けると、隙間から庫外の空気が入り込み、冷却機能が故障してしまう可能性もあるため、早めにメーカーや修理業者に依頼して交換しましょう。

コンプレッサーの力が落ちている
冷凍庫の温度が上昇する原因には、コンプレッサーの性能低下も挙げられます。コンプレッサーとは、冷蔵庫内の冷媒を循環させて冷気を生み出す部品です。
冷媒を補充すれば、一時的に持ち直す場合もありますが、冷蔵庫が古い場合は再発する可能性も十分考えられるため、早めの買い替えを検討しましょう。
冷凍庫の温度設定は季節ごとに変えよう
冷凍庫は庫外の気温の影響を受けやすいため、適切な庫内の温度を保つには、季節に合わせて最適な温度に設定することをおすすめします。設定温度が適切でないと、食品が解凍・再冷凍を繰り返してしまい、風味が落ちたり品質低下を引き起こしたりする可能性があります。
とくに、夏は気温が高く、冷凍庫内の温度も上がりやすくなるため、冷凍庫の温度設定を「強」にし、しっかりと冷却して食品の品質を守りましょう。反対に、冬は気温が低いため、温度設定を「弱」にしても十分に冷凍機能を保てます。春と秋は気温が安定しているため「中」がおすすめです。
食品の品質を保つために、季節ごとの温度設定を習慣づけましょう。
購入から9年以上の冷蔵庫は修理より買い替えがおすすめ
冷蔵庫の寿命は9~13年とされています。購入後9年以内の冷蔵庫が故障したときには修理を検討し、9年を過ぎた冷蔵庫は新しいものに買い替えるのがおすすめです。
家電メーカーには製品の部品を保有しておく期間が定められていて、冷蔵庫の場合には、製造終了後9年間が義務づけられています[2]。内閣府調査では、冷蔵庫の平均使用年数は13年[3]とされていますが、購入から9年を超えると、故障しても修理できないケースが発生します。
また、冷蔵庫の機能や性能は年々向上しており、最新モデルの冷蔵庫では、適切な温度管理で食品の保管期間が延びたり、省エネ性能の向上で大幅に節電できたりしています。長期的な視点で見ると、新しい冷蔵庫に買い換えることで、食費や電気代を節約できる可能性があるでしょう。
まとめ
冷凍庫の温度が高くなる原因には、パッキンやコンプレッサーの問題などの冷蔵庫本体の異常と、扉を頻繁に開閉するなどの普段の習慣が考えられます。
とくに、頻繁に冷凍庫を開閉したり、温かいものをそのまま入れてしまったりすると、冷蔵庫本体に異常がなくても冷凍庫の温度が上がってしまう可能性があります。
冷凍庫内の温度が高い状態が続けば、食品の品質低下や微生物繁殖のリスクが高まるため、注意が必要です。季節ごとに最適な温度設定を心がけて、電気代を節約しながら食品の品質を適切に保ちましょう。
- 経済産業省
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の JIS改正について [PDF] - 公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会
補修用性能部品表示対象品目と保有期間
- 内閣府
消費動向調査 令和5年3月実施調査結果 [PDF]
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事


![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)
![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)