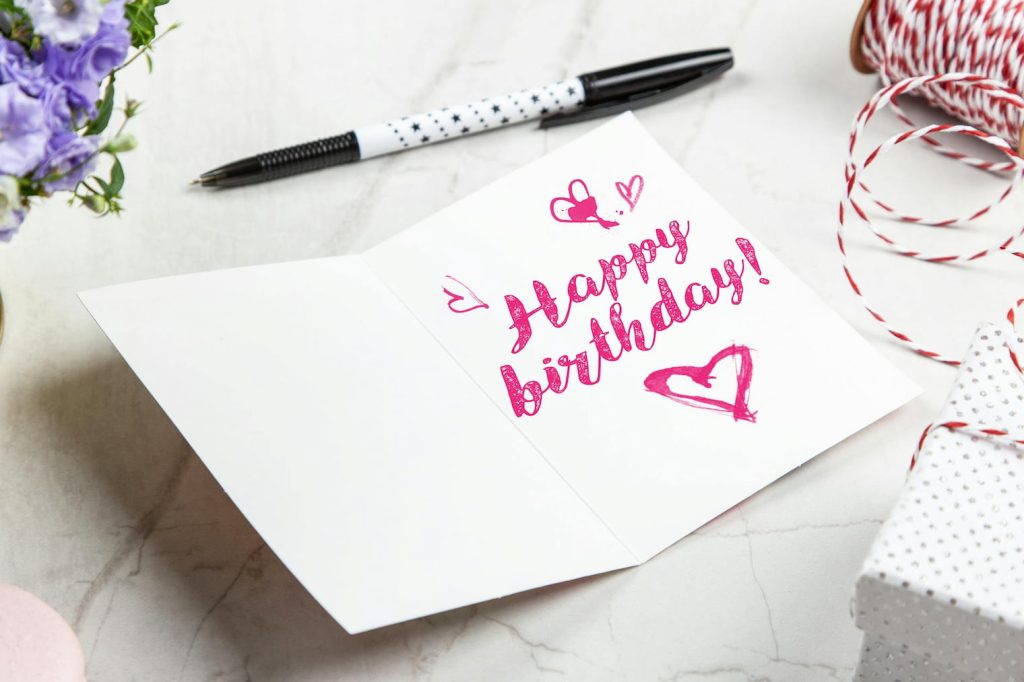【2025年】ハロウィンはいつ?起源や由来、過ごし方を解説
この記事では、2025年のハロウィンの日付や、起源や由来について分かりやすく解説します。子どもと一緒に楽しめるハロウィンの過ごし方も紹介しますので、この記事を参考に、ハロウィンパーティーを楽しんでみてください。
ハロウィンはいつ?【毎年10月31日】
ハロウィンは、毎年10月31日に行われる行事です。イースター(復活祭)やサンクスギビングデー(感謝祭)のように毎年日付が変わる祝祭日とは違い、ハロウィンの日付は固定されています。
日本でも、ハロウィンは仮装やコスプレをして楽しむ秋のイベントとして広く知られています。商業施設やテーマパークでは10月になると、かぼちゃやおばけなどの飾り付けが始まります。
2025年のハロウィンは10月31日(金)です。今年のハロウィンは金曜日のため、お祝いやイベントが楽しみやすいかもしれません。近年のハロウィンの日付と曜日を以下の表にまとめました。
| 年 | ハロウィンの日付・曜日 |
|---|---|
| 2024年 | 10月31日(木) |
| 2025年 | 10月31日(金) |
| 2026年 | 10月31日(土) |
| 2027年 | 10月31日(日) |
| 2028年 | 10月31日(火) |
なぜ10月31日?その理由はハロウィンの起源に由来
ハロウィンが毎年10月31日に行われる理由は、ハロウィンの起源とされる古代ケルト人の宗教儀式「サウィン祭」に由来します。
約2,000年以上前に現在のアイルランド、イギリス、フランス北部などに住んでいた古代ケルト人にとって、1年の終わりは10月31日で、11月1日からが新年とされていました。そして、10月31日の夜からその翌日にかけて行われていた祭りがサウィン祭です。
サウィン祭は秋の収穫を祝い、新年を迎える祭りとして開催されていました。日本のお盆のように、この日は死者の霊がこの世に戻ってくるとされ、先祖を敬い、迎える日でもあったのです。
ケルト文化とキリスト教の結びつきもハロウィンの文化に影響
ヨーロッパでキリスト教が広まると、ケルト文化はキリスト教の行事と融合していきます。8世紀ごろには、11月1日は「万聖節(ばんせいせつ:All Saints' Day)」、その翌日の11月2日は「万霊節(ばんれいせつ:All Souls' Day)」として、すべての死者の魂のために祈りを捧げる日となりました。
そして、ケルト文化であるサウィン祭の「収穫祭」「新年を迎える準備」「死者の霊を弔う」という要素と、キリスト教の聖人や死者を追悼する行事が融合し、10月31日の夜に行われる現在のハロウィンにつながっていきました。
ちなみに、「ハロウィン(Halloween)」という名前は、「万聖節」の前夜祭である「All Hallows' Eve」が、なまって短縮されたものだとされています。「Hallow」は古い英語で「聖人」を意味します。
ハロウィンの飾り付けはいつからいつまでが一般的?
ハロウィンの日付は10月31日ですが、街の雰囲気やイベントムードはもっと早くから始まりますよね。ご家庭で飾り付けを楽しむ場合、いつからいつまでするのが一般的なのでしょうか。
とくに決まりはありませんが、海外では9月下旬から10月上旬ごろに飾り付けを始める方が多いようです。日本でも、9月になると雑貨店や100円ショップなどにハロウィングッズが並び始めますので、そのタイミングで準備を始めるとスムーズでしょう。
そして、片付けるタイミングはハロウィン当日の10月31日が終わった後、すぐというのが一般的です。11月に入ると、街はあっという間にクリスマスムードに切り替わっていきます。ハロウィンの余韻に浸りつつ、早めに片付けるのがスマートなマナーといえるでしょう。

日本と海外のハロウィンの違い:日本のハロウィンはいつ始まった?特徴は?
日本と海外では、ハロウィンの楽しみ方にいくつかの違いが見られます。海外、とくにアメリカやカナダ、アイルランド、イギリスなどのハロウィンは、日本のお盆のように宗教に基づく慣習的な要素が強いです。
ここからは、日本と海外のハロウィンの違いについて解説していきます。各国のハロウィン文化の違いや、「日本のハロウィンはいつから始まった?」といった疑問に一つずつお答えしていきます。
- ▼日本のハロウィン:商業イベントとして始まり、仮装を楽しむ日として定着
- ▼アメリカ・カナダのハロウィン:子どものためのお祭りの意味合いが強い
- ▼アイルランドのハロウィン:「サウィン祭」の雰囲気が残る伝統的な祝祭日
- ▼イギリスのハロウィン:アメリカ・カナダやアイルランドに比べて小規模
日本のハロウィン:商業イベントとして始まり、仮装を楽しむ日として定着
日本のハロウィンは1970年代後半に、全国菓子協会が「ハロウィンキャンペーン」を開催したことが始まりとされています。それまで、10月はお菓子の購買につながるようなイベントがなかったため、新たな販促の機会としてハロウィンを取り入れたのです。
その後、原宿の雑貨店がハロウィングッズの販売に力を入れるようになったことも、日本のハロウィン文化の起点です。1980年代には、同店がハロウィンの仮装パレードを実施したことがメディアに取り上げられ、ハロウィンの知名度が徐々に上がっていきました。さらに、1990年代からはテーマパークでのハロウィンイベントも始まり、今では秋の風物詩として定着しています。
そのような背景から、日本のハロウィンは商業的要素が強く、子どもだけではなく大人も積極的に仮装を楽しむのが特徴です。伝統的なお化けや魔女の衣装だけでなく、アニメやゲームのキャラクターのコスプレをする人も多く、仮装を自由に楽しむ独自の文化として海外からも知られています。

アメリカ・カナダのハロウィン:子どものためのお祭りの意味合いが強い
アメリカやカナダのハロウィンは、主に「子どもたちのためのお祭り」です。
子どもたちは思い思いの仮装をして、近所の家を「トリック・オア・トリート!」と言って回り、たくさんのお菓子をもらうのがメインイベントです。大人たちは、家を不気味に飾り付けたり、子供たちのためにパーティーを開いたりして、地域全体でイベントを楽しみます。
アイルランドのハロウィン:「サウィン祭」の雰囲気が残る伝統的な祝祭日
ハロウィン発祥の地であるアイルランドでは、ハロウィンは伝統的なお祭りとして今も盛大に祝われています。各地でパレードや花火が打ち上げられ、焚き火を囲んでゲームをするなど、国を挙げての一大イベントとなっています。
アメリカやカナダ、イギリスなどと比較すると、古代ケルト文化である「サウィン祭」の伝統的な雰囲気を色濃く残しているのが特徴です。
イギリスのハロウィン:アメリカ・カナダやアイルランドに比べて小規模
イギリスのハロウィン文化は、一度アメリカに渡ってから逆輸入される形で入ってきました。しかし、イギリスの秋には伝統的に「ガイ・フォークス・ナイト」(毎年11月5日)という、花火や焚き火で祝う大きなお祭りがあり、ハロウィンはそれより小規模なイベントです。
イギリスのハロウィンはアメリカほど商業的ではなく、かぼちゃの代わりに元々の風習である「カブ」でランタンを作る家庭もあるなど、古風で素朴な楽しみ方が残っているのが特徴です。
ハロウィンの風習の由来
ハロウィンにはさまざまな風習がありますが、それぞれに興味深い由来があります。ここでは、意外と知らないハロウィンの風習の由来について解説します。
仮装:悪霊を驚かせて追い払う
ハロウィンの仮装は、悪霊払いが由来です。古代ケルトのサウィン祭には、ご先祖の霊とともに、悪霊も現世へ来ると考えられていました。
ケルト人は仮面を被ったり、動物の皮を被ったりして悪霊を驚かせ、追い払おうとしました。また、自分たちも悪霊の仲間だと思わせることで、襲われないようにするためでもあったといわれています。
こういった、元々は危険から身を守るために行われていた仮装の慣習が、現在の仮装を楽しむ文化へと発展し、次第にエンターテインメントの要素が強くなっていきました。

お菓子/トリック・オア・トリート:霊への供え物と祈りの習慣
ハロウィンで子どもたちがお菓子をもらうときに言う、「トリック・オア・トリート」もサウィン祭の風習が起源です。サウィン祭では死者の霊を慰めたり、悪霊を鎮めたりするために、家の前に食べ物やお供え物を置いていました。霊たちが食べ物を受け取って満足し、悪さをしないように願う風習です。
中世ヨーロッパでは、「ソウリング(Souling)」と呼ばれる習慣が生まれました。ソウリングでは、11月2日の万霊節に、貧しい人々が家々を訪ね歩き、「ソウルケーキ(魂のケーキ)」と呼ばれるお菓子と引き換えに、その家の亡くなった人のために祈りを捧げます。
19世紀にハロウィンがアメリカに伝わると、「霊への供え物」の習慣と「ソウリング」の習慣が融合しました。さらに、お菓子をもらえなかった場合にいたずらをするという要素が加わり、「トリック・オア・トリート(お菓子をくれないといたずらするぞ)」と言いながら家々を回る現在のハロウィンになったのです。
ランタン:アイルランドの昔話
ハロウィンの飾り付けとして有名な、かぼちゃをくり抜いたランタンは、「ジャック・オー・ランタン」と呼ばれ、魔除けの意味や先祖の霊を迎える道しるべの意味を持ちます。ジャック・オー・ランタンは、アイルランドの昔話「Stingy Jack(ケチなジャック)」が由来です。
「Stingy Jack」は、「ジャック」という男が何度も悪魔を騙したため、死後に天国にも地獄にも行けず、カブをくり抜いたランタンに火を灯して永遠にさまよっているという話です。「Jack of the Lantern(ジャックのランタン)」が短縮されて、現在の「Jack-o'-Lantern(ジャック・オー・ランタン)」になりました。
アイルランドやスコットランドでは、当初カブやジャガイモをランタンにしていましたが、アメリカに移住したアイルランド人たちが、より大きくくり抜きやすいカボチャを使うようになりました。こうして、現在のかぼちゃのジャック・オー・ランタンの形になったのです。
ハロウィンにおすすめの過ごし方
子どもと一緒に楽しめるハロウィンの過ごし方をご紹介します。意味や由来なども話しながら、イベントやパーティーを楽しみましょう。
仮装パーティー・イベント
ハロウィンといえば、仮装が楽しめるパーティーやイベントがおすすめです。商業施設やテーマパークでは、ハロウィンイベントが開催されます。家族や友人と仮装をして参加するのも良いでしょう。
また、地域のコミュニティセンターや児童館で開催される子ども向けのハロウィンイベントもおすすめです。家族で楽しめるプログラムが充実していることが多く、安心して参加できます。
お菓子・料理作り
ハロウィンならではのお菓子や料理を家族で作るのも楽しい過ごし方です。子どもたちに「トリック・オア・トリート」と言われたときに配るお菓子を作ったり、かぼちゃを使った料理を取り入れたりすると、味覚でもハロウィンを楽しめます。
かぼちゃのスープやパイ、クッキーなど、旬の食材を使った料理は栄養価も高く、季節を感じることができます。かぼちゃは食物繊維やビタミンA、カロテンなどの栄養素が豊富で健康にも良いため、小さな子どもにもおすすめの食材です。
まとめ
ハロウィンは毎年10月31日に行われるイベントで、2025年は金曜日です。この日付は毎年固定で、古代ケルト人の「サウィン祭」の日付に由来するとされています。また、ハロウィンの飾り付けは9月下旬~10月上旬につけ始め、11月に入ったらすぐにしまうのが一般的です。
一口にハロウィンといっても、日本と海外では大きく様子が異なり、アメリカ・カナダとアイルランド、イギリスでも風習は異なります。ハロウィンの歴史や意味、各国での文化の違いを知ることで、イベントをより楽しむことができます。
今年はぜひ、イベントに参加したり、かぼちゃ料理やお菓子を作ったりして、ハロウィンの時期ならではの楽しみ方を見つけてみてください。
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事


![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)
![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)