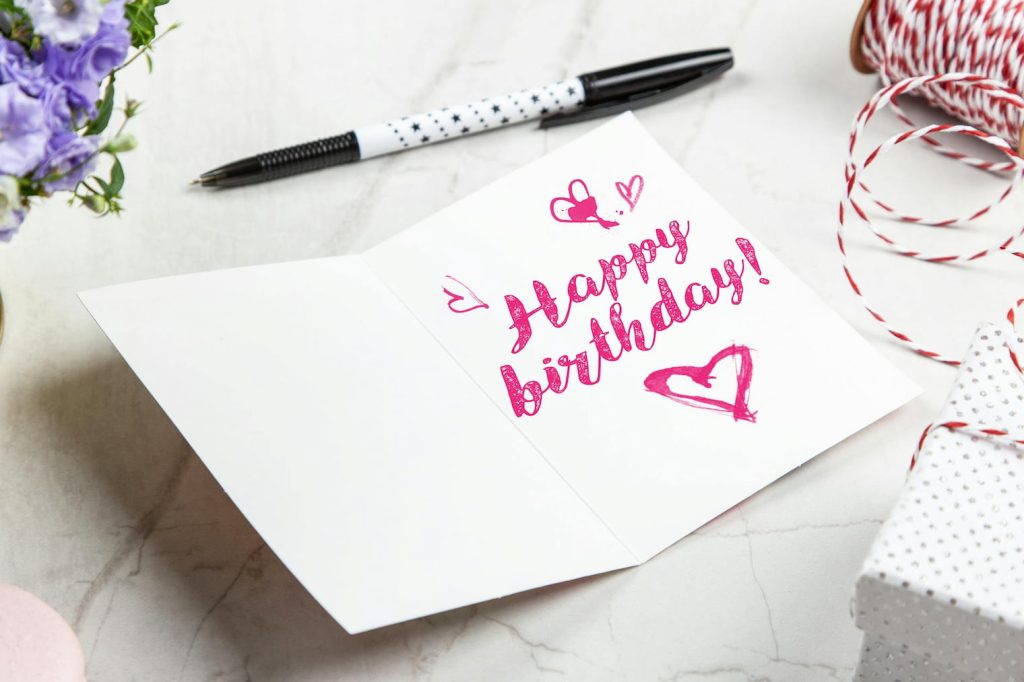【失敗しない】寒中見舞いの例文35選!喪中・年賀状への返信も相手別に解説
この記事では、寒中見舞いの基本的なマナーから、そのまま使える豊富な文例までご紹介します。喪中の場合やビジネスシーンなど、相手・状況別に最適な表現が必ず見つかるはずです。マナーや表現に気をつけ、大切な方へ心のこもったご挨拶を届けましょう。
目次
そもそも寒中見舞いとは?いつ、誰に送るもの?
寒中見舞いとは、一年で最も寒さが厳しい時期に、相手の健康を気遣い、お互いの近況を報告するために送る季節の挨拶状です。厳しい寒さの中、相手を思いやる気持ちを伝える日本の美しい風習の一つといえるでしょう。年賀状のように新年を祝う目的とは異なり、あくまで季節の挨拶状という位置づけです。
送る時期は、正月飾りを飾っておく期間である「松の内」が明けてから、「立春」(暦の上で春が始まる日)の前までとされています。地域によって松の内の期間は異なりますが、一般的には以下のとおりです。立春の日付も年によって変わりますので、事前に確認しておきましょう。
| 地域 | 送る時期 |
|---|---|
| 東北・関東・九州 | 1月8日~2月3日頃 |
| 関西 | 1月16日~2月3日頃 |
この期間内に相手に届くように送りましょう。なお、立春を過ぎてしまった場合は余寒見舞いを送ります。くわしくは、「▼寒中見舞いの時期(立春)を過ぎてしまったら?」を確認してください。
寒中見舞いを送る主な4つのケース
寒中見舞いは、主に以下の4つのケースで利用されます。ここからは、それぞれの状況に合わせた文例を詳しくご紹介していきますので、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
- 季節の挨拶として
- 年賀状を交換する習慣がない相手や、とくに理由がなくても季節の便りを送りたい場合に用います。
- 年賀状の返信が遅れたとき
- いただいた年賀状への返信が、松の内(一般的に1月7日または15日)を過ぎてしまった場合に、年賀状の返信を兼ねて送ります。
- 喪中のとき
- 自分や相手が喪中で年賀状での挨拶を控えた(控える)場合に、年始の挨拶の代わりとして送ります。
- 年賀状を出さなかった相手から届いたとき
- 自分は出していない相手から年賀状が届き、返信が松の内を過ぎてしまった場合に使います。
失敗しない!寒中見舞いの基本構成と書き方のマナー
寒中見舞いは、年賀状の返信遅れや喪中など、相手への細やかな配慮が必要な場面で書かれることが多くあります。そのため、寒中見舞いは、失礼のない正しいマナーと状況に合わせた言葉選びが非常に重要です。
まずは、寒中見舞いの基本構成を押さえ、「▼【相手・状況別】そのまま使える寒中見舞いの文例集」を組み合わせることで、心のこもった挨拶状を作成しましょう。
はじめに、基本となる5つの要素を見ていきましょう。
- 時候の挨拶
「寒中お見舞い申し上げます」などの決まり文句です。 - 相手の安否を気遣う言葉
「厳しい寒さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか」など、相手の健康を気遣う言葉を続けます。 - 自身の近況報告
「おかげさまで、私どもは元気に暮らしております」など、自分の家族や自身の状況を簡潔に伝えます。 - 結びの挨拶
「寒さ厳しき折、くれぐれもご自愛ください」など、改めて相手の健康を気遣う言葉で結びます。 - 日付
「令和〇年 一月」のように、漢数字で日付を書き添えます。
これだけは押さえておきたい4つの注意点
寒中見舞いを書く際には、特に気をつけたいポイントが4つあります。うっかりマナー違反にならないよう、投函前に必ずチェックしましょう。
「賀詞(がし)」は使わない
寒中見舞いは年賀状ではないため、「謹賀新年」や「おめでとうございます」といった新年を祝う言葉(賀詞)は使いません。あくまで、寒い時期に相手の健康を気遣う挨拶状であることを意識しましょう。
「拝啓」「敬具」などの頭語・結語は不要
一般的な手紙で使う「拝啓」や「敬具」といった頭語・結語は、寒中見舞いには不要です。また、「寒中お見舞い申し上げます」という言葉自体が時候の挨拶にあたるため、「厳寒の候」といった漢語調の時候の挨拶も重ねて使う必要はありません。
「年賀はがき」は使わない
年賀状の返信として送る場合でも、年賀はがきを使うのはマナー違反です。郵便局で販売されている通常の郵便はがきや、私製はがきを使用してください。切手も、お祝い用のデザイン(慶事用切手)は避け、普通切手を選ぶのが無難です。
句読点は使わないのがより丁寧
古くからの慣習で、挨拶状には句読点(「、」や「。」)を使わないのが正式なマナーとされています。これは、相手への敬意を示すためや、「縁が切れないように」という意味合いが込められているといわれています。
ただし、現代では必ずしも厳密なルールではなく、読みやすさを優先して句読点を使っても問題ありません。親しい間柄であれば、気にしすぎる必要はないでしょう。

【相手・状況別】そのまま使える寒中見舞いの文例集
ここからは、様々な相手や状況に合わせて、そのまま使える寒中見舞いの文例を豊富にご紹介します。ご自身の状況に最も近いものを選び、必要に応じてアレンジしてご活用ください。各文例にはポイント解説も添えていますので、言葉選びの参考にしてください。
- ▼【基本形】季節の挨拶に使える定番の文例
- ▼【年賀状への返信】遅れてしまった場合のお礼の文例
- ▼【喪中】自分と相手の状況別に使える文例とマナー
- ▼【カジュアル】親しい友人向けの気軽な挨拶の文例
- ▼【ビジネス】上司・取引先に送る丁寧な挨拶の文例
【基本形】季節の挨拶に使える定番の文例
特定の理由がなく、純粋に季節の挨拶として送る場合の基本的な文例です。フォーマルな表現と少しくだけた表現を用意しましたので、相手との関係性に合わせて使い分けましょう。
【フォーマルな文例】
寒中お見舞い申し上げます
厳しい寒さの折 いかがお過ごしでしょうか
こちらはおかげさまで 家族一同元気に過ごしております
寒さはまだしばらく続くようですので どうかお体を大切にお過ごしください
令和〇年 一月
ポイント解説
上司や目上の方にも使える、最も丁寧で基本的な形です。近況報告は簡潔にまとめ、相手を気遣う言葉で締めくくるのがポイントです。
【少しカジュアルな文例】
寒中お見舞い申し上げます
毎日寒い日が続きますが お変わりなくお過ごしでしょうか
私たちは元気に過ごしています
また近いうちに お会いできるのを楽しみにしています
風邪などひかぬよう 暖かくしてお過ごしください
令和〇年 一月
ポイント解説
親しい友人や同僚などには、少し柔らかい表現を使うと気持ちが伝わりやすくなります。「また会いたい」という一言を添えることで、よりパーソナルな温かみが加わります。
【年賀状への返信】遅れてしまった場合のお礼の文例
いただいた年賀状への返信が松の内を過ぎてしまった場合に使う文例です。お礼とお詫びの気持ちを丁寧に伝えましょう。
【丁寧な文例】
寒中お見舞い申し上げます
この度は丁寧な年始のご挨拶をいただき ありがとうございました
ご挨拶が遅れまして 大変失礼いたしました
厳しい寒さが続いておりますが 皆様お変わりなくお過ごしでしょうか
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます
令和〇年 一月
ポイント解説
まずは年賀状をいただいたことへのお礼を述べ、次に返信が遅れたことへのお詫びを明確に伝えます。「本年もどうぞよろしく」という言葉を添えることで、年賀状の返信としての役割をきちんと果たせます。
【近況報告を添える文例】
寒中お見舞い申し上げます
華やかな年賀状をありがとうございました
年末年始は慌ただしく過ごしており ご挨拶が遅れてしまい申し訳ありません
我が家では 子どもたちも冬休みを満喫し 元気な声が響いています
寒さ厳しき折 くれぐれもご自愛ください
令和〇年 一月
ポイント解説
お礼とお詫びに加え、「慌ただしく過ごしていた」など、返信が遅れた理由を簡潔に添えると、相手に状況が伝わりやすくなります。簡単な近況報告を入れることで、より心のこもった印象になります。

【喪中】自分と相手の状況別に使える文例とマナー
寒中見舞いが最も活用されるのが、喪中のケースです。ご自身や相手が喪中の場合、どのように挨拶状を書けばよいか、状況別に文例とマナーを詳しく解説します。非常にデリケートな状況ですので、言葉選びには細心の注意を払いましょう。
自分が喪中のとき(年賀状への返信と欠礼報告)
喪中とは知らずに年賀状をくださった方へ返信する場合の文例です。年賀状をいただいたことへの感謝と、喪中であったため年始の挨拶を控えさせていただいた旨を丁寧に伝えます。
【一般的な文例】
寒中お見舞い申し上げます
この度はご丁寧な年始のご挨拶をいただき 誠にありがとうございました
昨年〇月に【故人続柄】の【故人氏名】が永眠いたしましたので
年末年始のご挨拶は失礼させていただきました
ご通知が遅れましたこと 心よりお詫び申し上げます
寒い日が続きますので どうぞご自愛ください
令和〇年 一月
ポイント解説
年始のご挨拶をいただいたお礼と、喪中につきご挨拶を失礼させていただいた旨を丁寧にお伝えすることが大切です。誰がいつ亡くなったのかを明確に記すことで、相手にも事情が伝わります。
【故人に触れずに簡潔に伝える文例】
寒中お見舞い申し上げます
年始状をいただきありがとうございました
服喪中のため 年頭のご挨拶を控えさせていただきました
旧年中にお知らせが行き届かず 大変失礼いたしました
本年も変わらぬお付き合いのほど よろしくお願い申し上げます
令和〇年 一月
ポイント解説
故人の詳細には触れず、喪中であったことだけを簡潔に伝えたい場合の文例です。相手との関係性に応じて使い分けましょう。
相手が喪中のとき(お悔やみの言葉を添えて)
喪中の方へ、年賀状の代わりとして送る挨拶状です。お祝いの言葉は一切使わず、相手の心を慰め、気遣う言葉を中心に構成します。
【基本の文例】
寒中お見舞い申し上げます
ご服喪中と伺い 年始のご挨拶は遠慮させていただきました
寂しさの募る日々をお過ごしのことと存じます
ご家族の皆様のお悲しみはいかばかりかとお察しいたします
寒さ厳しき折 どうかお体を大切にお過ごしください
令和〇年 一月
ポイント解説
「お悔やみ申し上げます」といった直接的な言葉は使わず、「寂しさの募る日々をお過ごしのことと存じます」のように、相手の気持ちに寄り添う柔らかい表現を選ぶのがマナーです。故人の死に直接触れるのではなく、ご遺族を気遣う気持ちを前面に出しましょう。
【少し親しい相手への文例】
寒中お見舞い申し上げます
寒い日が続いていますが 皆様いかがお過ごしですか
お手紙をと思いながらも ご無沙汰してしまい申し訳ありません
まだまだお力落としのことと思いますが 無理なさらないでくださいね
皆様の心が少しでも安らぎますよう お祈りしております
令和〇年 一月
ポイント解説
親しい間柄であれば、少しパーソナルな言葉で気遣う気持ちを伝えても良いでしょう。「無理なさらないでくださいね」といった言葉が、相手の心を温めることもあります。
喪中と知らずに年賀状を出してしまったときのお詫び
相手が喪中であることを後から知った場合に、お詫びとお悔やみの気持ちを伝えるための文例です。気づいた時点ですぐに送るのがマナーです。
【丁寧なお詫びの文例】
寒中お見舞い申し上げます
この度は 〇〇様ご逝去のこと 少しも存じ上げず
年始のご挨拶状を差し上げてしまい 大変失礼いたしました
お悔やみ申し上げますとともに 深くお詫び申し上げます
ご家族の皆様におかれましては さぞご心痛のことと存じます
心よりご冥福をお祈りいたします
令和〇年 一月
ポイント解説
まずは知らなかったとはいえ、年賀状を送ってしまった非礼を丁寧にお詫びすることが最も重要です。その上で、改めて故人へのお悔やみの言葉と、ご遺族を気遣う言葉を述べます。電話などで済ませず、改めて書状で気持ちを伝えるのが丁寧な対応です。

【カジュアル】親しい友人向けの気軽な挨拶の文例
気心の知れた友人には、定型文にこだわりすぎず、自分らしい言葉で気持ちを伝えるのが一番です。近況報告や、次に会う約束などを盛り込むと、より温かみのある挨拶状になります。
【近況報告を兼ねた文例】
〇〇へ
寒い日が続くけど 元気にしてる?
私は相変わらず忙しくしているけれど とても元気に過ごしています
落ち着いたら またランチでも行こうね
感染症も流行っているみたいだから 気をつけてね
令和〇年 一月
ポイント解説
「元気?」「寒いね!」といった、いつもの会話のような書き出しで始めると親しみが湧きます。時候の挨拶は「寒中お見舞い申し上げます」でも、よりカジュアルな言葉でも構いません。
【写真付きはがきなどに添える文例】
寒中お見舞い申し上げます
ご家族皆様 お変わりありませんか
我が家は先日 スキー旅行に行ってきました
寒さも忘れるくらい とても楽しかったです
またみんなで集まれる日を楽しみにしています
令和〇年 一月
ポイント解説
家族の写真やペットの写真などを使ったはがきに、短いメッセージを添えるのも素敵です。写真があることで、文章だけでは伝わらない近況が一目で分かります。
【ビジネス】上司・取引先に送る丁寧な挨拶の文例
ビジネスシーンで寒中見舞いを送る場合は、より丁寧でフォーマルな言葉遣いが求められます。日頃の感謝の気持ちや、今後の関係性につながる言葉を添えましょう。
【上司・恩師など個人宛の文例】
寒中お見舞い申し上げます
〇〇様におかれましては お変わりなくお過ごしのこととお慶び申し上げます
旧年中は公私にわたり大変お世話になり 心より感謝申し上げます
まだまだ未熟者ではございますが 本年もご指導ご鞭撻のほど よろしくお願い申し上げます
厳寒の折 どうかご無理なさらないでください
令和〇年 一月
ポイント解説
日頃の感謝や、今後の指導をお願いする言葉を入れることで、丁寧で謙虚な姿勢が伝わります。相手の健康を気遣う言葉で締めくくりましょう。
【取引先など会社宛の文例】
寒中お見舞い申し上げます
貴社におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます
平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます
寒さ厳しき折 皆様のますますのご健勝と貴社のご発展を心よりお祈り申し上げます
令和〇年 一月
ポイント解説
会社宛の場合は、個人的な近況報告は不要です。定型的な挨拶を中心に構成し、相手企業の繁栄を祈る言葉で締めくくるのが一般的です。
知っておくと便利!寒中見舞いにまつわるよくある質問
ここでは、寒中見舞いに関してよくある細かい疑問についてお答えします。「これってどうなんだろう?」という悩みをスッキリ解消しましょう。
はがきはどんなデザインを選べばいい?
寒中見舞いに使うはがきは、年賀はがきでなければ基本的に自由ですが、季節感のあるデザインを選ぶのが一般的です。
- 一般的なデザイン
- 雪の結晶、雪うさぎ、椿、水仙、梅など、冬や早春を感じさせる落ち着いたデザインが好まれます。美しい冬景色の写真なども良いでしょう。

- 喪中の相手に送る場合
- 色味やイラストが控えめな、落ち着いたデザインを選びましょう。胡蝶蘭や菊、蓮といったデザインは弔事用なので、寒中見舞いには使用しません。白地やごく薄い色の無地に、シンプルなイラストが描かれている程度のはがきが最適です。派手なデザインは避け、相手の心情に配慮することが最も大切です。

一言メッセージを添えたいときのおすすめフレーズは?
印刷された文面に手書きで一言添えるだけで、温かみがぐっと増します。相手との関係性に合わせて、気の利いたフレーズを加えてみましょう。
【誰にでも使える定番フレーズ】
- 寒い日が続きますので くれぐれもご自愛ください
- 皆様の無病息災を心よりお祈り申し上げます
- 春の訪れが待ち遠しいですね
【親しい相手向けのフレーズ】
- 温かい飲み物でほっと一息ついてくださいね
- 風邪などひかないよう気をつけてお過ごしください
- またお会いできる日を楽しみにしています
【ビジネスシーンで使えるフレーズ】
- 本年も変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます
- 皆様のますますのご健勝を心よりお祈りいたします
寒中見舞いの時期(立春)を過ぎてしまったら?
うっかり返信が遅れ、寒中見舞いを送る時期である立春を過ぎてしまった場合は、「余寒見舞い(よかんみまい)」として送ります。
余寒見舞いは、「暦の上では春になりましたが、まだ寒い日が続きますね」と、相手の健康を気遣う挨拶状です。書き出しの言葉を「寒中お見舞い申し上げます」から「余寒お見舞い申し上げます」に変えて送ります。基本的な構成やマナーは寒中見舞いと変わりません。
いつまでに出すかは厳密には決まっていませんが、一般的に2月末頃までが目安とされています。遅くとも3月上旬までには相手に届くようにしましょう。
まとめ
寒中見舞いは、一年で最も寒い時期に、大切な人の健康を気遣い、思いを伝えるための大切なコミュニケーションツールです。年賀状の返信が遅れてしまった時や、喪中の時など、少しデリケートな状況で使うことも多いからこそ、正しいマナーと心のこもった言葉選びが重要になります。
この記事でご紹介した基本構成や注意点、そして相手・状況別の文例を参考にし、あなたらしい言葉を添えれば、きっと相手の心に温かく響くはずです。ぜひ、心のこもった寒中見舞いを送って、大切な方とのご縁を繋いでいってくださいね。
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事


![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)
![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)