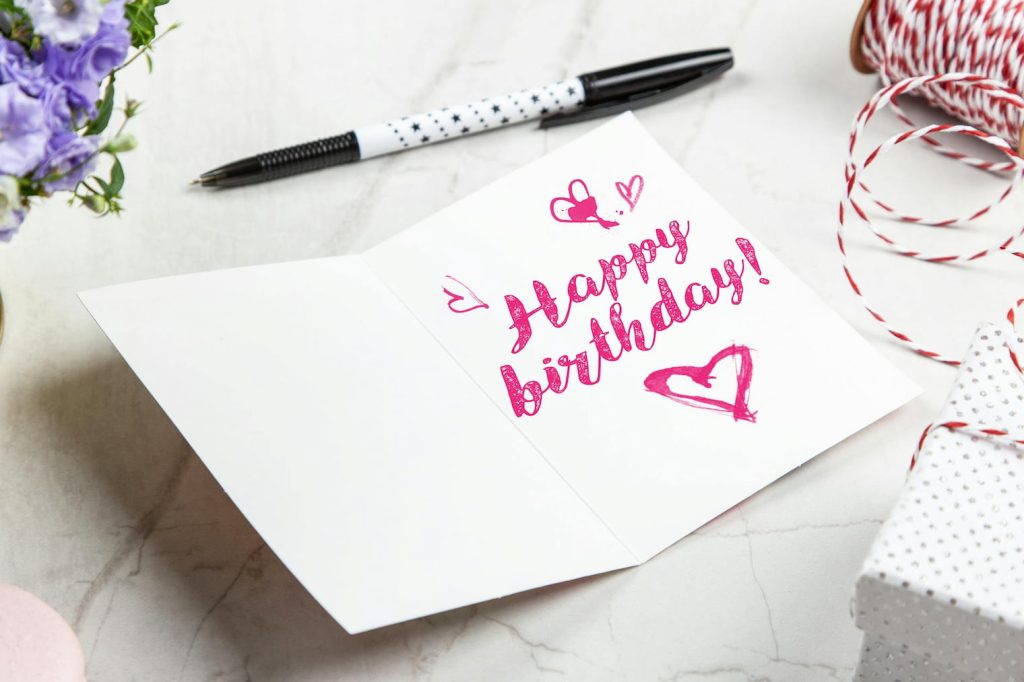【2025年版】立冬の食べ物は?時期やおすすめのレシピを紹介
そこで今回は、立冬の由来や立冬に旬を迎える食材、それらを使ったおすすめレシピをご紹介します。
目次
立冬とは?2025年の立冬はいつ?
立冬は冬の始まりの日です。
ここでは、立冬の由来と2024年の立冬の日にちについてご紹介します。
立冬は二十四節気のひとつ
立冬は、紀元前に中国で作られたとされる季節の区分方法、「二十四節気(にじゅうしせっき)」の一つです。二十四節気は、1年を約15日ごとに24等分したもので、太陰太陽暦(旧暦)の作成に利用されたり、季節の移り変わりを把握したりすることに役立てられていました。
立冬は冬の始まりを意味する節気で、この日から立春(毎年2月4日頃)までが暦の上では冬とされています。立冬は、二十四節気の1番目である「立春」から数えて19番目です。二十四節気の一つとして有名な「冬至」は22番目にあたり、例年12月後半に訪れます。
2025年の立冬は「11月7日」
2025年の立冬は、11月7日(金)です。二十四節気それぞれの日付は太陽の動きによって毎年変動し、立冬は例年11月7日か8日に訪れる傾向があります。
近年の立冬は以下のとおりです。
| 2024年 | 11月7日(木) |
|---|---|
| 2025年 | 11月7日(金) |
| 2026年 | 11月7日(土) |
| 2027年 | 11月8日(月) |
| 2028年 | 11月7日(火) |
立冬にまつわる伝統的な行事やお祭りなどはあまりありませんが、立冬の頃に七五三のお祝いをするご家庭は多いようです。
立冬に旬を迎える食べ物10選
立冬には、特別な行事食はありませんが、立冬の時期に旬を迎える食べ物は多くあります。
旬の食べ物は1年のうちで最も栄養価が高く、味もおいしくなります。立冬の日には、ぜひ旬の食べ物を食卓に取り入れてみてください。ここでは、立冬に旬を迎える食材をご紹介します。
かぼちゃ
かぼちゃの収穫は夏から初秋ですが、1~2か月風通しの良い日陰で保管し追熟(収穫後に徐々に甘くなる現象)することで、立冬の時期に最も甘みが強くなります。
かぼちゃは、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンEが豊富[1]で、抗酸化作用による免疫力アップ[2]や老化防止[3]が期待できます。
おいしいかぼちゃは、ヘタが枯れて乾燥し、皮がつややかで硬いことが特徴です。カットされたかぼちゃは、種が詰まっているものを選ぶと良いでしょう。

ほうれん草
ほうれん草は、低温で育つことで栄養が増加します。そのため、立冬の時期に収穫されるほうれん草は、ビタミンCやカリウムが豊富[4]なのが特徴です。ビタミンCには免疫力の強化[5]、カリウムはむくみ解消[6]などの効果が期待できるとされています。
また、ほうれん草には灰汁(あく)の成分であるシュウ酸が含まれています。シュウ酸は摂りすぎると体に悪影響を及ぼすと考えられているため、調理前にはあく抜きをするようにしましょう。
あく抜きの手順は以下のとおりです。
- 鍋に2Lの水を入れ、沸騰させる
- 塩を大さじ1/2入れ、ほうれん草の根元を30秒茹でる
- 30秒経ったら、ほうれん草の葉先まで入れ、1分半~2分半茹でる
濃い緑色で葉先がピンとしており、葉肉が厚いものが新鮮なほうれん草といわれています。

ごぼう
ごぼうは年間を通して手に入る食材ですが、旬は立冬の時期です。
ごぼうは食物繊維を豊富に含んでいる[7]ため、血糖値やコレステロール値を下げる[8]効果があります。また、食物繊維にはカルシウムの吸収を促進する働きもあるとされ、大豆製品や海藻類と一緒に食べるのもおすすめです。
おいしいごぼうは、表面に土がついていて、太さが均一でひげ根が少ないことが特徴です。

さつまいも
さつまいもは8~11月に収穫され、追熟を経て立冬の時期に食べごろを迎えます。
さつまいもの皮には、食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富に含まれています[9]。そのため、栄養を効率的に摂るには、皮ごと食べるのがおすすめです。
さつまいもを選ぶときは、レモンのように丸く、凹凸が少ないものを選ぶのがコツです。また、皮の色が濃い紫色で、つやのあるものは、甘みが強くおいしいさつまいもとされています。
りんご
立冬の時期に収穫されるりんごは「晩生種(おくてしゅ)」と呼ばれ、甘みと香りが強いのが特徴です。晩生種の代表的な品種には、「ふじ」「シナノゴールド」「王林」などがあります。
りんごには、カリウムが豊富[10]に含まれています。カリウムを摂ることで、高血圧の予防や疲労回復の効果が期待できます[6]。
甘みが強くおいしいりんごは、果皮が赤くハリとつやがあります。また、軸が太く、おしりの部分がオレンジ色や黄色のりんごは、蜜が詰まっているといわれています。

ゆず
立冬の時期に収穫されるゆずは、夏のゆずよりも熟していて果汁が豊富なのが特徴です。果皮にビタミンC、ビタミンE、食物繊維が多く含まれている[11]ので、果皮も料理に活用すると良いでしょう。
ハリがある鮮やかな黄色の果皮で、ヘタの切り口に青みが残っているものが新鮮でおいしいゆずです。

洋梨
洋梨は、収穫から2週間から1か月の追熟を経て、立冬の時期に完熟になります。洋梨はスイーツだけでなく、肉料理の付け合わせやサラダにしてもおいしく食べられます。
洋梨は、丸くずっしりとした重みがあり、果皮がツルツルでハリがあるものを選びましょう。薄い緑色から、きれいな黄色に変わったときが完熟のサインです。

生姜
生姜は1年に2回旬があるとされています。夏の新生姜は6~8月頃に旬を迎え、多くがハウス栽培です。一方、秋の新生姜は10~11月頃に旬を迎え、露地栽培のものが多いという特徴があります。
生姜は体を温める効果があることで知られています。寒い立冬の時期に旬を迎える秋の新生姜は、積極的に取り入れたい食材です。
生姜の辛み成分である「ジンゲロール」には、血行を促進し、体を温める効果が期待できます。また、免疫力を高める作用もあるとされ、風邪予防にも効果的です[12]。
大根
冬が近づくにつれて甘みが増し、柔らかくなるのが大根です。煮物や炒め物、サラダなど、あらゆる料理に使える万能野菜で、葉にもビタミンCやβカロテンが豊富に含まれています[13]。
おでんや煮物など、じっくり煮込むことで大根本来の甘みと旨みが引き出され、心も体も温まる一品になります。

銀杏
銀杏(いちょう)は、秋から冬にかけて実がなります。殻を割って炒ったり、蒸したりして食べるのが一般的です。
独特の風味とほろ苦さが特徴で、茶碗蒸しや炊き込みご飯の具材として使われることが多いです。栄養価も高く、ビタミンCや食物繊維、ミネラルが含まれています[14]。

立冬におすすめのレシピ
立冬には、栄養たっぷりの旬の食材を使ったおいしい料理を食べて、体調を整えましょう。
ここでは、立冬におすすめのレシピをご紹介します。
かぼちゃのそぼろあん

生姜で炒めた鶏ひき肉と、ひと口大に切ったかぼちゃを柔らかく煮て、水溶き片栗粉でとろみをつけた料理です。醤油とみりん、砂糖、塩で優しい味付けになっています。
ほくほくとした食感のかぼちゃにそぼろあんが絡み、冬にぴったりのレシピです。
材料(2人分)
- かぼちゃ:1/5個(200g)
- 鶏ひき肉:50g
- 生姜:1/2かけ
- サラダ油:大さじ1/2
- 【A】水:250cc
- 【A】塩:小さじ1/4
- 【A】砂糖:大さじ1/2
- 【A】みりん:大さじ1
- 醤油:大さじ1
- 水溶き片栗粉:適量
作り方
- かぼちゃはところどころ皮をむき、ひと口大に切る。生姜はすりおろす。
- 鍋に油と生姜を入れ火にかけ、鶏ひき肉を加え色が変わるまで炒める。
- 2に【A】とかぼちゃを加え、落とし蓋をしてかぼちゃが柔らかくなるまで煮る。
- 醤油を加えひと煮立ちさせ、水溶き片栗粉でとろみをつける。
ほうれん草入り麻婆豆腐

麻婆豆腐にほうれん草を加えた、栄養たっぷりの一品です。ほうれん草の鮮やかな緑が、料理に彩りを添えます。
豆腐は重しを乗せるなど、しっかりと水気を切ってから調理しましょう。
材料(2人分)
- 豚ひき肉:150g
- 木綿豆腐:150g
- ほうれん草:1/2束
- ごま油:大さじ1/2
- 水溶き片栗粉:適量
- 【A】にんにく:1かけ
- 【A】生姜:1かけ
- 【A】長ネギ:5cm
- 【A】花椒(粉末):小さじ1/2
- 【A】豆板醤:小さじ1
- 【B】酒:大さじ1
- 【B】醤油:大さじ1
- 【B】トウチジャン:小さじ1
- 【B】鶏がらスープの素:小さじ1/2
- 【B】砂糖:小さじ1
- 【B】水:100cc
作り方
- にんにく、生姜、長ネギはみじん切りにする。豆腐はペーパーでつつみザルに置き重しをのせて水切りしておく。ほうれん草は5cm幅に切りさっと茹で流水で冷やし水気を切っておく。
- フライパンにごま油を入れ火にかけ、豚ひき肉と【A】を加えて炒める。
- 豚肉に火が通ったら豆腐と【B】を加えて蓋をして煮詰める。水溶き片栗粉でとろみをつける。
根菜ラタトゥイユ

食物繊維たっぷりのごぼうやさつまいも、れんこんをオリーブオイルとにんにくで炒め、トマトピューレで柔らかく煮込んだラタトゥイユです。具材を炒める際、玉ねぎやまいたけ、ベーコンを加えることで、より味に深みが出ます。
冷蔵保存する場合は、汁気がなくなるまでしっかり煮詰めましょう。
材料(2人分)
- れんこん:80g
- さつま芋:80g
- ごぼう:80g
- 玉ねぎ:1/4個
- ベーコン:2枚
- まいたけ:1/2パック
- オリーブオイル:大さじ1
- にんにく:1かけ
- 【A】トマトピューレ:100cc
- 【A】水:30cc
- 【A】白ワイン:大さじ1
- 【A】タイム(乾燥):少々
- 【A】砂糖:小さじ1
- 【A】塩:小さじ1/4
- 【A】こしょう:少々
作り方
- れんこん、さつま芋、ごぼうは乱切りにする。玉ねぎは1.5cm程度のダイスカット、まいたけは食べやすい大きさに手でさく。ベーコンは1cm幅に切る。にんにくはみじん切りにする。
- 鍋にオリーブオイルとにんにくを入れ火にかけ、香りが出たらベーコンと玉ねぎを加え玉ねぎが透き通ったら他の野菜を加えて炒める。
- 全体がしんなりしたら、【A】を加えて20分程度煮込む。
さつま芋のチャウダー

さつまいも、人参、玉ねぎ、ハムを柔らかくなるまで煮込み、低脂肪乳で仕上げたチャウダーです。
具材の甘みと旨みが溶け込んだスープに、低脂肪乳のまろやかさを加え、心も体も温まる優しい味わいに仕上げています。具材は、食べる人や好みに合わせて同じ大きさにカットしておくのがおすすめです。
材料(2人分)
- さつま芋(小):1本(150g程度)
- 人参:1/2本
- 玉ねぎ:1/4個
- ハム:2枚
- オリーブオイル:大さじ1/2
- 低脂肪乳:100cc
- 【A】水:300cc
- 【A】コンソメの素:3g
- 【A】塩:小さじ1/2
- 【A】砂糖:小さじ1
- 【A】こしょう:少々
- 【A】(飾り)パセリ:適量
作り方
- 材料は1cm角に切り、さつま芋は水につけておく。パセリはみじん切りにする。
- 鍋にオリーブオイルと玉ねぎを入れて弱火で炒め、玉ねぎが透き通ったらさつま芋、人参、ハムも加えさらに炒める。
- 2に【A】を加え、さつま芋が柔らかくなるまで煮て低脂肪乳を加え、沸騰直前まで温めてから火を止める。器に盛り、パセリを飾る。
焼リンゴのアイスクリーム添え

皮付きのままカットしたりんごを、バターとグラニュー糖でこんがりと焼いて、バニラアイスクリームを添えたデザートです。りんごの皮には、抗酸化成分のアントシアニンが含まれているので、健康にうれしいレシピです。
砂糖は焦げやすいため、グラニュー糖を入れたら焦がさないように注意しながら焼きましょう。
材料(2人分)
- りんご:1個(250g)
- バニラアイスクリーム:100g
- バター:大さじ1/2
- グラニュー糖:大さじ2
作り方
- りんごは皮付きのまま12等分にして芯を取る。
- フライパンにバターを入れ火にかけ、バターが溶けたら1のりんごを並べる。両面少し透き通るまで焼く。
- 2にグラニュー糖をふり、砂糖を煮詰めるように焼く。両面カラメル色になったら器に盛り、バニラアイスクリームを添える。
白菜とりんごのヨーグルトサラダ

サッとゆでた白菜とりんごを、粒マスタードとヨーグルトをベースに作ったドレッシングで和えたサラダです。りんごは、カットした後に塩水につけておくと変色を防げます。
白菜とりんごは疲労回復や風邪予防の効果が期待できるビタミンCが豊富で、寒くなり体調を崩しやすい立冬の時期にはぴったりの栄養素です。
材料(2人分)
- りんご:1/3個
- 白菜:200g
- 紫玉ねぎ:1/6個
- 塩:少々
- 【A】粒マスタード:大さじ1/2
- 【A】無糖ヨーグルト:大さじ1
- 【A】はちみつ:小さじ1
- 【A】オリーブオイル:小さじ1
- 【A】塩:少々
作り方
- りんごは皮のままいちょう切りにし、10分程度塩水にさらし水気を切る。白菜と紫玉ねぎは太めの千切りにして、さっと茹で流水で冷却し水気を切っておく。
- 【A】をボウルに入れてよく混ぜる。
- 2にりんご、白菜、紫玉ねぎを加えて混ぜる。
鶏肉とかぶの煮物 ゆず風味

栄養豊富なかぶの根と葉を使用した、ホッとする優しい味わいが特徴の煮物です。ひと口大に切って焼き色をつけた鶏もも肉とかぶを、ゆず果汁を加えた煮汁で柔らかくなるまで煮込みましょう。
お皿に盛り付けた後にさらにゆずの皮を飾れば、彩りも豊かになり、爽やかな香りも楽しめます。
材料(2人分)
- かぶ:3個
- かぶの葉:適量
- ゆず:1/2個
- 醤油:大さじ1
- サラダ油:小さじ1
- 【A】水:2カップ
- 【A】みりん:大さじ1
- 【A】砂糖:小さじ1
- 【A】塩:小さじ1/4
作り方
- りんごは皮のままいちょう切りにし、10分程度塩水にさらし水気を切る。白菜と紫玉ねぎは太めの千切りにして、さっと茹で流水で冷却し水気を切っておく。
- 【A】をボウルに入れてよく混ぜる。
- 2にりんご、白菜、紫玉ねぎを加えて混ぜる。
まとめ
立冬は秋が終わり、冬の始まりを知らせる時期です。立冬の時期には、かぼちゃ、ほうれん草、ごぼう、りんご、ゆずなど多くの野菜や果物が、栄養豊富でおいしくなる旬を迎えます。
今年の立冬は、本記事で紹介したレシピを参考に、旬の食材を活かした料理を食べて、心も体も満たされるひとときを過ごしてみませんか。
- 文部科学省 :
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年「第2章(データ)」 「6野菜類」D67 - 厚生労働省:
健康日本21アクション支援システム「抗酸化ビタミン」 - 公益財団法人長寿科学振興財団:
健康長寿ネット「抗酸化による老化防止の効果」 - 文部科学省 :
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年「第2章(データ)」「6野菜類」D348 - 厚生労働省:
eJIM「ビタミンC」 - 東京電力エナジーパートナー:
くらひろ by TEPCO「【管理栄養士監修】ドラゴンフルーツ(ピタヤ)の栄養素は?種類・食べ方も」 - 文部科学省 :
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年「第2章(データ)「6野菜類」D107 - 厚生労働省:
健康日本21アクション支援システム「食物繊維の必要性と健康」 - 文部科学省 :
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年「第2章(データ)」「2いも及びでんぷん類」D25 - 文部科学省 :
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年「第2章(データ)」「7果実類」D189, D190 - 文部科学省 :
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年「第2章(データ)」「7果実類」D98, D99 - くらひろ by TEPCO:
管理栄養士監修:生姜の成分や効能は?健康効果やレシピも解説 - 文部科学省:
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年「第2章(データ) 6野菜類 D160」 - 文部科学省:
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年「第2章(データ) 5種実類 D22」
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事


![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)
![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)