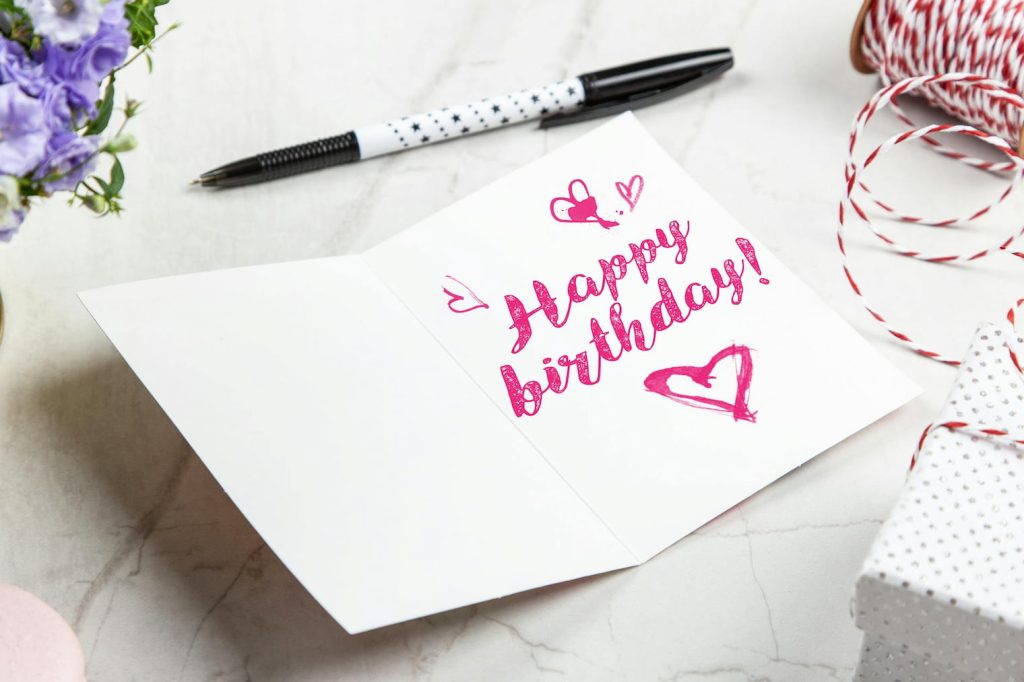梅仕事とは?初心者でもできる基本のやり方とおすすめ梅レシピを紹介
毎年6月ごろ、梅雨入りの時期に始めるのが一般的で、日本の風土とともに受け継がれてきた丁寧な暮らしのひとつです。「興味はあるけれど、手間がかかりそうで…」と迷っている方も多いかもしれません。
この記事では、初心者の方でもわかりやすいように、梅仕事の意味や由来、始め方から簡単なレシピまでをやさしくご紹介します。季節の移ろいを感じながら、梅仕事を楽しんでみませんか?
梅仕事とは?意味・由来・楽しみ方を解説
「梅仕事(うめしごと)」という言葉を耳にしたことはあっても、その意味や由来までは知らない方も多いかもしれません。実はこの季節の手しごとは、ただの保存食づくりにとどまらず、日々を丁寧に過ごすための豊かな時間でもあります。
ここでは、梅仕事の基本や楽しみ方、そして意外と知られていない“梅の日”についてもご紹介します。
梅仕事とは何?いつやるの?
「梅仕事(うめしごと)」とは、旬の梅を使って保存食を作る、梅雨の季節の手しごとのことです。旬を迎えた青梅を使い、梅干しや梅酒、梅シロップなどを仕込みます。ちょうど梅雨の時期と重なるため、家の中で静かに楽しめる暮らしの営みとして、昔から多くの家庭で親しまれてきました。
梅が店頭に並びはじめるのは初夏から梅雨にかけての5月下旬~6月中旬ごろ。この短い時期が、梅仕事のベストシーズンです。
「仕事」というと少し難しそうに感じるかもしれませんが、少ない材料とシンプルな工程でできるものも多く、料理初心者の方でも気軽に始められます。

梅仕事の魅力は“季節を楽しむ癒しのひととき”
梅仕事の魅力は、ただ保存食を作るというだけではありません。旬の素材に触れ、香りや手触りを感じながら、少しずつ時間をかけて育てるプロセスそのものが、心を豊かにしてくれます。
たとえば、梅を一つひとつ丁寧に洗い、へたを取っていく作業。瓶に氷砂糖と梅を交互に重ねる瞬間。梅の色が変わり、香りが熟していく様子を見守る時間。それらすべてが、忙しい日々の中で自分と向き合う“癒しのひととき”になるのです。
仕込んだものが美味しく仕上がったときの喜びも格別です。手間をかけたぶんだけ、家族にふるまったり、友人への贈り物にしたりと、日常の中で“手しごとの温かさ”を実感できます。
6月6日は「梅の日」
6月6日は「梅の日」です。この日は、天文14年(西暦1545年)、後奈良天皇が京都の賀茂神社に梅を奉納し、五穀豊穣を祈願したことが由来とされ、2006年に「紀州梅の会」によって制定されました[1]。
ちなみに、そのときの梅を奉納した祈願のあと、長く降らなかった雨が降り始めたことから、人々はその雨を「梅雨」と呼ぶようになったとも伝えられています。
梅の恵みに感謝する意味を込めて、現在でもこの日に青梅や梅干しを神社に奉納する行事が各地で行われています。こうした歴史や文化を知ることで、梅仕事が単なる保存食づくりではなく、自然や季節と寄り添う大切な行事であることが感じられるはずです。

梅仕事の準備と手順
はじめての梅仕事は、少しハードルが高そうに感じるかもしれませんが、基本の道具と手順をしっかり押さえておけば、どなたでも安心して始められます。
ここからは、梅の選び方から保存容器の消毒、下ごしらえのコツまで、はじめて梅仕事に取り組む方でも分かりやすいように詳しくご案内します。
まずは梅を知ろう!種類と選び方のポイント
梅仕事を始める第一歩は、梅の種類や特徴を知ることからです。梅には観賞用の「花梅(はなうめ)」と、食用の「実梅(みうめ)」がありますが、梅干しや梅酒に使うのはもちろん「実梅」です。
中でも人気の品種は「南高梅(なんこううめ)」。果肉がやわらかくてジューシーなため、梅干しや梅酒にぴったりです。東日本で栽培量の多い「白加賀(しらかが)」や、小ぶりで歯ごたえのある「甲州最小(こうしゅうさいしょう)」など、用途に合わせて選ぶのがポイントです。
選ぶときは、青くてハリがあり、傷のない実を選びましょう。梅の香りもチェックして、フレッシュなものを選ぶと失敗が少なくなります。

梅仕事に必要な道具と保存容器の消毒方法
梅仕事には、清潔な道具の準備が欠かせません。使用する主な道具は、以下のとおりです。
- 梅を洗うためのボウル
- へた取り用の竹串
- 保存用のガラス瓶やホーロー容器
- 梅を干すためのざる(梅干しを作る場合)
なお、梅を干す際には、アルミ製のバットではなく、ざるなどを使用しましょう。梅干しは酸性が強いため、アルミ製のバットは黒ずんだり溶けてしまったりすることがあります。
また、保存容器は必ず煮沸消毒を行いましょう。大きめの鍋でしっかりと熱湯にかけることで、雑菌の繁殖を防ぎます。割れを防ぐために、加熱前から容器を鍋に入れておくのがコツです。
消毒後は清潔な布や金網の上で自然乾燥させ、容器の内側には触れないように注意してください。

下ごしらえの基本手順(洗浄・水気の拭き取り・へた取り)
梅を使う前には、丁寧な下ごしらえが必要です。
- 1. 洗浄
- たっぷりの水で梅をやさしく洗い、汚れを落とします。
- 2. 水気の拭き取り
- 清潔なふきんで水分をしっかり拭き取りましょう。
- 3. へた取り
- 竹串を使って、梅の「なり口(へた)」をやさしく取り除きます。実を傷つけないよう、そっと行うのがポイントです。
作るレシピによっては、梅を一度冷凍して使うこともあります。冷凍することで繊維が壊れ、エキスが出やすくなるため、梅シロップなどにおすすめの方法です。目的に合った下処理を選んでみてください。
初心者にもおすすめ!梅仕事の簡単レシピ集
はじめての梅仕事でも手軽にチャレンジできる、定番の梅レシピを集めました。梅干しや梅酒、梅シロップなど、どれも少ない材料でできるものばかりです。
保存食としてだけでなく、日々の食卓を彩る一品としてもおすすめです。
- ▼梅干し:一番人気!梅仕事の代表格
- ▼梅酒:梅仕事の定番!保存期間と飲み頃は?
- ▼梅シロップ:ノンアルコールで家族で楽しめる
- ▼梅ジャム:梅仕事で漬けた梅の実で作れる
- ▼梅の砂糖漬け:炭酸で割って梅ジュースに
梅干し:一番人気!梅仕事の代表格
初心者でも挑戦しやすい梅仕事が、梅干し作りです。用意するものは、青梅・塩・保存袋・重石だけです。
基本の作り方
- 梅を洗い、しっかりと水気を拭き取ったあと、竹串などでなり口(へた)を取る。
- 保存袋に梅と梅の重さに対して20%の塩を加えて、よく馴染ませる。
- 袋を密閉し、重石をのせて冷暗所で1か月間保存する。
- 梅酢が出てきたら梅を取り出し、晴天が続く日に3日間干して完成。
一粒ひとつぶ、自分で手をかけた梅干しは格別の味わいです。

梅酒:梅仕事の定番!保存期間と飲み頃は?
梅酒も梅仕事の定番です。梅酒は、梅と氷砂糖、ホワイトリカー(焼酎甲類)があれば作れます。
基本の作り方
- 梅をよく洗い、水に2時間ほどさらしてアク抜きをする。
- 水気を拭き取り、なり口(へた)を取った梅と氷砂糖を交互に広口瓶に詰める。
- 最後にホワイトリカーを注ぎ、密閉して冷暗所へ。
分量の目安は、梅1kgに対して氷砂糖700g、ホワイトリカー1.8Lです。3か月ほどで飲み頃になりますが、1年以上寝かせると味に深みが出て、さらにおいしくなります。

梅シロップ:ノンアルコールで家族で楽しめる
梅シロップはノンアルコールで飲みやすく、家族みんなで楽しめる一品です。炭酸水やお水で割れば、夏のドリンクにもぴったりです。
基本の作り方
- 梅を洗って水気を拭き取った後、なり口(へた)を取り、冷凍庫で一晩凍らせる。
- 凍らせた梅と氷砂糖を交互に消毒済みの瓶に入れる(梅1kgに対して氷砂糖800g)。
- 常温で保存し、1週間ほどでシロップが完成。
完成後は冷蔵庫で保存し、1か月以内を目安に飲み切りましょう。

梅ジャム:梅仕事で漬けた梅の実で作れる
梅ジャムは、梅酒や梅シロップを作る際に漬けていた梅で作ることができます。無駄なく梅を使いきる工夫も、丁寧な暮らしの楽しみのひとつです。
基本の作り方
- 漬けていた梅の実を鍋に入れ、かぶるくらいの水を加える。
- 中火で沸騰させ、その後弱火にして5分加熱する。
- 梅の実を一度ざるにあげてお湯を捨て、梅の実を鍋に戻す。
- 再び梅の実がかぶるくらいの水を加え、梅の実が柔らかくなるまで煮込む。
- 柔らかくなったらざるにあげ、種を取り除いて、再び鍋に戻す。
- 砂糖(梅1kgに対し砂糖200~500g)を加えて煮込み、練り上げて完成。

梅の砂糖漬け:炭酸で割って梅ジュースに
梅の砂糖漬けも梅仕事におすすめです。シロップを水や炭酸水で割り、割った梅を加えれば、夏にぴったりな梅ジュースが楽しめます。
基本の作り方
- 梅をよく洗い、水気を拭き取ってなり口(へた)を竹串などで取り除く。
- 保存袋に入れて冷凍庫で凍らせる。
- 清潔な千枚通しなどを用意し、凍った梅のヘタの部分から種を避けるように斜めに1か所穴を空ける。
- 消毒した広口瓶に梅と砂糖を交互に詰める(梅1kgに対し砂糖700g程度)。
- 冷暗所に保存し、ときどきかき混ぜる。砂糖が完全に溶けたら以降は冷蔵庫で保存する。

梅干しの活用法もいろいろ!おすすめアレンジレシピ
手作りの梅干しは、そのまま食べるだけでなく、料理にアレンジすることでさらに楽しみが広がります。シンプルながら奥深い味わいを活かせば、いつもの食卓がワンランクアップ。
ここでは、初心者でも挑戦しやすい梅干しアレンジレシピをご紹介します。
豚しゃぶ梅干しうどん:暑い夏に食欲をそそる一品

「豚しゃぶ梅干しうどん」は暑い季節にぴったり。さっぱりとした梅の風味が食欲をそそります。梅干しに含まれるクエン酸には疲労回復効果が期待できます。
梅びしお:万能な練り梅調味料

梅干しを塩抜きしてペースト状にし、砂糖を加えて煮詰めた「梅びしお」は、常備しておくと便利な万能調味料です。甘みと酸味が絶妙で、鶏の唐揚げやドレッシング、和え物のアクセントとしても活躍します。
基本の作り方
- 梅干し500gを6~8時間塩抜きし、種を除いて裏ごしする。
- 土鍋で砂糖100g(2回に分けて)とともに弱火で練るように加熱する(約20分)。
- 最後にみりん大さじ1を加え、照りを出したら完成。
冷蔵保存で半年~1年ほど日持ちします。
梅ごはん:炊飯器で簡単さっぱりごはん
炊飯器にちぎった梅干しを入れるだけで、爽やかな風味が広がる「梅ごはん」が完成します。青じそのトッピングで香りが豊かに広がります。
基本の作り方(3合分)
- 白米3カップに古代米大さじ1を加え、通常通りの水加減で炊飯器へ。
- 梅干しを2~3個、種も一緒にちぎって加え、炊飯器にセット。
- 炊き上がったら梅の種を取り除き、全体を混ぜて器に盛り、千切りの青じそを散らす。
梅漬け:梅干しでつくる簡単浅漬け
梅干しを使った浅漬けは、ほんのひと手間で毎日の食事に彩りを添える一品になります。夜に仕込めば翌朝には食べられる、時短レシピです。
基本の作り方
- キュウリ1本(乱切り)、カブ2個(食べやすく切る)に塩をふって2~3時間おく。
- 野菜を軽く洗い水気を切ったら、容器に入れて梅干し3個(ちぎって種ごと)、醤油大さじ2、削り節3gを加え、混ぜて重石を載せる。
- 一晩寝かせて完成。
初めての梅仕事Q&A
初めて梅仕事に挑戦する方にとっては、「どれくらい時間がかかるの?」「何から始めればいいの?」といった疑問や不安もあるかもしれません。
ここでは、よくある質問をQ&A形式でまとめ、初心者の方が安心して梅仕事をスタートできるよう、やさしく丁寧にお答えします。
梅仕事ってどれくらい時間がかかるの?
レシピによって異なりますが、梅干しの場合は仕込みから完成まで1か月半~2か月ほどかかることが多いです。梅酒や梅シロップは、仕込み自体は30分ほどで完了し、保存期間中にゆっくりと味が変化します。
じっくりと育てる時間も梅仕事の醍醐味です。
どの梅料理から始めるのが簡単?
もっとも手軽なのは「梅シロップ」です。火を使わず、材料もシンプルで失敗が少ないため、初心者の方にもおすすめです。次に挑戦したいのが「梅酒」です。アルコールを扱う点だけ注意すれば、長く楽しめる保存食になります。
失敗しないための注意点は?
梅仕事で大切なのは「清潔さ」と「正しい保存環境」です。とくに、保存容器や使用する道具は、煮沸消毒やアルコール消毒をしっかりと行いましょう。
また、直射日光を避けた涼しい場所で保存することもポイントです。梅は傷みやすいため、食べている途中で異臭がしたり、カビが発生したりした場合は廃棄してください。

まとめ
梅仕事は、梅雨の季節にしかできない特別な手しごとです。梅干しや梅酒、シロップなど、保存食を自分の手で仕込むことで、季節の恵みを暮らしに取り入れることができます。
初心者の方でも、正しい手順と道具をそろえれば、意外と簡単に始められるのも魅力のひとつ。手間をかけるぶん、完成したときの喜びもひとしおです。
この記事を通して、梅仕事の魅力や楽しみ方に触れ、毎年の恒例行事として取り入れてみてはいかがでしょうか。丁寧な暮らしの第一歩として、ぜひ挑戦してみてください。
- 紀州梅の会:
「梅の日」には、みんなで梅を食べましょう
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事


![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)
![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)