
時短で叶う、理想の空間 二人で続けられるラク家事テクニック

片づけは家の中に幸せを招く
家の中が片付いているという状態は、単にスッキリしていて空間が広く使えるというだけではありません。例えば、実家からたくさんのお米や日用品が送られてきたとします。その時、家の中に置いておくためのスペースがあれば素直に受け取ることができますが、スペースが無いと嬉しい贈り物にもかかわらず「どこにしまっておこう…」と少し考えてしまう事もありますよね。
この例に限らず、家の中を整えておくことは、受け入れる準備ができているということ。その準備ができていれば、チャンスが舞い込んだときすぐにとりかかることができます。片づいた家の中の空間は心もキレイになる、幸せを呼び込むためのスペースなのです。
「片づけ脳」を作るための7つの考え方
片づけを始める前に、片づけの基本となる7つの考え方をチェックしていきましょう。
自分たちのライフスタイルに合わせて「これは取り入れられそう」と思うものから少しずつ取り組んでみるとよいですよ。

ものを減らして家事をラクに
ものを多く持つということは、その数だけメンテナンスや手間がかかるということです。
例えば、キッチンのシンク下など、「とりあえず入るからいれておけばいいや」とぎゅうぎゅうに詰め込まれていませんか。夕食に鍋パーティーがしたいのに土鍋が見つからない…。といった探しもののストレスから解放されるためには、「ものを減らす」という選択が欠かせません。
とはいえ、一度にものを手放すのは「もったいない」「いつか困るかもしれない」となかなか踏ん切りがつかないものです。
まずは、自分が家事をしている中で「何が一番ストレスに感じているか」を考えて、その場所から手を付け、徐々に範囲を広げていくとよいでしょう。
整理整頓はダイエットと同じ
ダイエットには、体重が減る→体のラインが変わってくる→まわりに気づいてもらえる→さらにダイエットをがんばる→習慣になる、という一連のサイクルがあります。
整理整頓もよく似ていて、ものを減らして家事のストレスが減ると、気持ちの良い達成感を味わうことができ、さらに片づけをがんばれる、というサイクルができあがります。二人で取り組み、お互いを褒めあえば、さらに片づける原動力になりますよね。
整理整頓もダイエットも、成果は目に見えます。こつこつと積み重ねていき、習慣化してしまえば大成功です。
いる・いらない・保留に分類する
「今日はここを整理する」と決めたら、そこにあるものをすべて出し、次の3つのグループに分類する習慣をつけましょう。パートナーと共有しているものは話し合いながら分類を進めてくださいね。
1.いるもの・まあまあいるもの
2.いるかどうか悩むもの
3.いらないもの
すべて分類できたら、まず収納していた場所をキレイに掃除し、分類した1のグループを戻していきます。その際、取り出しやすさを考えながら場所を決めるとよいでしょう。
次に、3のグループは潔く手放しましょう。ゴミに出すのはもったいない…という時は、リサイクルショップやフリマアプリなどを活用するのもよいですが、捨てるつもりだったと考え、値段にはこだわらないよう心がけてください。
最後に、2のグループは「保留ボックス」を用意して入れましょう。ある程度の期間を設け、そのときがきたら必要かどうかをあらためて考えて決めます。
小さな場所から少しずつ片づける
家事の中で一番ストレスを感じている場所が「キッチン」だとしたら、その中でも一番小さな引き出しから手を付けてみてください。
最初から大きなスペースから始めてしまうとなかなか終わらず、途中で嫌になってしまうこともありますが、小さなスペースなら思いのほか簡単にすっきり片づき、達成感を味わうことができます。
「〇〇用」にこだわるのをやめる
ものを増やさないためのテクは、「専用品はやめて、使いまわしのきくものを選ぶ」ことです。
例えば、「食器用洗剤」「窓ガラス用洗剤」などの専用品はピンポイントに使えてとても便利なのですが、用途に合わせて買っていると収納場所を圧迫してしまいますよね。用途を兼用できるものはなるべくひとつにまとめてしまいましょう。
無駄な買い物を避けるコツ
ものを減らして整理整頓の習慣がついたとしても、家の中にものは入ってきます。
そのほとんどが自分たちの買い物でしょうから、「本当にこれが必要なのかな?」と買う前によく考えて、納得のいくものだけを買いましょう。
「安いから買っておこう」ではなく、「本当に必要か」「収納する場所は確保できるか」を考えることも重要と心得ましょう。
人を呼ぶことでキレイを保つ
整理整頓と掃除の最終到達点は、やはり「お客様が来ても恥ずかしくない」状態です。
そのために、友人や親族を積極的に家に招いてお茶をしたりランチを食べたりすることを習慣にしてみましょう。気の置けない友人たちでも、家に来てもらうとなれば玄関やトイレ、リビングをキレイにしておきたいですよね。第三者目線で部屋を見ることになりますので、普段気づかないポイントが掃除できるチャンスですよ。
掃除の基礎を知ろう
片づけの基本を学んだ後は、片づけのなかでも「掃除」の基礎を学んでいきましょう。掃除は苦手という方も、どんな汚れがどんな方法で落とせるのか知っておくとラクになりますよ。

知っておきたい汚れの種類
家の中の汚れは、大きく分けて3種類あります。どこにどんな汚れが多いのか、どんな特徴があるのかを知っておけば、洗剤や掃除法を使い分けて無駄なく掃除ができるのです。
1.油汚れ
キッチン周りが代表とされる「酸性の汚れ」です。
放置していた油はねなどが温度などの影響で酸化してしまうことが原因ですが、それにホコリやチリが加わって固まると、手ごわい汚れになってしまいます。目に見える油はねだけでなく、空気中にオイルミストとなって拡散してしまうので、食器棚や壁、冷蔵庫など広範囲に付着してしまいます。
また、手や足の皮脂も油ですので、ドアノブやフローリングの床など、触れるところはすべて汚れがたまってしまっていると考えましょう。
2.水アカ汚れ
水回りが代表とされる「アルカリ性の汚れ」です。
水道水の飛び散りを放置する事で水分が蒸発し、カルシウムなどのミネラル分が白く残ることが原因で、毎日同じような場所に水滴が飛び散るため、どんどん汚れが重なり、しつこい汚れになってしまうのです。また、石けんカスなどの成分と結合する性質があるため、放置すればするほどガッチリとし固まってしまいます。
場所だけでなく、やかんやポット、加湿器などの「もの」にも水アカは付着しますので見落とさないようにしましょう。
3.カビ汚れ
水回りが代表とされる「カビやバクテリアの汚れ」です。
カビ汚れの場合は「湿度」「温度」「栄養」の3条件が揃った場所で増殖してしまう汚れで、湿気がたまりやすい浴室、押し入れなどの他に、エアコンの内部や結露によって壁や天井にも発生することがあります。カビ、バクテリアは、表面だけでなく内部にまで広がる汚れです。アレルギーや病気の原因にもなるので、カビやバクテリアの性質に適した対処法が必要となるのです。
5つの掃除アイテム
前項で見てきた3種類の汚れは、5つの掃除アイテムでキレイにできます。窓やキッチンといった「場所」ごとに洗剤を変えなくても良いので、収納場所も小さくて済みますし、幅広く使えて効果抜群ですよ。
1.クエン酸
水アカ汚れなどの「アルカリ性の汚れ」に効果があります。
カリカリの落ちにくい水アカをしっかり落としてくれる酸性の粉末ですが、アルミや大理石の製品には使えないので注意しましょう。
また、塩素系漂白剤と混合すると有毒ガスが出るので、必ず各洗剤の使用上の注意を確認してから使ってくださいね。
2.重曹
油汚れなどの「酸性の汚れ」に効果があります。
軽い油汚れや焦げ落としに最適な、弱アルカリ性の粉末です。あまり時間の経っていない油汚れには重曹を使うとよいでしょう。
畳や白木などの天然素材、アルミ製品には使えませんので注意してくださいね。
また、重曹は「食用」と「掃除用」の2種類が売っていますので、間違って掃除用の重曹を料理に使わないよう気を付けましょう。
3.セスキ炭酸ソーダ
こちらも重曹と同じく、油汚れなどの「酸性の汚れ」に効果があります。
重曹よりもアルカリ度が高く、しつこい油汚れを落とすのに向いており、粉末だけでなく液体タイプも売られています。
こちらも重曹と同じく畳や白木などの天然素材、アルミ製品には使えず、さらに二度拭きが必要になります。セスキ炭酸ソーダが残ったままにならないようしっかりと拭きあげてくださいね。
4.アルコール
軽い油汚れなどの「酸性の汚れ」に効果があります。
油はねなどには効果が弱いですが、手アカなどの軽い油汚れ落としや殺菌に向いています。
少量なら口にしても害がないのでテーブルや食器にも安心して使え、速く乾くというメリットがありますが、引火性があり塗料などを溶かしてしまう場合がありますので、使う場所には注意しましょう。
5.酸素系漂白剤
カビ汚れなどの「カビやバクテリアの汚れ」に効果があります。
塩素系の漂白剤と比べると効果がマイルドで使いやすいのがポイントで、浴室のカビやバクテリアの除去、漂白、除菌などに向いています。
素材によっては洗濯にも使えますので、布巾の除菌漂白にもオススメですよ。
二人でやれば時短でラクちん!場所別家事テクの紹介
一人で家事をするのはとても大変ですが、二人でやればコミュニケーションのひとつになりますし、時間も短縮できて一石二鳥ですよね。
場所別の家事テクを知ることで、時短でラクに家事ができるようになりますよ。

キッチンは使いやすさと清潔さがカギ
キッチンで面倒な家事といえば、食器洗いという方は多いのではないでしょうか。
スムーズに食器洗いを始めるためにも、食器洗い用具をひとまとめにしておきましょう。スポンジが見当たらない、ゴムベラをどこにしまったか忘れた、というプチストレスから解放されますよ。
そして、スポンジでこする前に汚れをゴムベラで落としておくのもおすすめです。こうすることにより少しの洗剤で汚れがラクに落とせます。
最後の洗い流す方法ですが、著者のおすすめは洗いおけを使わない「シャンパンタワー方式」です。やり方はとっても簡単で、下から大きい順に重ねた食器に、シャンパンタワーの要領で上から水を流していけばOKです。
二人で分担する場合は、一人はゴムベラで汚れを落とす担当、もう一人は洗い流す担当と分担してみるのはいかがでしょうか。手分けして作業すれば、面倒な食器洗いも短時間で終わらせることができます。
トイレや浴室は汚れを防ぐ心がけを
トイレは服の上げ下ろしも多く、ほこりがたまりがちです。尿や皮脂汚れなど、様々な汚れがたまってしまうと掃除も嫌になってしまいますよね。
便器回りは毎日さっと拭き掃除をすることを習慣にすれば、キレイなトイレを維持することができますよ。どちらかがやっていない、ということがないようにパートナーにもきちんと共有しましょう。
また、浴室には極力ものを置かないようにしましょう。浴室用の収納ラックもぬめりやカビの原因になってしまうため、無いほうが掃除はラクになりますよ。浴室内にはシャンプーや石けんなど最低限のものだけ置いて、あとは脱衣所などの棚に収納しましょう。シャンプーやコンディショナーなどはパートナーと同じものを使えるのであれば、さらにスッキリしますね。
ホコリの舞いやすいリビングは効率重視
リビングの汚れは、空気中のホコリが床に落ちたもの、皮脂、食べこぼしたものが中心なので、ホコリが空気中に舞い散らない朝のうちに掃除機をかけるのが効率的です。
とはいっても、忙しい朝の時間に掃除機なんてかけていられない!という方も多いですよね。そんなときには、一人が洗濯物を干している間にもう一人が掃除機をかけるなどすれば、2倍の速さで家事が進みます。
クローゼットは使う人に合わせた収納を考える
クローゼットは、基本的にはつるす収納にするのがよいでしょう。
洗濯物をたたむ手間が省けるほか、全体が見やすいのでコーディネートしやすくなりますよ。つるす収納は、使いやすい高さや位置を見つけることがポイントなので、身長はもちろん、お互いの性格に合わせてみるのもひとつの手ですよ。
まとめ
片づけと聞いただけでネガティブになってしまう方も少なくないと思いますが、片づけの基本と掃除の基礎を知っておくだけで効率よく家事を進めることができます。
二人で取り組めば、コミュニケーションもとれ、時短にもなるので一石二鳥ですよね。
自宅を理想の空間にするため、この家事テクニックを活用して今日から少しずつ始めてみましょう!
引用書籍:「もっと簡単に、ずーっとキレイ! ラクして続く、家事テク」(牛尾理恵 著/朝日新聞出版)2018年8月出版
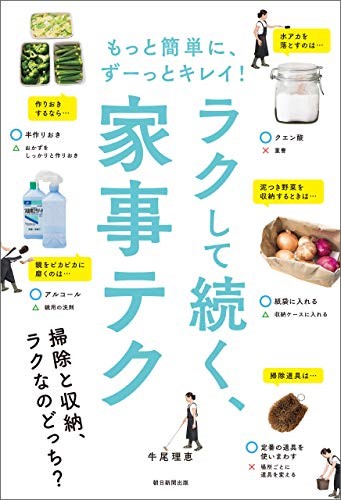
出版社・書籍紹介:「もっと簡単に、ずーっとキレイ! ラクして続く、家事テク」(牛尾理恵 著/朝日新聞出版)2018年8月出版
・Amazon
・楽天ブックス
・紀伊國屋書店
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事

























