
ズボラさんでも安心、水回りのちょこちょこ掃除テク
目次 [CLOSE]
毎日忙しい方や掃除嫌いさんにおすすめ。水回りの掃除テクをご紹介

お風呂、洗面所、シンクなど水回りの掃除は、忙しいと後回しになりがちですが、水回りの汚れは放置すると落としにくくなってしまうのが悩みのタネです。今回は、簡単にキレイをキープできるお掃除のコツを紹介します。
水回り掃除に手こずっている人は多い!

汚れのたまりやすい水回りは、こまめな掃除が大事です。しかし、掃除がしにくい、水垢やヌメリなどが不快、寒い時期は掃除がおっくう、などの理由で、水回りの掃除に苦手意識がある方はたくさんいます。
お風呂場は水垢取りやカビ落としなどがゆううつ
鏡や蛇口についた水垢や石鹸カスの掃除、椅子の裏やパッキンについたカビ落としなど、水をよく使うお風呂場は掃除が大変になりがちな場所です。床や排水口にヌルヌルしたピンク色の汚れがつくのも気になりますね。
また、寒い時期はお風呂場に掃除へ行くのもおっくうになります。寒い時期こそ清潔で温かいお風呂でリフレッシュしたいのに、悩ましいところです。
鏡の汚れ、落ちた髪の毛が気になる洗面所
洗面所の鏡も汚れが気になる場所です。洗面所の鏡には、水垢のほか、洗顔や歯みがきのときに飛び散った石鹸や歯磨き粉が付着していることもあります。こちらも固まると掃除が大変です。
洗面所では、ドライヤーを使って髪の毛を乾かしたり、髪の毛を整えたりすることが多いので、髪の毛がよく床に落ちてしまうのも気になります。
シンク周りはいろいろな汚れがあって大変!
シンク周りはたくさんの種類の汚れが発生する場所です。水垢汚れや油汚れ、食器用洗剤を使うときに出る石鹸カスの汚れ、排水口のヌメリなど、あらゆる汚れが現れます。
シンク周りは食べ物の用意をするところですから、なるべく清潔を保ちたいもの。そうはわかっていても洗剤を使い分けて掃除をするのは大変ですから、掃除にストレスを感じる場所でもあります。
水回りの掃除を放置するとどうなる?

忙しいとつい後回しになる水回りの掃除。放置しておくとどのような事態が起こるのでしょうか。
悪臭や害虫の原因になることも
ごみ受けやヘアキャッチャーなど、排水口付近にたまった汚れを放置していると、ヌメリやカビが発生してしまいます。ヌメリやカビを放置していると、悪臭の原因にもなります。
また、水回りの汚れは、チョウバエやゴキブリなど害虫の栄養となる成分を含んでいます。チョウバエやゴキブリは生命力が強く大量発生の恐れもあるため、適切な駆除はもちろん、水回りを清潔にしてそれらを寄せ付けないことが大切です。
個人で対策できない汚れになることも
例えば、ホコリがたまっただけの状態の場合では、簡単に掃除をすることができます。しかし、最初はただのホコリでも、空気中の水分を含んだり、調理のときなどに出た油を含んだりするうちに、ガンコな汚れとなってしまいます。
その状態をさらに放置すると、ホコリが素材自体に吸着し、掃除がとても大変になります。
汚れの層が何層にもなってしまうと、素人の掃除でキレイにすることは難しくなるため、ハウスクリーニング業者への依頼が必要になるかもしれません。
水回りは、なるべくラクに「ちょこちょこ掃除」
「水回りはこまめな掃除が大事」だとはわかっていても、毎日しっかりとお掃除をするのはハードルが高く大変です。なるべくラクに、ちょこちょこと掃除ができるよう、普段使いのアイテムを見直してみるのもおすすめです。
これでカンタン お風呂場のちょこちょこ掃除

お風呂場の掃除は、扱いがラクな掃除道具を選ぶことから。なるべくストレスをかけず、掃除ができるようにしましょう。
毎日のお掃除はスポンジでササッと
入浴後のお風呂場は、石鹸カスや水垢、皮脂などの汚れが付着している状態です。温かく水気のある入浴後のお風呂場は、カビや細菌などが繁殖しやすい環境なので、ほったらかしにすると危険なことに。
とは言え、汚れがついて間もない状態なら、スポンジでササッと洗うだけで大丈夫です。あとで大変なことにならないよう、「ちょこちょこ掃除」の習慣をつけましょう。
バスポリッシャーは天井掃除やタイル掃除の強い味方
少ない力でお風呂掃除ができるところが魅力のバスポリッシャー。腰をかがめる必要もないため、体への負担も少なくなります。
スグに完了 洗面所のちょこちょこ掃除点

ふとしたときに気になるのが洗面所の汚れ。気が付いたときに、サッと使える掃除道具があれば便利です。
鏡や蛇口の汚れにはマイクロファイバークロス
マイクロファイバークロスとは、ナイロンやポリエステルでできた合成繊維「マイクロファイバー」で織られた布です。髪の毛の100分の1ともいわれる極細の繊維で織られており、かつ繊維の断面がギザギザになっているため、水やホコリをよく取ってくれるところが特徴です。
鏡や蛇口の汚れは、マイクロファイバークロスを使うことでキレイになります。また、マイクロファイバークロスは繊維の毛羽立ちが起きにくいため、水拭きの跡や繊維のくずが残りにくいという特徴もあります。
洗面所の床はフロアワイパーでお掃除
洗面所の床は、髪の毛やホコリですぐに汚れてしまう場所です。こまめに掃除機をかけたいところですが、掃除機の収納場所が洗面所から遠い、出し入れが面倒、掃除機重たい、などの理由があると、掃除機がけが負担になることも。
そんなときは、フロアワイパーを洗面所に置き、「ちょこちょこ掃除」に使ってみてはいかがでしょうか。
ラクにキレイに シンク周りのちょこちょこ掃除

いろいろな種類の汚れが付着するシンク周りは、ラクに使える洗剤がいいですね。シンク周りは食べるものを扱う場所なので、自然由来の身体にやさしい洗剤もすおすすめです。
エコで節約にも ナチュラルクリーニングに注目
水垢汚れはアルカリ性の汚れ、油汚れは酸性の汚れのため、落とし方が異なります。アルカリ性の汚れには酸性の洗剤を、酸性の汚れにはアルカリ性の洗剤を使いましょう。酸性洗剤であるクエン酸と、アルカリ性洗剤である重曹があれば、シンク周りのお掃除に役立ちます。
クエン酸や重曹など自然由来の天然成分は、環境や人体にやさしく、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心して使えるものです。自然由来の天然成分を使ったお掃除は「ナチュラルクリーニング」と呼ばれており、近年注目を集めています。
クエン酸や重曹は、いろいろな場所のお掃除に使えるので、さまざまな種類の洗剤がいらなくなり節約になるというメリットもあります。
水垢汚れに クエン酸の使い方
クエン酸を掃除に使う時は、クエン酸水でスプレーをつくると便利です。クエン酸水の作り方は、スプレーボトルに水(42℃前後のお湯でもOK)100mlあたり小さじ1/2のクエン酸を入れて、よくふって混ぜるだけです。
シンクや蛇口についた水垢の掃除をするときは、クエン酸スプレーを吹きかけてから水拭きをして、マイクロファイバークロスで仕上げると、白っぽいくもりが取れやすくなります。
頑固な水垢汚れの場合は、クエン酸水を含ませたキッチンタオルで汚れ部分をパックして、1時間ほど放置しましょう。パックした部分を食品用ラップで覆うと効果がアップします。時間が過ぎたらパックをはがし、汚れの部分をスポンジで軽くこすると、頑固な汚れも取れやすくなりますよ。
クエン酸を使う時の注意点
- 酸性のクエン酸は、塩素系と混ざってしまうと有害なガスが発生します。危険ですから、塩素系の製品とは併用しないでください。
- 金属や大理石にクエン酸を使うと、錆びたり溶けたりする原因になります。それらの素材への使用は避けましょう。
- 濃度を濃くしたり放置時間を長くしたりしすぎると、肌や素材に影響が出る恐れがあります。
- 中の水が腐敗してしまうため、クエン酸スプレーは1~2週間で使いきりましょう。
油汚れに 重曹の使い方
重曹を使ってシンクを掃除するときは、シンクに重曹を振りかけ、濡らしたスポンジなどでこすり洗いをします。こすり洗いの後は、水で洗い流しましょう。
しつこい汚れの場合は、重曹を振りかけたあとでクエン酸を溶かしたお湯を流し込みます。重曹とクエン酸が混ざると泡が出てきますが、無害な炭酸ガスなので問題はありません。この泡が、しつこい汚れを浮き上がらせてくれます。掃除の最後には、しっかりと水で洗い流しましょう。
重曹を使う時の注意点
- 重曹には研磨作用があるので、やわらかい素材に使うと傷をつけてしまう場合があります。気になる素材に使うときは、目立たないところで試してから使いましょう。
- 重曹をアルミの製品に使うと、黒く変色させてしまうことがあります。畳や白木も変色の可能性があるため、使用を避けてください。
キッチンの排水口は気付くとヌメリが…
気付くとヌメリができているキッチンの排水口。ヌメリの正体は、細菌が汚れを餌に増殖するときにできる膜で、「バイオフィルム」といいます。
バイオフィルムの発生を予防するには、こまめな除菌が大切です。
自分にとってのベストを探して、ラクなお掃除習慣を
すぐに汚れる水回りの掃除は、できればラクに済ませたいものです。ラクに掃除をするためには、洗剤をむやみに増やさない、取り扱いがラクなグッズを使う、といったポイントがあります。
しかし、ちょこちょこ掃除を続けるのに一番大切なのは、なんといっても自分が取り組みやすいお掃除方法を見つけることでしょう。
巷には、さまざまなお掃除テクニックやグッズがありますが、生活習慣や好みは人それぞれです。「もっと効率よくするにはどうしたらいいだろう?」と、ちょっとした実験のような気持ちで、ちょこちょこ掃除にトライしてみてくださいね。
この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事
-

【図解】エアコンの冷房と除湿の違いは?適切な使い分けや電気代を比較
-

【図解】サーキュレーターの効果的な使い方は?効率を上げる置き方を解説
-

【図解】冷房の適切な風向きは上向き!電気代や体感温度を下げる方法を解説
-
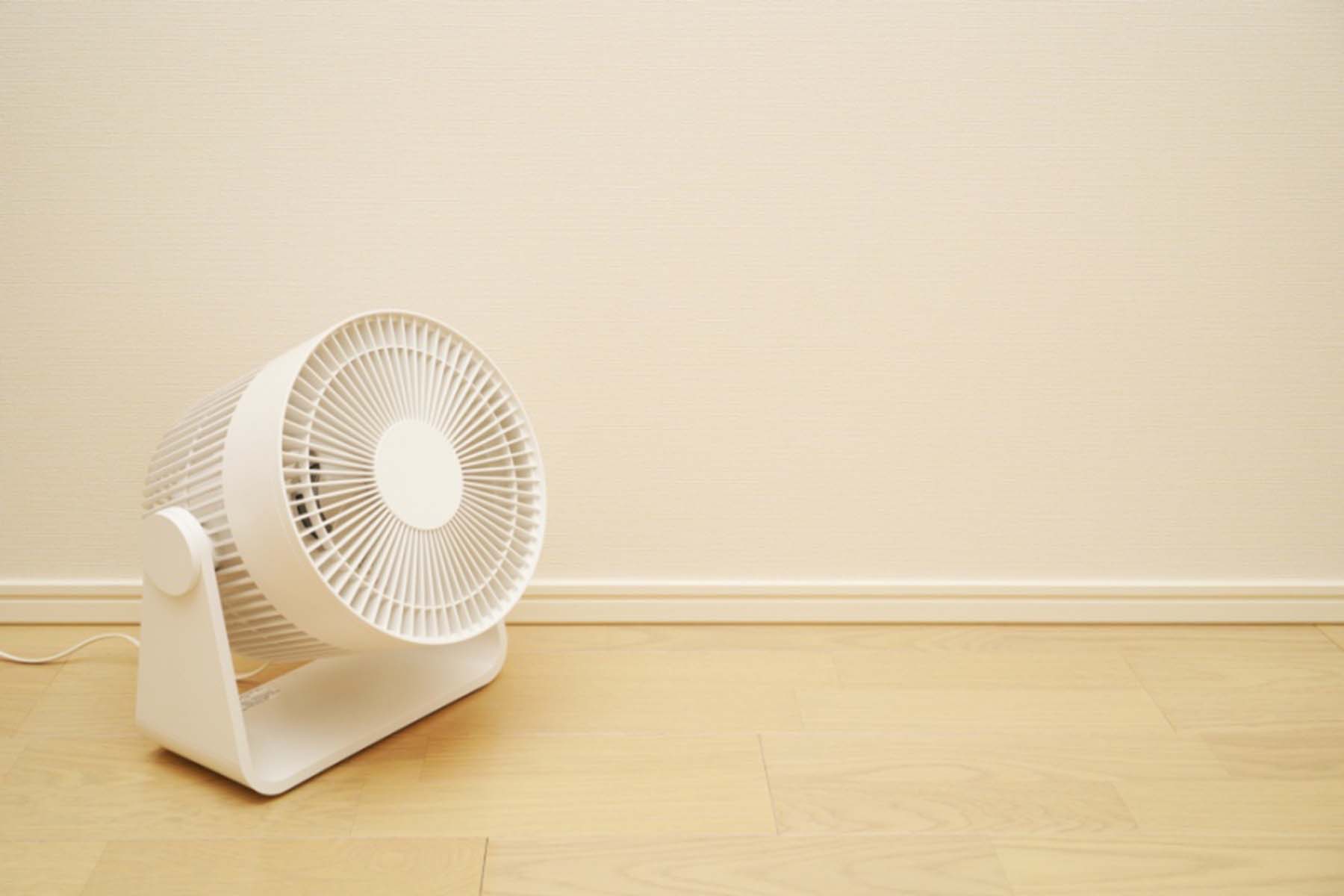
【図解】冷房にサーキュレーターは逆効果?正しい置き方と使い方
-

医師監修:寝るときの冷房の温度は何度が最適?おすすめの設定を解説
-

部屋の適正湿度は?温度とのバランスや適正に保つ方法を解説
-

エアコン除湿の電気代を解説!冷房・除湿機との料金比較や節約法も
-

東京電力のエアコンクリーニングの特徴は?安心価格・高品質・高技術!
-

エアコンとクーラーの違いとは?仕組みと機能を簡単に解説
-

エアコンフィルターの掃除方法は?手順や頻度、節電方法も解説
-

エアコン冷房を1か月つけっぱなしにしたら電気代は?節電方法も解説
-

東京電力の「住宅設備・家電修理サービス」とは?費用やプランを徹底解説!
-
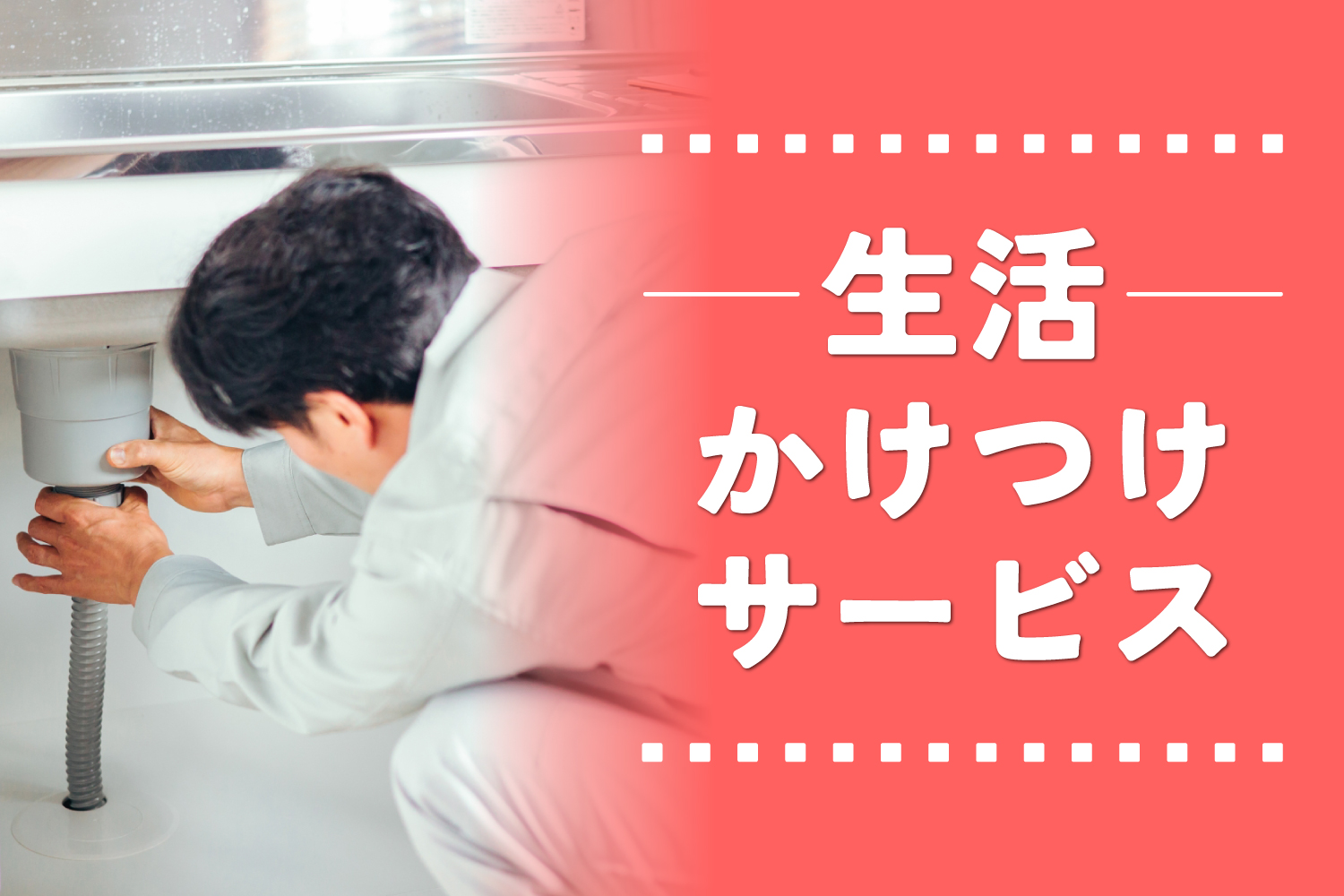
緊急時に頼れる東京電力の「生活かけつけサービス」を徹底解説!
-

エアコンの電気代は?使用時間・期間あたりの電気代や節電方法も
-

エアコンからぬるい風しか出ないときはリセット!原因も解説
-
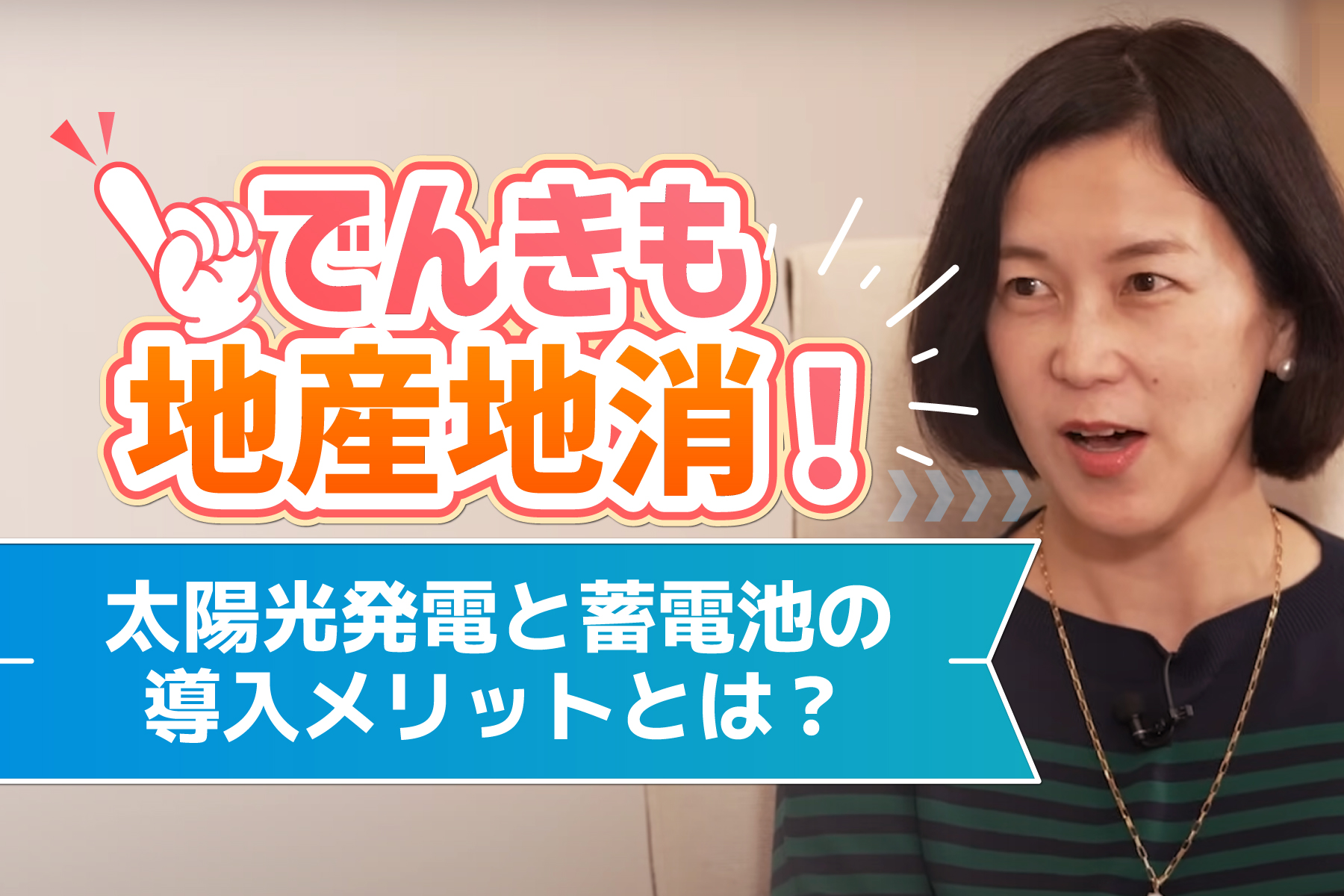
でんきは自宅で地産地消!太陽光発電と蓄電池の導入メリットとは?
-

冷凍庫の適正温度は-18℃以下!温度が高くなる原因や対処法を解説
-
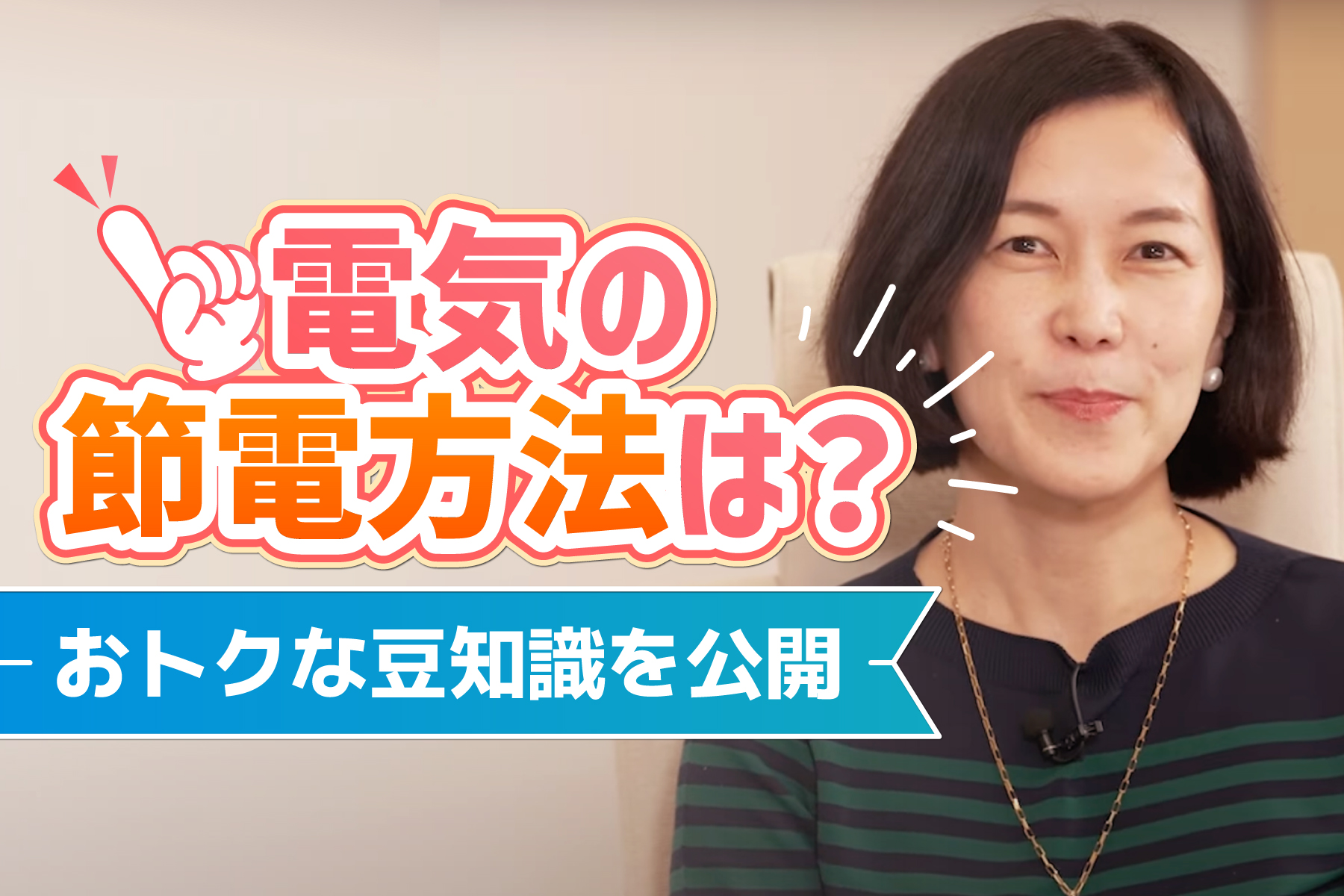
東京電力EP社長直伝!電気代の節約方法は?おトクな豆知識を公開
-

IHの電気代はいくら?ガスコンロとどっちが安い?節約術も解説
-
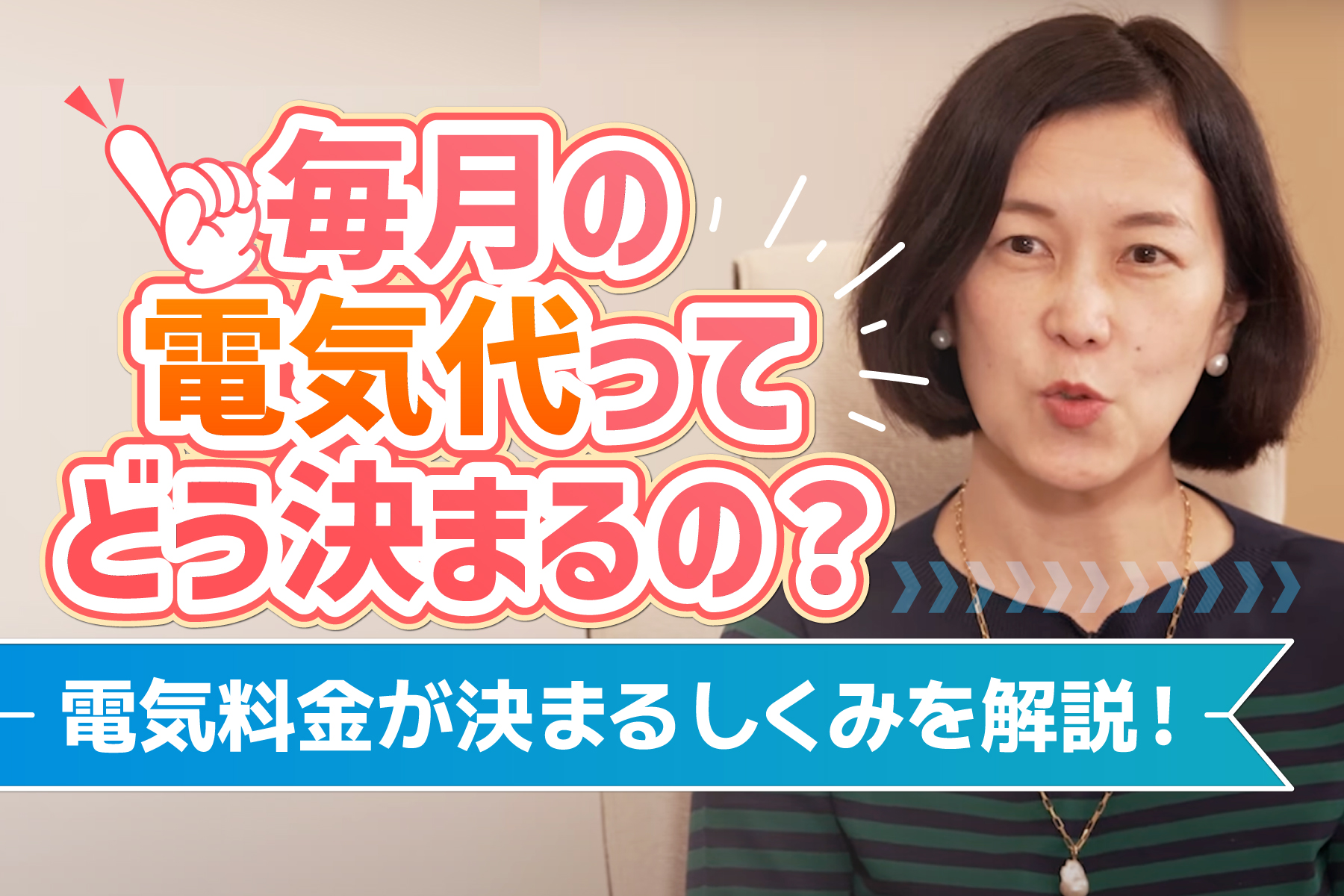
毎月の電気代ってどう決まるの?電気料金のしくみを解説!





