
仕事を辞めたい時にすべきことは?退職の判断基準や流れも解説
そこでこの記事では、仕事を辞めたいと思う理由や、やる気がでない場合の原因と対処法、退職の判断と流れについて、詳しく解説します。
仕事を辞めたい主な理由5つ
まずは仕事を辞めたいと考える際に、どのような理由があるのかを見ていきます。なかには、スキルアップやキャリアアップなど前向きな理由から仕事を辞める方もいますが、この記事では、今の仕事の環境・内容と自分の理想にギャップを感じて「仕事を辞めたい」と思う場合の理由に焦点を当てていきます。
以下で、代表的な退職理由について5つご紹介します。
人間関係が悪い
退職理由としてもっとも多いのが、人間関係によるものです。職場での孤立や、職場の人と馬が合わないというケースは少なくありません。こうした状況がストレスとなり、仕事を辞めたくなる原因になりえます。
学生時代と違い、社会に出ると付き合う人を自分では選べなくなります。関係性が良好でない上司や同僚などと今後も仕事を共にしなくてはならない状況というのは、やはり辛いと感じるものです。
給与が低い
自分の働きが給料と見合っていない、もしくは、今後のキャリアアップも望めないといった状況は、転職の大きな理由のひとつです。どんなに好きな仕事でも、満足のいく賃金が出ていなければ、継続は困難になります。
また、給与だけでなく福利厚生面に不満があるケースも考えられます。ある程度の金額を稼げていたとしても、必要な福利厚生が整っていなかったり、他社に比べて充実していなかったりする場合には、モチベーションダウンの理由になりえます。
残業時間などの待遇への不満
連日の残業や休日出勤など、過酷な労働が続けば、気持ちより先に体力の限界が訪れ、退職のきっかけになってしまいます。とくに、サービス残業やサービス出勤、常習的な徹夜対応などがあるブラックな状態は、従業員のワークライフバランスを崩していきます。
仕事の経験やスキルは身につきますし、一定の達成感も得られますが、ストレスや体力の許容範囲を超えてしまうと、不満が募り「辞めたい」と思うのは当然です。
仕事内容に不満がある
自分の業務にやりがいを見出せなくなってしまったり、自分の適性と合っていない業務ばかり振られたりすると、仕事内容自体に不満が募ります。「自分の人生をムダにしているのでは?」と疑念や焦りを感じる方もいるでしょう。

「仕事はお金を稼ぐ手段」と割り切れればよいかもしれません。しかし、どうしても仕事が好きになれなかったり、自分に合っていないと感じたりした場合は、退職を考えることにつながります。
社風が合わない
自分の性格に対して社風が厳しすぎたり、落ち着きすぎていたりすると、ミスマッチを感じて仕事を辞めてしまう人も少なくありません。こうした環境は自分ではどうしようもできないので、別の職場に移りたいと考えるのは自然です。
そのほかにも、チャレンジが難しい空気が蔓延していたり、安定した経営ができていなかったりすると、それが不満となって退職のきっかけになってしまいます。
仕事を辞めたい時にすべき3つのこと
ここからは、より具体的な内容について触れていきましょう。まずは「仕事を辞めたい」と思った時にしておきたい3つの行動です。
辞めたい理由を明確にする
まずは、自分がなぜ仕事を辞めたいと考えているかについて、冷静に分析をしてみましょう。多くの場合、その理由は人間関係や給与など、いくつかの要素が複合的に絡み合っているはずです。
そこで、いったん自分が感じている不満をすべて紙に書き出すのがおすすめです。その上で、より不満に思う事項から順位を付けてください。紙に書き出した内容を俯瞰すると、自分が会社を辞めたい理由を客観的に把握できます。
自分で解決できることなのか分析する
自分の悩みを客観視できたなら、次は解決策について模索してみましょう。自分で行動を起こせば解決できるような悩みなら、退職する必要はないかもしれません。例えば、給与額に不満があるのなら、一度上司へその旨を相談してみてください。会社にとって必要な人材だと認められていれば、昇給が叶う場合もあります。

人間関係についても同様です。例えば、苦手だと感じる同僚が多い部署にいるのであれば、人事に異動を申し出るのもひとつの手です。どうしても馬が合わない人がいてストレスが募る、といった状況なのであれば、担当変更などでその人と関わらない状況を作り上げるのです。
このように、行動次第で解決できる問題も少なくありません。自分だけで解決が難しい問題であっても、他人に頼ることでサポートやアドバイスをもらえる場合もあります。
退職・転職後に解決する問題なのか考える
退職や転職は、抱えている問題を解決するのに有効な手段のひとつです。しかし、すべての問題が退職・転職によって解決できるとは限りません。一部は解決できたとしても、今度は別の問題が生まれる可能性も考えられます。
具体的には、給与額に不満があるから退職をしたのに、次の就職先がなかなか決まらなかった場合は、より生活が不安定になってしまいます。仕事内容に対する不満についても、別の会社ならやりがいを持てるかと言えば、必ずしもそうではありません。現在の悩みと、退職後のリスクを天秤にかけ、辞めるメリットが大きいと判断できる場合に、退職・転職を決断することが大切です。
仕事への気力が出ない場合はどうする?原因と対処法
何らかの原因によって仕事に対する気力が失われてしまっている場合は、原因を把握し、適切な対処を行いましょう。なくしていたやる気を取り戻せる可能性があります。
仕事のやる気が出ない原因
問題解決の第一歩は原因の究明です。なぜモチベーションが上がらないのかについて、自問自答してみましょう。代表的な例としては、以下のような原因が挙げられます。
- 職場の人間関係やノルマなどにストレスを抱き、心身ともに疲れ果てている
- 家族や恋人との関係、自身の健康など、プライベートでストレスを感じている
- 自分の仕事に対する評価に納得できていない
- 仕事や会社とミスマッチがあり、割り振られた仕事内容に興味を持てない
無気力状態を解消する対処法
仕事が手につかず、何もやる気が出ないという悩みは、簡単に解決できるものではありません。ある程度時間をかけてじっくりと解決していく必要があります。
そこで大切なのが、仕事とは別の部分で楽しみを見出すことです。プライベートを充実させたり、見た目を変えてリフレッシュしたりするのも良いでしょう。また、心身ともにヘトヘトなのであれば、無理せずしばらく休むことも大切です。

会社との条件面で折り合いがつかずにストレスを感じている場合は、一度上司に相談してみることをおすすめします。自分が挑戦してみたい領域の仕事を、今後振ってもらいやすくなる可能性もあります。また、上司から業務の采配や待遇の意図を聞くことで、現状に納得でき、前向きになれるかもしれません。
さらに、自分の希望と会社のニーズがマッチすれば、より適正に合ったポジションへの異動や昇給などが叶うことも考えられます。
さまざまな対処法を試し、それでもやる気が回復しないということであれば、退職を視野に入れましょう。
仕事を辞めるかどうか判断するポイント
退職の意思はあるものの、そのタイミングが今すぐなのか?それとも、検討の余地があるのか?といった判断は、なかなかつきにくいものです。ここでは、即退職が必要かどうかを判断するポイントについて解説します。
早急に退職すべきケース
まずは、できる限り早く退職をすべきケースについて、その条件を見ていきましょう。一つ目の条件は、以下のような状況に当てはまる場合です。
- 日常的なパワハラやセクハラ
- 違法性のある長時間労働の強要
- 肉体的・精神的に負担の大きい健康を害す作業
上記のような環境での労働は、心身に危険を及ぼしますので、少しでも早く退職を決断しましょう。
内容次第ではありますが、損害賠償請求が可能になるようなケースも考えられます。現状はもちろん、将来のことも考えると、一日でも早く退職をするのがおすすめです。一度体調を崩すと、回復までに時間がかかったり、悪化したりして、転職のハードルが上がる可能性があります。
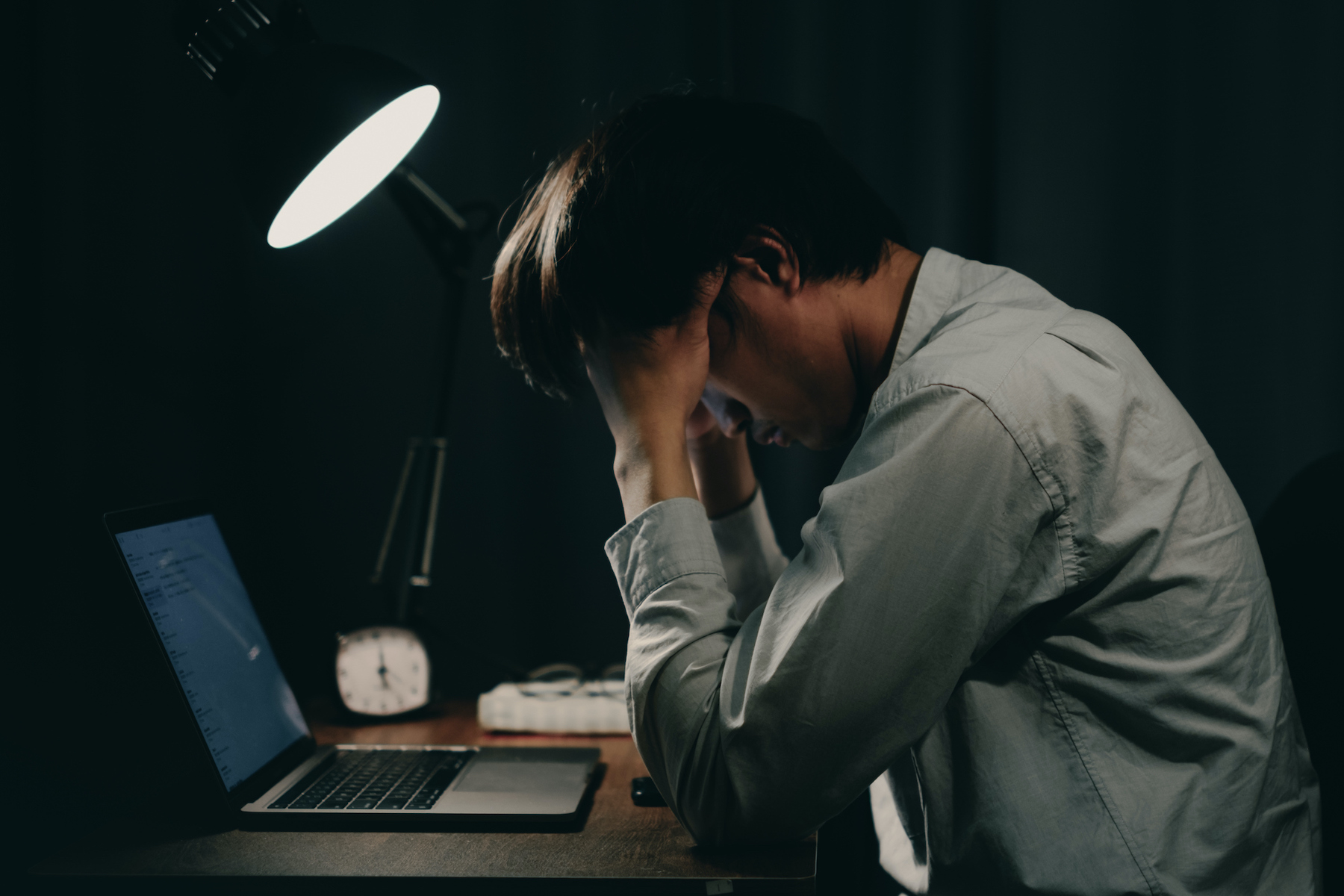
二つ目は、仕事に抱える不満を自分自身で解消するのが難しい場合です。例えば、部署異動や昇給を申し出たものの、受け入れてもらえないような状況です。今後、自分の努力で改善ができる見込みがあればよいですが、会社の方針や経営状況上それが難しいとなると、退職・転職によって問題を解決するしかありません。
また、人間関係や社風なども自分で解消することが難しい例の一つです。自分がどんなに友好的に振る舞い、関係を改善しようと試みても、同僚や上司の態度は変わらないということもあるでしょう。また、チームでコミュニケーションをとりながら仕事をしたいと考える人が、個人で仕事を進める社風の会社にいる場合、ギャップを埋めることは難しいかもしれません。こういった場合も、退職・転職をして、新天地であらためて頑張ることが適しているといえるでしょう。
慎重に退職を検討すべきケース
次に、退職を慎重に検討すべきケースについてです。
退職の理由が、結婚や介護などライフスタイルの変化にある場合は、退職ではなく「働き方を変える」という選択肢もあります。例えば時短勤務やリモート勤務など、キャリア自体は維持しつつ、負担を軽減するという方法があることも覚えておきましょう。
退職後、何の職にも就かずに長い期間を過ごすと、復帰が遅れる原因にもなりえます。どうしても辞めざるを得ない場合は、再就職のプランを立てておくことをおすすめします。とくに介護での退職は、収入が途切れると自分を含めた家族の生活に影響します。この場合も、できるだけ退職ではなく、介護休暇や両立支援制度などの活用も検討してみましょう。
その他、上司とのコミュニケーションや、仕事が非効率であることが理由の場合は、改善する方法がないかどうかを考えてみてください。実際には、とくに対処をしないまま、先に退職をしてしまう方も少なくありません。この場合、転職をしたとしても、結局別の会社で同じ状況が繰り返される可能性があります。まずは改善できるか試してみてから、退職を検討するようにしましょう。
一般的な退職までの流れを解説!
検討の結果、退職することを決断した後は、会社に対して手続きを行う必要があります。以下で、一般的な退職までの流れを解説します。
1. 1~2カ月前までに退職の意思を伝える
退職を決断したら、予定日の1~2カ月前までに直属の上司へその旨を伝えましょう。なお、退職の申し出の期限は、法的には14日前と定められています。しかし、実際には後任者の手配や業務の引き継ぎもあるため、余裕を見て伝えるのがおすすめです。
また、就業規則に退職の申し出期間に関する規定がある場合は、その内容に従っておくほうが無難です。ただし、半年前、1年前など、極端な既定の場合は無理に従う必要はありません。
2. 退職日を決定し、退職願を提出
上司と相談をしてもなお、退職の意向が変わらない場合には、退職日を決めます。この際のポイントとなるのが、次の仕事です。
転職先が決まってから退職するか、決まる前に退職するかは、個人の状況や志向次第です。例えば、在職中に転職活動ができる人や、キャリアアップが目的の人、無収入期間を作りたくない人の場合は、先に内定が出てから退職日を決めます。

一方、忙しくて転職活動ができない人、無職期間で新たなスキルを身に着けて別の業種にチャレンジしたい人、しばらくは生活資金に余裕がある人に関しては、退職後に転職活動をしてもよいでしょう。
退職日が決定した後は、その日付を記載した退職願を上司へ提出しましょう。ちなみに、退職願等の届け出については、会社ごとに要不要が異なります。詳しくは、就業規則を確認してください。
なお、退職願と退職届には以下のような違いがあります。退職届を出すと万が一の際に撤回できなくなりますので、基本的には退職願を提出するようにしましょう。
- 退職願
- 退職を願い出るための書類。撤回が可能。円満退社のためにも退職願が用いられるのが一般的。
- 退職届
- 会社側の意思にかかわらず退職を通告する書類。撤回不可。退職願いを提出して会社の承諾を取った後、退職届を提出することもある。
3. 業務の引き継ぎ
退職日を迎えるまでは、滞りなく仕事を引き継げるよう、マニュアルなどの資料作成に注力しましょう。もしも後任者が決まっている場合は、一緒に業務を行い情報共有することも大切です。
4. 社内・社外への挨拶
退職日が近づいてきたら、社内・社外への挨拶回りを行います。ただし、実施すべきかどうかは会社次第であるため、動向に従いましょう。近年は、直接かかわりがある人以外へのあいさつは、メールで済ませる場合も多いです。
なお、後任が決定している場合は、挨拶の際に同行を依頼するのが一般的です。取引先に後任を紹介し、その後のスムーズな業務につなげられるようフォローしましょう。
まとめ
退職は、人生において大きな決断のひとつです。だからこそ、冷静に自分を見つめ直した上で、正しい判断ができるよう努めましょう。退職や転職について真剣に考えることは、必ずご自身の成長につながるはずです。今回の記事を参考に、ぜひ仕事やご自分について、じっくり振り返ってみてください。
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事


























