
どうして女性は冷えやすい?冷えの理由と体を温める食事
実はその「冷え」、食生活が原因の一つになっていることもあるのです。今回は、33人の医師や専門家の知恵が詰まった『本当にすごい冷えとり百科』(オレンジページ)から、体の内側からぽかぽかを目指す食材や食べ方についてご紹介します。
目次
体が冷える理由
「手足が冷たい」「寒くて眠れない」といった自覚症状のある冷えはもちろん、肩こりや頭痛、生理痛など女性が悩まされている不調は、元をたどれば「冷え」が関わっている場合が多くあります。
そもそも、なぜ「冷え」という現象が起きるのでしょうか?
人間の体は、食事や運動で熱をつくり出し、その熱を血流に乗せて全身に行き渡らせています。外が寒くても体温を37℃前後に保つことができるのはこのシステムがあるからなのですが、熱を十分につくれなかったり、体のすみずみまで熱をうまく運べなかったりすると、体内の熱がかたよって「冷え」が発生するのです。
しかも、一か所血流が悪くなると、全身に冷えが広がってしまいます。体が冷えて血流が悪化することにより、各器官の機能が低下して全身の不調へと連鎖するのです。冷えの原因は体質や加齢だけでなく、食事などの生活習慣、ストレス、運動不足などの影響が大きいと言われています。
しかし、ストレスは社会生活を送っているうえではなかなか根本的に解決できなかったり、急に運動を始めようと思ってもハードルが高かったりしますよね。そこで、日常に取り入れやすい改善方法として「食べ物」から始めることがおすすめです。
毎日の食事に体を温める食べ物を取り入れれば、手軽に冷え対策ができるのです。
体を温める食べ物とは?
体内の熱は、食べ物に含まれるさまざまな栄養素を吸収・代謝することによって生み出されていますので、食事の内容や調理方法を工夫することで冷え体質改善を目指すことができます。
体を温める食事を続ければ全身の血行もアップし、内側から熱をつくり出せるようになりますので、体を温める食べ物を4つの視点から見ていきましょう。
筋肉の元となる食べ物

体温を上げるのに筋肉は大切な存在で、その筋肉を作る材料になっているたんぱく質はしっかりとらなければなりません。
納豆や豆腐、みそなどの大豆製品には良質なたんぱく質が豊富に含まれており、肉や魚より脂肪分が少ないほか、便秘を防ぐ食物繊維、女性ホルモンに似た働きをする大豆イソフラボンも含有しています。
そして、レバーやひじきなど鉄分を多く含むものを食べることも大切です。鉄分は酸素を運ぶ赤血球を作るもとになり、その赤血球が運ぶ酸素はエネルギーを燃焼し体を温めるのに欠かせないのです。
体のめぐりをよくする食べ物
せっかく作った熱も体のめぐりが悪ければ届けることはできませんので、血流をよくする食べ物もバランス良く摂りたいものです。ここではしょうが、ナッツ類、根菜についてみていきましょう。
体を温める食べ物で思い浮かぶものといえば「しょうが」ではないでしょうか?
しょうがに含まれる成分は血流促進、殺菌作用、整腸作用に加え、脂肪や糖質の燃焼を促して体温を上げる効果があります。料理や飲み物に入れるなど使い勝手が良いので、普段の料理に取り入れてみてはいかがでしょうか。

ナッツ類は、ビタミンEが持つ強力な抗酸化作用が血栓を防いで血液をサラサラにしてくれます。くるみやアーモンドなどのナッツ類は、砕いて料理にふりかけたりすると、こまめに補給することができますし、料理のアクセントにもなるのでおすすめです。
さつまいも、にんじん、大根、ごぼう、れんこんなどの根菜類はビタミンCを多く含んでいます。ビタミンCは血液を作る鉄の吸収やビタミンEの抗酸化作用を高める強力なサポーター役です。さらに、それだけではなく、豊富な食物繊維は便通を解消して血流もスムーズにする働きがあります。
余計な水分を出す食べ物
体に余計な水分がたまると冷えやすくなります。冷えは血行不良につながり、さらに水分がたまるという悪循環に陥ってしまいますので、利尿効果のある食べ物で余分な水分を体の外に出してあげるとよいでしょう。
利尿効果を期待するなら、きゅうりや山いも、小豆などが効果的です。ただし、きゅうりはそのまま食べると体を冷やしてしまうので、塩もみやぬか漬け、炒めものにするのがおすすめ。山いもは腎臓の血行をよくして水分を排出するほか、強精作用があり体を温めてくれます。小豆は皮に含まれる「サポニン」という成分に高い利尿作用があり、むくみやダイエットにも効果的です。
腸内環境を整える食べ物
健康のバロメーターとして注目される腸は、冷えとも大きなかかわりがあるのです。幸せホルモンと呼ばれる「セロトニン」は腸の粘膜から分泌されていて、セロトニンが多いほど精神が安定し睡眠の質が高まります。睡眠の質が良くなると自律神経が整えられて、血流の循環が良くなるので、体が温まりやすくなりますよ。
冷えを改善するには腸内環境も整える必要があるとわかりました。そこで、腸内環境を整えるためにおすすめしたいのがヨーグルトです。ヨーグルトに含まれる乳酸菌が善玉菌を増やして、腸内環境を整えてくれます。
さらに、ヨーグルトは人肌程度に温めると胃腸に負担をかけず、乳酸菌のパワーをより活かすことができるのです。1、2回食べるだけで効果は得られないので、是非毎日続けてみてくださいね。
また、ヨーグルトの他に腸内環境を整える食べ物として、「納豆塩麹」もおすすめです。納豆塩麴とは、納豆と塩麴、玉ねぎのみじん切り、皮つきしょうがのせん切りを混ぜて冷蔵庫で一晩ねかせた発酵食品です。
納豆に含まれるナットウキナーゼが血液をサラサラにして血行不良による冷えを改善しつつ、塩麹の麹菌が腸内環境を改善し、さらに、血めぐりをよくし体を温める作用がある玉ねぎと、発汗作用のあるしょうがの効果で冷えに効果的に働きかけます。
婦人科トラブルを改善する食事とは?
女性が気になる不調には、生理痛やPMS(月経前症候群)などの婦人科トラブルがありますよね。これらのトラブルには、子宮の血めぐり悪化が深くかかわっています。
女性にとって特に大切な器官である子宮には、栄養分を届けるためにたくさんの血液が流れ込んでいるため、冷えをとり血めぐりをよくすることはとても大切なのです。ここでは、女性ならではの不調の原因と、それを改善するための食べ物についてご紹介します。

冷えは女性ならではの不調の原因になる
子宮の血流が冷えて滞ると、子宮の筋肉がコチコチに硬い状態になってしまい、生理痛やPMS(月経前症候群)、生理不順などのトラブルを引き起こしてしまいます。
さらに子宮や卵巣が冷えによって正常に機能しなくなると、ホルモンや自律神経のバランスも乱れてしまうのです。そうなると女性ならではの不調にとどまらず、代謝や免疫力など体全体の機能低下にも繋がります。
寝起きにオススメの飲み物
生理中は体が重く、フラフラとしてしまう人が多いのではないでしょうか。そんな日の朝は代謝と体温が落ちているだけではなく、貧血で布団から起き上がるのも辛いですよね。寝ている間に失われた水分を補給するため、コップ一杯の水や白湯を飲むことは大切ですが、著者がおすすめするのは代謝と体温をあげるプルーンエキスを溶かしたお湯です。
プルーンエキスは鉄分を含んでおり、貧血になりがちな女性の血液をつくるサポートをしてくれますし、温かい飲み物は胃腸から全身を温めて子宮にも血液を送る働きもあります。
生理中はもちろん、普段から鉄分を取ることは冷え改善につながりますので、毎朝の習慣にするのもいいかもしれませんね。

体温低下にもつながる貧血を防ぐ食べ物
女性は1回の生理で約20~30mgの鉄を体外に流出するため、生理中は特に意識をして鉄分を含んだ食事を摂るとよいでしょう。
体の熱は血流に乗って全身へ運ばれるので、貧血になると血めぐりが悪くなり全身の冷えにつながってしまうのです。そこでおすすめしたい食べ物が、赤身肉やレバーです。赤身肉やレバーは鉄分をたくさん含んでいるため貧血改善に効果的で、体温低下を防いでくれるのです。
リラックスさせてくれる飲み物
生理中や生理前など、ホルモンバランスが変動する時期は、徐々に精神的な不調がでてしまいます。そのような不安定なときにリラックスができず緊張が続くと、体がこわばってしまい血行不良に陥り、冷えに発展してしまうのです。
そこで、おすすめしたいのがリラックスさせてくれるあたたかい飲み物を飲むことです。カモミールティーなどのリラックス効果の高いハーブティーを飲むことにより、不安定な気持ちを整えることができます。心が安らげばこわばっていた体も力が抜け、血めぐりもよくなるはずですよ。

体質から見直す漢方の知恵
がんこな冷えへの最終手段として漢方がありますが、「どこで買えるの?」「どうやって選んだらいいの?」などの疑問や不安もありますよね。
ここでは、冷えに効く漢方薬の成分や副作用などの基本を学びましょう。
冷えに効果があるという「漢方」とは?

漢方とは東洋医学から生まれた自然素材の生薬です。「冷え」は、東洋医学では病気ではないものの病気に向かいつつある「未病」の状態ととらえられています。
漢方は「血や栄養のめぐり」「エネルギーのめぐり」「水のめぐり」の3つが滞ったり、不足したり、バランスが崩れたときに起こる不調を、その人の今の体の状態やもともとの体質に合わせて根本から改善することができるのです。
漢方の多くは天然の植物、動物、鉱物が由来としています。例えば、「陳皮(ちんぴ)」は温州みかんの皮ですし、人参、生姜、シナモンなど身近な食べ物も漢方としてたくさん使われています。これらは生薬と呼ばれ、生薬を組み合わせたものが漢方と呼ばれています。
漢方の効果は、冷えている場所や冷えの程度によって実感できる早さが異なります。効果は穏やかに感じると言われますが、自分の体質にぴったり合った漢方を飲んだ場合にはすぐに改善されることもありますよ。
気になる副作用は少ないとされていますが、まれに副作用が出ることもあるので、服用後に胃もたれ、下痢などの胃腸症状やじんましん、発疹などのアレルギー反応があったら服用をストップして漢方薬局などに相談をしましょう。
体を温める食事も体質が悪ければ効果なし?
運動やマッサージ、食事などいろいろ試してみたものの、しばらくするとまた冷えてしまうという人は、根本的な体質改善が必要かもしれません。体質が悪いのは体のエネルギーが偏っていたり、不足していたりする状態と考えられます。
もともとの体質が悪いのならば、良い食事も効果を発揮してはくれませんが、漢方は体質から改善をして冷えをとってくれるのです。
舌で分かる3つの冷えの種類とオススメ漢方
漢方は自分の体質や体調に合ったものでないと十分に効果を発揮しません。その判断は体格、顔色、肌の乾燥などさまざまな要素から行われており、自分でも舌を見ることで簡単にセルフチェックができます。
舌は内蔵の鏡といわれ、消化器の不調、冷えや血めぐりの悪化など、さまざまな情報が隠されているのです。

舌の見方は、飲んだり食べたりする前に、コケなどをとらず舌先から2/3くらいをチェックしましょう。理想的な舌はピンクから淡い赤い色で、楕円形のきれいなラインの状態をしています。
では、舌を3つの冷えタイプに分けてみましょう。
血液や栄養のめぐりの悪いタイプの舌
紫色っぽい舌をしており、舌の一部に紫や茶の斑点があったり、舌の裏側の動脈が蛇行して枝分かれしたりしているのが特徴です。デスクワークが中心で体を動かさない人に多いタイプによく見られます。
しょうが、にんにく、胡椒、唐辛子などのスパイスを取り入れた、血行をよくする食事が効果的でしょう。漢方としては当帰芍薬散、婦宝当帰膠、温経湯、桂枝茯苓丸が用いられます。
体を温めるエネルギーが不足しているタイプの舌
色は淡いピンク~白っぽい色で、舌の縁に歯の跡がついており、舌を出したときに口角からはみ出るほど大きく、弾力がありません。冷え性の自覚があり、寒いのが苦手な人に多いタイプです。
穀類、豆類、温野菜など胃腸の働きを高めて代謝を上げる食事を心がけ、冷たいものや生ものは避けましょう。漢方としては八味地黄丸、十全大補湯、補中益気湯が用いられます。
水分代謝が悪くて冷えるタイプの舌
舌の中央に白いコケがべったりついており、大き目でぶよぶよしていますが、色は正常に近い淡いピンク色をしているのが特徴です。もともと胃腸が丈夫でない人や、冷たいものを取りすぎる人に多いタイプです。
冷たいもののとりすぎに注意が必要ですので、暑い夏でも、常温か温かい飲み物を少しずつ飲むのが良いでしょう。漢方としては苓姜朮甘湯、五苓散、苓桂朮甘湯が用いられます。
漢方は自分に合ったものを取り入れることが重要なので、もし自分に合ったものがわからないときは漢方薬局で相談するのがおすすめです。冷えを改善する生活面でのアドバイスをしてくれることもありますよ。
まとめ
手先が冷たい、寒くて眠れないといった自覚症状のある冷えだけでなく、肩こりや頭痛、生理痛などの不調には冷えが大きく関わっています。
冷えを改善し、体全体を楽にするためにも、食事はとても大事な要素です。軽いストレッチなども取り入れながら、体を温める食事を続けて習慣的に体を温めましょう。なかなか効果を実感できないと思ったら、体質の改善のために漢方の力を借りてみるのもいいかもしれませんよ。
引用書籍:『本当にすごい 冷えとり百科』(オレンジページ)2016年10月出版
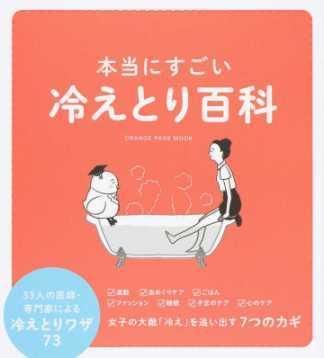
出版社・書籍紹介:『本当にすごい 冷えとり百科』(オレンジページ)2016年10月出版
・Amazon
・楽天ブックス
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事


























