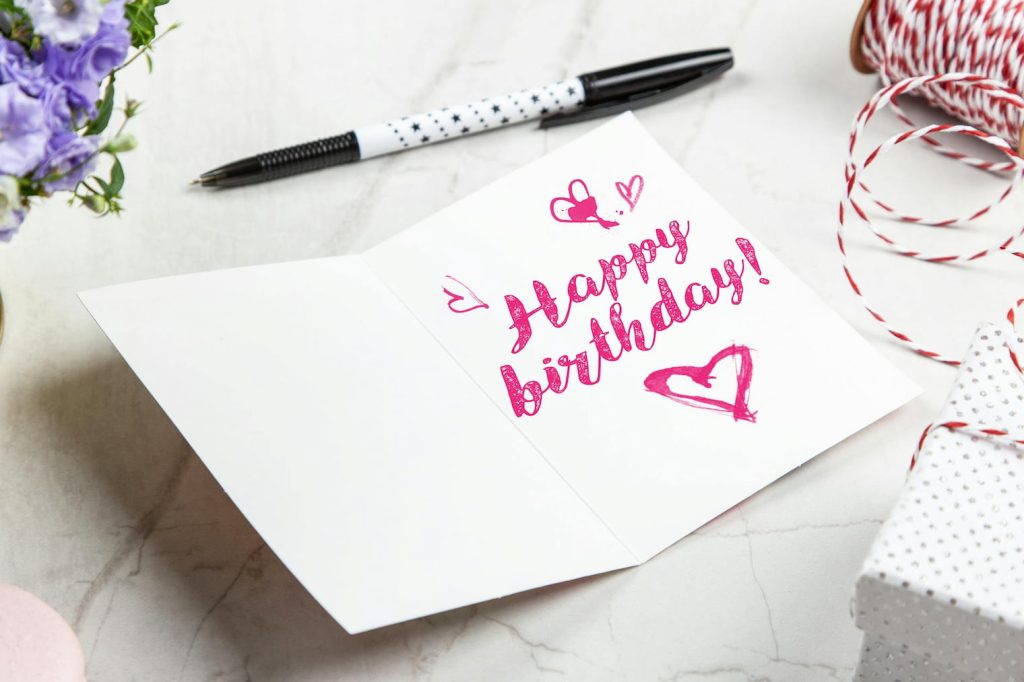年越しそばはいつ食べるのが正解?縁起の良い食べ方・レシピも紹介
この記事では、食べるタイミングや年越しそばの意味について解説します。縁起を担ぐ食べ方やレシピも紹介しますので、ご家庭でぜひトライしてみてください。
年越しそばはいつ食べるのが正解?
年越しそばは、いつ食べるのが正解なのでしょうか。結論からいうと、大晦日の何時に食べるべきといった明確な決まりはありません。昼食や夕食として食べる方もいれば、1月1日になる0時直前、除夜の鐘が鳴ったタイミングで食べる方もいます。
ただし、年越しそばには「1年の悪運や厄を断ち切る」という意味が込められており、それらを翌年に持ち越さないためにも、大晦日のうちに食べ終わるのが良いとされています。
とはいえ、地域によっては元日の朝にそばを食べる習慣があるところもあります。そのため、「必ず大晦日のうちに食べなければ」と神経質になる必要はありません。その土地の習慣や習わし、家庭の都合に合わせて、気楽に食べましょう。
年越しそばの意味・食べる理由
毎年何気なく食べている年越しそばですが、その意味や食べる理由については、深く知らない方も多いのではないでしょうか。ここでは、年越しそばに込められた意味について解説します。
- 厄払い
- そばは切れやすいため、「今年1年間の悪運や厄を断ち切って翌年に持ち越さない」といった厄落としの意味で食べる説が有名です。悪いものと縁を切ってスッキリとした気持ちで新年を迎えたいという願いから、「縁切りそば」の別名もあります。
- 長寿祈願・健康祈願
- そばは細長い形をしていることから、「細く長く生きる」という長寿の願いが込められているともいわれています。また、そばの原料となるそばの実は五臓の毒を取ると信じられてきたことから、健康への縁起づけとして食べる意味合いもあります。
- 家族円満
- 家族との縁が長く続くのを願って食べるという説もあります。引っ越してきた際に近隣に配る引っ越しそばも、「細く長く良いお付き合いができますように」と、人との縁を大切にする思いから贈るケースが多いです。
- 金運上昇
- 昔の金銀細工師は、そば粉で作った団子で散らかった金粉や銀粉を集めたり、金箔を延ばすときにそば粉を用いたりしていました。そこから、そばは金銀を集める縁起物と考えられ、金運上昇の願いを込めてそばを食べる風習が生まれたともいわれています。
- 運気上昇
- 鎌倉時代、博多の承天寺にて貧しい人びとに年越しのための「世直しそば」というそば餅が振舞われていました。それを食べた人は翌年から運が向いてきたといわれ、運気上昇の願いを込めて食べるようになったとされています。
年越しそばの食べ方
年越しそばを食べる時間に決まりがないように、食べ方についても「これが正しい」といったルールはありません。ただし、縁起物として食べる意味合いが強いため、以下の3点に気をつけると良いでしょう。
理由については、以下で解説します。
縁起の良い食材をトッピング【食材一覧】
食べる時間や食べ方と同様に、入れる具材についても明確なルールはありません。家庭や地域にもよりますが、ゲン担ぎとして縁起の良い食材をトッピングする方もいます。
よく使われるのは、以下の具材です。
| 食材名 | 意味 |
|---|---|
| ニシン | 「子宝に恵まれる」:「二親(にしん)」とかけたゲン担ぎの側面があります。 |
| 海老 | 「長寿」:海老のように腰が曲がるまで長生きを、という思いで使用され始めたのが由来です。 |
| 油揚げ | 「商売繁盛」「五穀豊穣」「家内安全」:稲荷神社の守り神であるキツネの大好物であることから、別名「稲荷揚げ」と呼ばれます。金運や仕事運を上げる食材として有名です。 |
| ネギ | 「1年の労を労う(ねぎらう)」という語呂合わせから、縁起の良い食べ物として親しまれています。 |
上記以外にも、「よろこんぶ」の語呂合わせが有名なとろろ昆布、「繁栄」を意味する春菊などの食材もよく使用されています。
途中で噛みきらない
年越しそばは、途中で噛みきらないで食べるのが良いとされています。理由としては、「良縁を切らないために」という説が有力です。また、そばは細長い形をしていることから、1本を噛み切らずに食べると延命や長寿につながるといった意味も込められています。
残さず食べる
年越しそばは、残さず食べることが推奨されています。残してしまうと、「1年の幸運が逃げる」、「金運に恵まれなくなる」といった説があるためです。家族や自分が食べきれる量を準備し、残さずおいしくいただくよう心がけましょう。
各地域で食べられている年越しそば
次に、各地域で食べられている年越しそばを紹介します。
どれも、その地域ならではの特色をいかした個性豊かな仕上がりとなっています。大晦日にこれらの地域に行く予定のある方は、ぜひ食べてみてください。
北海道・京都府:ニシンそば

北海道や京都府では、かけそばにニシンの甘露煮を乗せたニシンそばが人気です。北海道はニシンの名産地であり、江戸時代から身欠きニシンが全国へと運ばれていました。その身欠きニシンを使用した、ニシンそばが明治時代に京都で流行し、現在に至るまで名物となっています。
なお、北海道では濃口醤油、京都府では薄口醤油による味付けが一般的です。
岩手県:わんこそば

岩手県では、わんこそばが人気です。岩手県を代表する郷土料理で、もともとはお殿様をもてなすために作られたという説もあります。小さなお椀に盛られた一口サイズのそばを給仕が次々と追加してくれる形式のユニークなそばで、日本三大そばの一つとしても有名です。
かつては、年齢の数と同じ杯数のわんこそばを食べて長生きを願う「年越しわんこ」の風習もありました。
新潟県:へぎそば

新潟県では、へぎそばが有名です。新潟県魚沼地方が発祥で、布海苔(ふのり)という海藻をつなぎに使用して作られています。
そばには、ツルリとしたのど越しと強いコシがあるのが特徴です。「へぎ」と呼ばれる木を剥いだ板で作られた器を用意し、その上にひと口大に丸めたそばを盛り付けたのが、名前の由来です。
福井県:おろしそば

福井県では、おろしそばが食べられています。越前おろしそばとも呼ばれ、硬めの麺に辛味大根おろしをかけてネギやかつお節と一緒に食べるのが、大きな特徴です。
福井県のおろしそばに用いる麺は硬くて少し黒っぽく、一般的なそばよりも食べ応えがあります。大根おろしによる健康効果や美容効果も期待できます。
島根県:釜揚げそば

島根県では三段重ねの割子(わりご)そばが有名ですが、地元民が食べる年越しそばとしては、釜揚げそばが人気です。
釜や鍋で茹でたそばをゆで汁と一緒にお椀によそい、かつお節やネギ、特産品の十六島海苔(うっぷるいのり)などをトッピングした上から甘辛いつゆを回しかけて食べます。栄養価の高いそば湯と一緒に食べるため、健康食や美容食としてもおすすめです。
年越しそばを楽しむためのポイント
年越しそばを楽しむためのポイントは、次の2点です。
おすすめのレシピも紹介しますので、家庭でぜひトライしてみてください。
トッピングを楽しむ
これまで紹介してきたように、年越しそばには、具材に関する明確なルールはありません。縁起物にこだわらず、さまざまな食材をトッピングして自分好みの味を楽しめるのが醍醐味です。
アレンジしてみる
いつもと同じ年越しそばに飽きてしまった方には、アレンジするのもおすすめです。以下で紹介するレシピを参考に、調理してみてください。
カレーそば:体をあたため満足感を得たい方に

カレーそばは、体をあたためて満足感を得たい方におすすめです。カレー粉とめんつゆを合わせることで、和風だしの効いたコクのある味わいに。とろとろとしたピリ辛のスープがそばによく絡み、食べやすい一品です。
材料(2人分)
- そば:2玉
- 玉ねぎ:1/2個(薄切り)
- 豚こま肉または鶏もも肉:100g
- カレールウ(市販):1〜2かけ(好みで)
- めんつゆ(3倍濃縮):大さじ4
- 水:500mL
- 片栗粉+水(水溶き片栗粉):各大さじ1
- サラダ油:適量
- 青ねぎ、七味唐辛子:お好みで
作り方
- 下準備
玉ねぎを薄切りにし、肉を食べやすい大きさにカットする。そばは茹でておく。 - 具材を炒める
鍋に油を熱し、玉ねぎを炒める。玉ねぎがしんなりしたら肉を加えてさらに炒める。 - だしを作る
水を加えて煮立たせ、アクを取る。めんつゆを加えて味を整える。 - カレーだしを仕上げる
火を弱めてカレールウを溶かし、軽く煮立たせてから水溶き片栗粉を少しずつ加え、とろみをつける。 - 盛り付け
器にそばを盛り付け、カレーだしをかける。青ねぎや七味をふりかけて完成させる。
まぜそば:辛い物好きや濃い味を楽しみたい方に

辛い物好きや濃い味を楽しみたい方には、まぜそばがピッタリです。豆板醤や花椒、辣油などが効いたピリ辛な味わいとにんにくや生姜の香りが、食欲をそそります。卵黄を乗せるのもおすすめです。
材料(2人分)
- そば:2玉
- 豚ひき肉(または鶏ひき肉):160g
- 豆板醤:小さじ1
- めんつゆ(3倍濃縮):大さじ3
- ごま油:小さじ2
- 卵黄:2個
- 刻みねぎ、白ごま、刻み海苔、ラー油(追い辛用):お好みで
作り方
- 肉を炒める
フライパンにごま油を熱し、ひき肉を炒める。火が通ったら豆板醤とめんつゆを加え、水分が飛ぶまで炒めて旨辛肉味噌を作る。 - そばを茹でる
そばを茹でて冷水で締め、水気をよく切る。 - 盛り付け&仕上げ
そばを器に盛り、肉味噌をのせ、卵黄をトッピング。お好みでねぎ・ごま・海苔・ラー油をかけて完成!
サラダそば:野菜と一緒にさっぱり食べたい方に

野菜と一緒にさっぱり食べたい方は、サラダそばを試してみてください。作り方は至ってシンプルで、お正月の準備で忙しい大晦日にもピッタリです。野菜たっぷりでヘルシーなのに満足感もあり、正月太りが気になる年末年始にもおすすめです。
材料(2人分)
- そば:2玉
- お好みの野菜:適量
- めんつゆ(3倍濃縮):大さじ1.5
- 酢:小さじ1
- ごま油:小さじ1
- マヨネーズ:小さじ1(コク出しにおすすめ)
- お好みでラー油:or:わさび:少々(味変に◎)
- ねぎ、ごま:お好みで
作り方
- そばを茹でる
袋の表示どおりに茹でたら、冷水でしっかり洗ってぬめりを取り、水気をよく切る。 - 野菜の準備
野菜は手でちぎったり、包丁でカットしたりして、食べやすいサイズにしておく。 - ドレッシングを作る
めんつゆ、酢、ごま油、マヨネーズ、お好みでラー油を混ぜてドレッシングを作る。 - 盛り付け
器にそばを盛り、野菜を乗せる。食べる直前にドレッシングをまわしかけて完成。
年越しそばに関するよくある疑問
年越しそばについて、ほかにも気になることは多いと思います。ここでは、よくある疑問をお答えします。
Q.大晦日に食べるのを忘れてしまったらどうなる?
大晦日に食べるのを忘れてしまっても、特に問題はありません。年始にそばを食べる風習がある地域も存在しますし、香川県では年越しそばならぬ「年明けうどん」を食べる風習があります。
食べ忘れてしまったからといって落ち込むのではなく、明るく前向きな気持ちで新年を迎えようという心がけが大切です。
Q.年越しで食べるのは他の麺類でも良い?
縁起や意味を重視するなら、そばが適しています。健康意識が高い方には、グルテンフリーの米粉麺や十割そばもおすすめです。
しかし、年越しそばの意義を気にしないのであれば、ラーメンやパスタなど好きなものを食べても大丈夫です。そもそも、そばアレルギーがある方やそばが苦手な方もいますので、家庭の都合や個人の好みに合わせて選択して問題ありません。
まとめ
年越しそばにはさまざまな意味が込められていますが、食べる時間や食べ方、入れる具材などに明確なルールはありません。
年越しそばは、お住まいの地域の習慣や習わし、家庭の事情に合わせて食べられるのが、大きな魅力です。本記事で紹介したアレンジレシピも参考に、大晦日の食卓を楽しんでみませんか。
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事


![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)
![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)