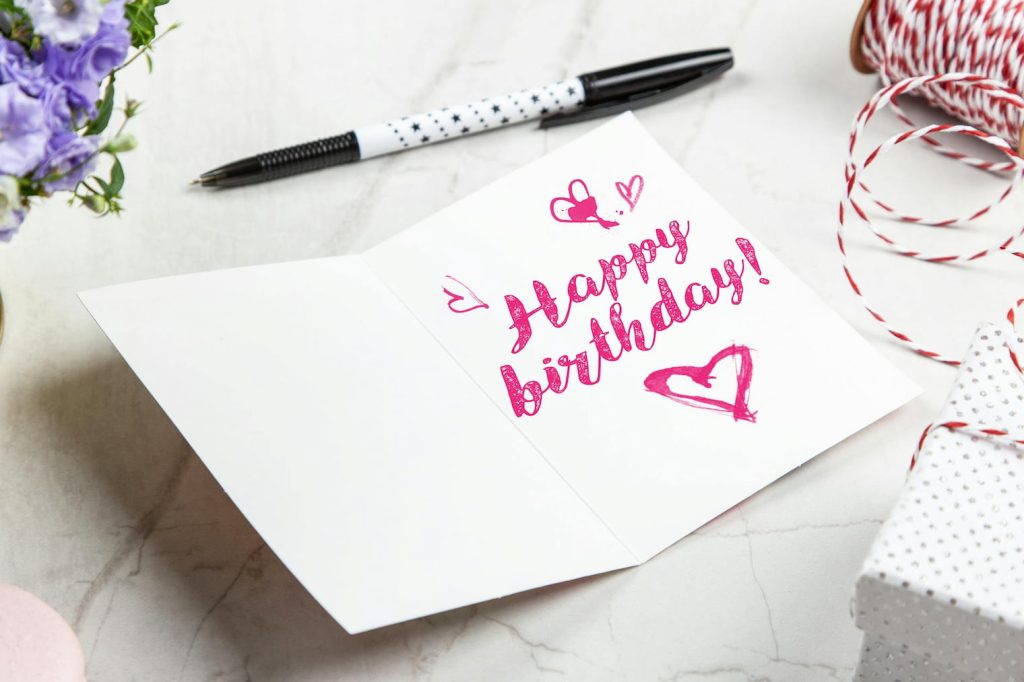時候の挨拶とは?手紙の基本構成や月ごとの挨拶・結びの例文を紹介
ビジネス文書やお礼状で時候の挨拶を添えようとすると、なんとなく堅苦しく感じたり、適切な表現が浮かばなかったりして困ることがあります。
本記事では、時候の挨拶とは何か、どのような場面で使うべきか、そして季節ごとの適切な表現について詳しく解説します。
目次
時候の挨拶とは季節を表す文章
時候の挨拶とは、手紙やビジネス文書において頭語(「拝啓」など)の後に続く、その時々の季節を表現する文章のことです。相手への心遣いを示す言葉であり、コミュニケーションの潤滑油として重要な役割を果たします。
時候の挨拶には大きく分けて二つのタイプがあります。一つは「春暖の候」「新緑の候」「初夏の候」「清秋の候」「師走の候」などの「漢語調」で、もう一つは「桜がきれいに咲き誇る季節となりました」「蒸し暑い日が続いております」といった「口語調」です。
「漢語調」はお礼状や目上の方向けの文書に適しており、格式高く丁寧な印象を与えます。一方、「口語調」はプライベートの親しい友人・知人向けの文書に向いており、やわらかな印象を与えることができます。
ビジネスの場合は必要
ビジネス文書では時候の挨拶が必要ですが、漢語調に限定する必要はありません。むしろ、硬い表現ばかりだと事務的な印象を与えてしまうことがあります。
時候の挨拶は、相手との関係性や文書の内容に応じて、適切な表現を選ぶことが大切です。とくに、長期的な取引関係にある相手や、感謝の気持ちを伝えたい場合には、口語調も交えながら季節感のある時候の挨拶を織り交ぜることで、「心遣いができる人」という好印象を与えることができます。
お詫び・お見舞いの場合は不要
すべての文書に時候の挨拶が必要というわけではありません。例えば、お詫びの手紙では、謝罪の誠意を率直に伝えることが最優先されるため、時候の挨拶は省くのが一般的です。
同様に、お見舞いの手紙でも、相手の体調を気遣うことが最も重要なポイントです。そのため、相手の容態によっては時候の挨拶を省略し、直接的にお見舞いの言葉を述べるほうが適切な場合もあります。
真心のこもったコミュニケーションでは、状況に応じた適切な判断が欠かせません。

挨拶文の構成と注意点
ビジネス文書や丁寧な手紙を書く際には、一定の形式を守ることが大切です。時候の挨拶だけでなく、文書全体の構成や頭語・結語の組み合わせなどにも気を配ることで、より洗練された印象を与えることができます。
ここでは、挨拶文の基本的な構成と、気をつけるべきポイントについて解説します。
挨拶文の基本構成
丁寧な手紙やビジネス文書には、以下のような基本構成があります。この順序に従って文章を組み立てることで、誰が読んでも分かりやすく、礼儀正しい印象を与える文書になります。
| 構成 | 記載する内容 |
|---|---|
| 前文 |
|
| 主文 |
|
| 末文 |
|
| 後付 |
|
頭語と結語は対のものを正しく選ぶ
手紙やビジネス文書において、頭語と結語は対になるものを選ぶことが重要です。手紙の内容や相手との関係性によって、適した頭語・結語の組み合わせは異なります。また、頭語を使用した場合は、必ず対応する結語も使用する必要があります。
以下に、主な頭語と結語の正しい組み合わせを表にまとめました。
| 頭語 | 結語 | 用途・特徴 |
|---|---|---|
| 拝啓 | 敬具/敬白 | 最も一般的な組み合わせ。目上の人や取引先などへの丁寧な文書。 |
| 拝呈 | 敬具/敬白 | 初めての相手や、とくに丁寧さを示したい場合。 |
| 謹啓 | 謹言/謹白 | 非常に丁寧な表現。公的な文書やとくに敬意を表したい場合。 |
| 謹呈 | 謹言/謹白 | 目上の人への贈り物に添える手紙など、とくに格式高い場合。 |
| 前略 | 草々/不一 | 親しい間柄での略式な表現。ビジネスでは取引先の担当者など。 |
| 急啓 | 草々/不一 | 急用を伝える手紙の場合。 |
| 拝復 | 敬具/敬白 | 相手からの手紙に返信する場合。 |
| 再啓 | 敬具/敬白 | 返事が来ないときなど手紙を再信する場合。 |
頭語と結語を使用すると、文書の格式や丁寧さの度合いを適切に表現することができますが、その際は正しい組み合わせで使うことが重要です。例えば、「拝啓」で始めた手紙を「草々」で結ぶのは不適切です。また、頭語があるのに結語が抜けている文書も、形式を理解していないと見なされるおそれがあります。
文書の目的や相手との関係性に応じて、適切な頭語・結語の組み合わせを選ぶようにしましょう。
月別:時候の挨拶・結びの例文を紹介
時候の挨拶は、日本のビジネス文書やフォーマルな手紙において季節感と相手への配慮を示す重要な要素です。ここからは各月に適した時候の挨拶と結びの例文をまとめますので、ぜひ参考にしてください。
1月【睦月】
1月は新年の始まりであると同時に、一年で最も寒さが厳しい時期でもあります。新春の喜びと厳冬の厳しさを織り交ぜた表現が特徴的です。
書き出しの例文
- 新春の候/初春の候/寒冷の候/厳冬の候
- 例年より寒さが身にこたえております
- 新春とは名ばかりの厳しい寒さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか
結びの例文
- 本年も何卒よろしくお願い申し上げます
- 寒さの厳しい折、くれぐれもご自愛ください
- 本年も変わらぬお付き合いのほどをお願い申し上げます
2月【如月】
2月は立春を迎え、暦の上では春になりますが、実際はまだ冬の寒さが続く時期です。梅の花が咲き始め、少しずつ春の兆しを感じられる時節を表現した挨拶が好まれます。
書き出しの例文
- 立春の候/晩冬の候/雪解の候/梅花の候
- 余寒の候、お元気でお過ごしでしょうか
- 春の訪れが待ち遠しいこの頃、皆さまお元気にお過ごしでしょうか
結びの例文
- まだまだ寒い日が続きそうですので、どうぞご自愛ください
- 余寒の厳しき折、無理せずお過ごしください
- 春とは名のみの寒さ厳しいこの時節、皆様お元気でお過ごしください
3月【弥生】
3月は寒さが和らぎ、春の訪れを実感できる時期です。また、年度末で慌ただしい時期でもあるため、相手を思いやる言葉を添えることで心遣いが伝わります。
書き出しの例文
- 早春の候/春分の候/春色の候
- 啓蟄を過ぎ、春の気配を感じる頃となりました
- 春分を過ぎ、桜前線が待ち遠しい頃となりました
結びの例文
- 新年度を迎えご多忙かと存じますが、くれぐれもお体にお気を付けください
- 年度末のお忙しい時期かと思いますが、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます
- 日々暖かくなりますが、油断して風邪などお召しになりませぬようお過ごしください
4月【卯月】
4月は桜が満開となり、新年度が始まる活気に満ちた季節です。春の明るさと新たな門出を祝う言葉が季節感を演出します。
書き出しの例文
- 桜花の候/麗春の候/陽春の候/春日の候
- 春もたけなわの頃となりましたが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか
- 桜の便りが次々聞かれるようになりましたが、皆様お元気でお過ごしでしょうか
結びの例文
- 天候不順の時節柄、どうぞお身体ご自愛ください
- 花冷えの季節ですので、くれぐれもご自愛ください
- 新年度を迎えご多忙かと存じますが、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

5月【皐月】
5月は新緑が鮮やかで、風薫る爽やかな季節です。心地よい季節感を表現しつつも、まだ気温の変化があることを気遣う言葉を添えると丁寧さが増します。
書き出しの例文
- 青葉の候/立夏の候/残春の候/初夏の候
- 新緑が目にしみる季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか
- 風薫るさわやかな五月となりました
結びの例文
- 梅雨のはしりのように気まぐれな空の下、くれぐれもご自愛ください
- 梅雨の始まりも感じられる今日このごろでございますが、くれぐれもお身体にお気を付けください
- 大空を泳ぐ鯉幟に負けず、ますますのご健勝を心よりお祈りいたしております
6月【水無月】
6月は梅雨の季節で、湿度が高く蒸し暑い日々が続きます。雨の多い時期の心情を表現した言葉を添えると季節感が伝わります。
書き出しの例文
- 入梅の候/梅雨の候/初夏の候
- 梅雨寒のこのごろ、お変わりなくお過ごしでしょうか
- 紫陽花が美しく咲き誇る季節、皆様いかがお過ごしでしょうか
結びの例文
- 梅雨明けまで今しばらくの辛抱ですが、気持ちだけはさわやかにお過ごしください
- 梅雨明けが待ち遠しい今日この頃ですが、くれぐれもご自愛ください
- 梅雨寒の中、風邪をお召しにならぬよう、ご自愛ください
7月【文月】
7月は梅雨が明け、本格的な夏の到来を感じる時期です。厳しい暑さを乗り切る健康への気遣いを表現する挨拶が適しています。
書き出しの例文
- 梅雨明けの候/盛夏の候/酷暑の候
- 梅雨が明け、夏本番も迫ってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか
- 梅雨明けの暑さひとしおですが、いかがお過ごしでしょうか
結びの例文
- 暑さ耐えがたきこの頃ですが、くれぐれもご自愛ください
- 暑い日がまだまだ続きますが、お体に気を付けてお過ごしください
- 暑さ厳しき折、ご一同様のますますのご健勝をお祈り申し上げます

8月【葉月】
8月は一年で最も暑さが厳しい時期で、夏休みシーズンでもあります。暑さへの配慮と夏のレジャーに関する表現が特徴的です。
書き出しの例文
- 残暑の候/納涼の候/暮夏の候/晩夏の候
- 残暑が続く毎日ですが、お変わりなくお過ごしでしょうか
- 処暑の候、皆様にはますますご隆盛の段、慶賀の至りに存じます
結びの例文
- 猛暑厳しき折、くれぐれもご自愛ください
- 暑い日々が続きますが、お身体を大切にお過ごしください
- 残りの夏休みを元気にお過ごしください
9月【長月】
9月は残暑から秋へと移り変わる季節の変わり目です。爽やかな秋風を感じ始める一方で、朝晩の寒暖差に注意を促す表現が用いられます。
書き出しの例文
- 初秋の候/秋分の候/秋晴の候/秋冷の候
- すがすがしい秋風を感じる頃となりました
- 9月になってもまだ残暑が厳しいですが、お変わりなくお過ごしでしょうか
結びの例文
- まだ残暑は続きそうですが、くれぐれもご自愛ください
- 秋の兆しを感じる中、くれぐれもお身体にはお気を付けください
- この秋の豊かな実りをお祈り申し上げます
10月【神無月】
10月は秋が深まり、木々が色づき始める美しい季節です。秋の風情を感じさせる表現と同時に、冷え込みへの気遣いを示す言葉が適しています。
書き出しの例文
- 仲秋の候/秋冷の候/紅葉の候
- 秋雨の候、皆様お元気でお過ごしでしょうか
- 実りの秋となりましたが、いかがお過ごしでしょうか
結びの例文
- 朝夕の冷え込みが激しくなりますので、みなさまご自愛ください
- 寒さを感じる季節となりましたが、お体にお気をつけてお過ごしください
- 草木が色づく季節、貴社のご多幸をお祈り申し上げます

11月【霜月】
11月は晩秋から初冬へと季節が移り変わる時期です。紅葉が終わり、冬の気配が徐々に強まる様子を表現した挨拶が季節感を演出します。
書き出しの例文
- 紅葉の候/晩秋の候/初冬の候/氷雨の候
- 落ち葉が風に舞う季節となりましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか
- さざんかが華やぐ時期となりましたが、皆様お元気にお過ごしでしょうか
結びの例文
- 向寒の折柄、くれぐれもご自愛ください
- 寒さに向かう季節となりましたが、どうか体調を崩さないようにお気を付けください
- 忙しい年末を前に、お体に気をつけてお過ごしください
12月【師走】
12月は年末の慌ただしさと厳しい寒さが増す時期です。一年の締めくくりを意識した表現と、新年を迎える準備の忙しさへの気遣いを込めた挨拶が用いられます。
書き出しの例文
- 師走の候/霜寒の候/歳晩の候
- 年の瀬も近く何かと忙しい季節ですが、お変わりございませんでしょうか
- 寒冷のみぎり、お変わりございませんでしょうか
結びの例文
- 本年も大変お世話になりました。来年も貴社のますますのご健勝をお祈りいたしております
- 新雪の季節となり寒さの厳しい折、くれぐれもご自愛ください
- 忙しい年末ですが、体に気をつけてお過ごしください

まとめ
時候の挨拶は、日本の手紙文化において欠かせない要素で、季節感を通じて相手への思いやりを表現します。
デジタル時代だからこそ価値のある、心のこもった手紙の書き方を身につけられる内容です。ビジネスシーンから私的な手紙まで活用できる時候の挨拶を、ぜひ日常に取り入れてみてください。
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事


![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)
![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)