
ときには外注サービスも有効活用を 共働き家庭のお金と暮らしのヒント
ファイナンシャルプランナー・内藤眞弓氏の著書『3000以上の家計を診断した人気FPが教える お金・仕事・家事の不安がなくなる 共働き夫婦 最強の教科書』(東洋経済新報社)をもとに、肩の力を抜いて共働きをするためのコツを紹介します。
目次
共働きをするからといって、無理をする必要はありません。縁があって一緒になったパートナーと協力しながら、未来への一歩を踏み出しましょう。ひとりひとり性格が違えば、働き方や家族観も異なります。下記の項目から実行できそうなものを取り入れつつ、自分流のアレンジを加えて、笑顔で支え合うためのヒントにしましょう。
まずは家計を可視化しよう

家計の管理というと、「無駄遣いをしない」「赤字を出さない」など、目先のやりくりだけにとらわれがちです。しかし、暮らしはずっと続いていくものであり、目先のやりくりだけでなんとかなるものではありません。ライフプランを明確にし、将来を見える化しましょう。
1.将来のライフプランをイメージ
まず、現在の自分とパートナーの手取り収入と、貯蓄総額を書き出しましょう。さらに、年間の手取り収入の合計から年間の貯蓄額を引くと、年間の支出額を算出することができます。何にいくら使ったかはわからなくても、手取り収入と貯蓄した金額がわかれば、1年の暮らし使った支出の総額をつかむことはできるのです。
その上で、自分たちの年齢や、出産などの家族構成の変化を意識しながら、累計貯蓄額がどのように変化するかを予測します。子供が小学生以上になれば、塾通いの費用が必要になるかもしれません。大学受験となれば、貯蓄ができない年があるかもしれません。
一般的には、子供が小学3年生になる頃までと、末子が社会人になってから自分が退職するまでが、人生の数少ない貯め期といわれています。つまり、子供が小さい頃にしっかりと貯蓄をし、教育費から解放されたときにある程度の貯蓄が残っていることが、ライフプランの鍵となるのです。
人生の貯め期と自分たちのキャリアプランを想定しつつ、将来を見通しましょう。
2.支出項目を見える化する
家計を見渡すためには、支出を「シマ」ごとに管理する方法がおすすめです。シマにはいろんなパターンが考えられますが、まずは3つの領域に分けて考えてみましょう。
1つめは「機能」で、水道光熱費や食費は「暮らしのお金」、家賃や住宅ローンは「住まいのお金」のようにまとめます。2つめは「人」で、自分とパートナー、子供と、それぞれの小遣いや服飾費を各人ごとにまとめます。3つめは「行動」で、家族旅行なら「旅行のお金」、帰省なら「帰省のお金」のようにまとめます。
シマとしてまとめることで、「子供にいくらかかった」「帰省にはいくら必要だ」と、通常の家計簿では見えにくいお金の流れが明らかになります。これを月ごとだけではなく1年単位でも把握することで、「毎月のやりくりでは見えなかったけれど、1年では大きな負担となっている」という支出に気づくことができます。
3.パートナーと収支の情報共有
パートナーと支出の情報を共有することも、家計を明確にするためのポイントです。食費や日用品費、家賃、水道光熱費などは、生活口座を開いて二人で管理するのがおすすめです。食材を購入するときなどは、共通の財布を決めておき、生活口座から下ろしたお金を使います。クレジットカードの家族カードの利用も効率的です。
また、自動車税や保険料などの年にいくつかの大きな支出は、事前に洗い出して予算に組み込んでおきます。1年間の特別支出を洗い出して12カ月分で割り、1カ月ごとの予備費として積み立てておきましょう。子供の教育費や老後に向けた貯蓄、不測の自体に備えた貯蓄なども、二人で話し合って決めます。
毎日の家事を洗い出そう

お金を稼ぐためには仕事が大切ですが、暮らしの基盤となる家事が保たれてこそ、仕事がはかどるというものです。家事が得意か不得意かは個人差が大きいので、あまり深く考えずに淡々と分担するのが、時間と心のゆとりを作り出すためのコツです。
1.家事の現状を共有する
毎日の生活の中で、避けることができないものが家事です。まずは現状を把握するために、あらゆる家事の情報を共有しましょう。漏れをなくすためには、平日と休日に分け、行動パターンをたどりながら書き出していくのがおすすめです。加えて、子供の定期健診やエアコンの掃除など、不定期な家事も洗い出していきます。
家事をリスト化したら、誰が担当するかを割り振ります。担当を固定するのか、日替わりや週替わりにするのかなど、実情に合わせて話し合いながら決めましょう。気力や体力、時間には限りがあるので、本当に大事なことに集中できるように優先順位をつけつつ、快適に過ごせるように心がけましょう。
自分が完璧に家事をしていることをアピールしたり、パートナーの家事にダメ出しを連発したりすることは禁物です。
2.賢く電化製品を選んで時短と節約
家事は、なるべくシンプル化することがポイントです。例えば、食器洗い乾燥機(いわゆる食洗機)は、食器を洗う時間を節約でき、その時間を別の家事に振り分けることができます。その上、3人以上の家族の場合は、手で洗うのに比べて水道光熱費が抑えられるという報告があります。
同様に、衣類乾燥機付きの洗濯機であれば、干したり取り込んだりする作業がカットできます。さらに、ロボット掃除機は、床のゴミを吸い取るだけではなく、水拭きや窓拭きができるものもあります。このように、便利な家電を導入すれば、家事の負担が軽減され、ストレスが軽減されます。利用できそうなものから取り入れてみてはいかがでしょうか。
3.外部サービスを上手に利用
家事の手間を省きたいときには、外部サービスを利用するのも一案です。もっとも導入しやすいのは、食材の宅配です。1週間分の食材を選んで注文するものや、調理済みの食事が届くものなど、さまざまなサービスがあります。パートナーのどちらかに食事の負担がかかってしまう場合は、手間を省くために活用を検討しましょう。
さらに、掃除の外注、いわゆるハウスクリーニングの利用もおすすめです。まずは、窓ガラス拭きと水回り(バスルームとキッチン)など、負担が重い場所に絞って利用を検討しましょう。「窓ガラスが汚れている」「換気扇を掃除しなくちゃ」など、気になりながらも手をつけられずに暮らすのは、ストレスが溜まるものです。
日々の掃除で手薄になりやすい部分を外注するのは、有効な選択肢です。日々のストレスが軽減でき、快適に仕事を継続できるのであれば、外部サービスの利用は必要経費と考えることができます。
育児のために準備すべきこと

仕事と子育ての両立には、トラブルに対する備えや、パートナーとの協力が不可欠です。いざというときに慌てないように、日頃から子育てについてパートナーと理解を深めつつ、準備を整えておきましょう。
1.子どもの病気やケガに備える
まずは、信頼できる「かかりつけ医」を持っておくことが望まれます。受診の際には、病気や生活習慣で気になることを箇条書きにしておき、要領よく伝えるのが効率的です。また、気軽に相談できる薬剤師をみつけておくことで、子供でも飲みやすい薬の情報など、さまざまなアドバイスを受けることができます。
さらに、地域で休日診療や夜間診療を行っている病院を確認しておきましょう。病院に連れて行くかの判断に迷った場合は、「こども医療でんわ相談(♯8000)」に電話することで、アドバイスを受けることができます。夫婦ともに仕事が休めない場合に備えて、地域に病児・病後児保育サービスがあるどうかをリサーチしておくこともおすすめします。
2.休日は育児を楽しむ日に

夫婦のどちらか一方が家事や育児をこなす「ワンオペ育児」が話題になることがあります。「子育てを楽しむこと」と「仕事をすること」を対立概念ととらえる人がいますが、育児は夫と妻が取り組むべき重要な課題です。
どちらか一方が仕事で忙しいなら、休日を子供と向き合う時間にしてはいかがでしょうか。夫と妻では、好みや得意なことが違うはずです。子供にとって多様な大人とのかかわりは大切であり、親との信頼関係を築くかけがえのない時間となります。
さらに、仕事で忙しい側は、子供と接することで学びを得ることができ、育児で忙しい側は、自分の時間を取り戻してリフレッシュすることができるのです。このような積み重ねが、夫婦の家事や育児への心理的なハードルを下げ、共働きで仕事を継続するためのモチベーションの維持につながるのです。
まとめ
共働きを始めるためには、自分たちの年齢や家族構成の変化を意識しながら、ライフプランを設計することが大切です。二人の手取り収入と貯蓄総額を明確にしつつ、年間の貯蓄額や支出額を算出し、将来的な累計貯蓄額の変化を予測しましょう。家計を見渡すためには、日頃の支出を管理しながら、パートナーと情報共有をすることも大切です。
さらに、家事や育児の負担がどちらか一方に偏ってしまうと、肉体的にも精神的にもストレスとなり、共働きを続けることが困難となってしまいます。家事は、家電や外部サービスを利用することで、時間を節約することができます。育児は、パートナーと協力し合うことで、心理的なハードルを下げることができます。
ときには、各種サービスを利用することも必要経費と考え、安定した収入を維持することを心がけましょう。
書籍紹介:『3000以上の家計を診断した人気FPが教える お金・仕事・家事の不安がなくなる 共働き夫婦 最強の教科書』(内藤眞弓著/東洋経済新報社)2021年10月出版
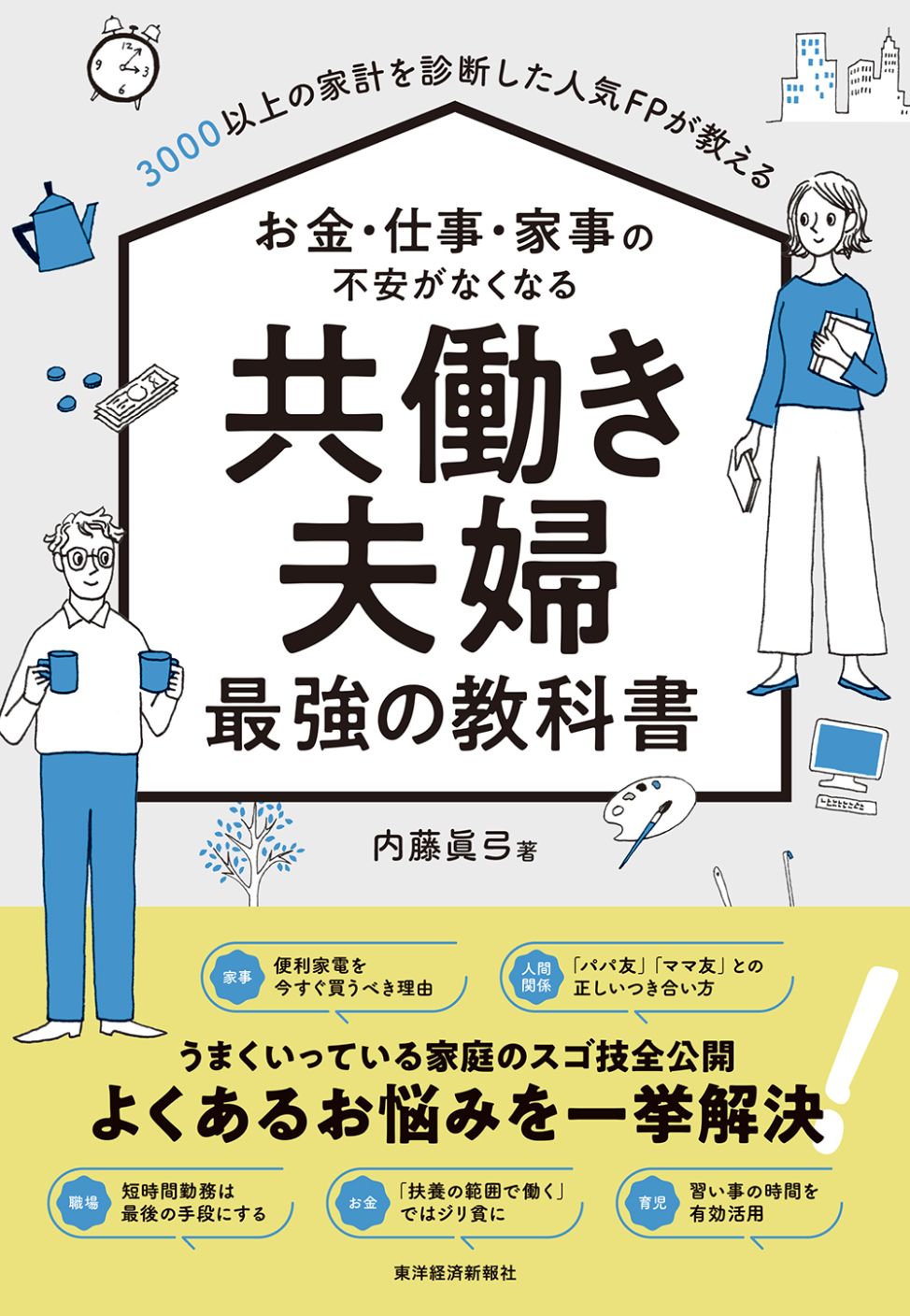
出版社書籍紹介:『3000以上の家計を診断した人気FPが教える お金・仕事・家事の不安がなくなる 共働き夫婦 最強の教科書』(内藤眞弓著/東洋経済新報社)2021年10月出版
・Amazon
・楽天ブックス
・紀伊國屋書店
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事


























