
みんなで取り組むカーボンニュートラル 温室効果ガスを実質ゼロにするために、私たちにできること
でも具体的にどんなことなのか、どんな取り組みなのか、ちゃんと説明することは難しいですよね。そこでカーボンニュートラルについて、具体的な仕組みや取組みについてご紹介します。ご家庭でもできることについて話し合ってみてはどうでしょう。
目次
いまさら聞けない、「カーボンニュートラル」ってどんなこと?
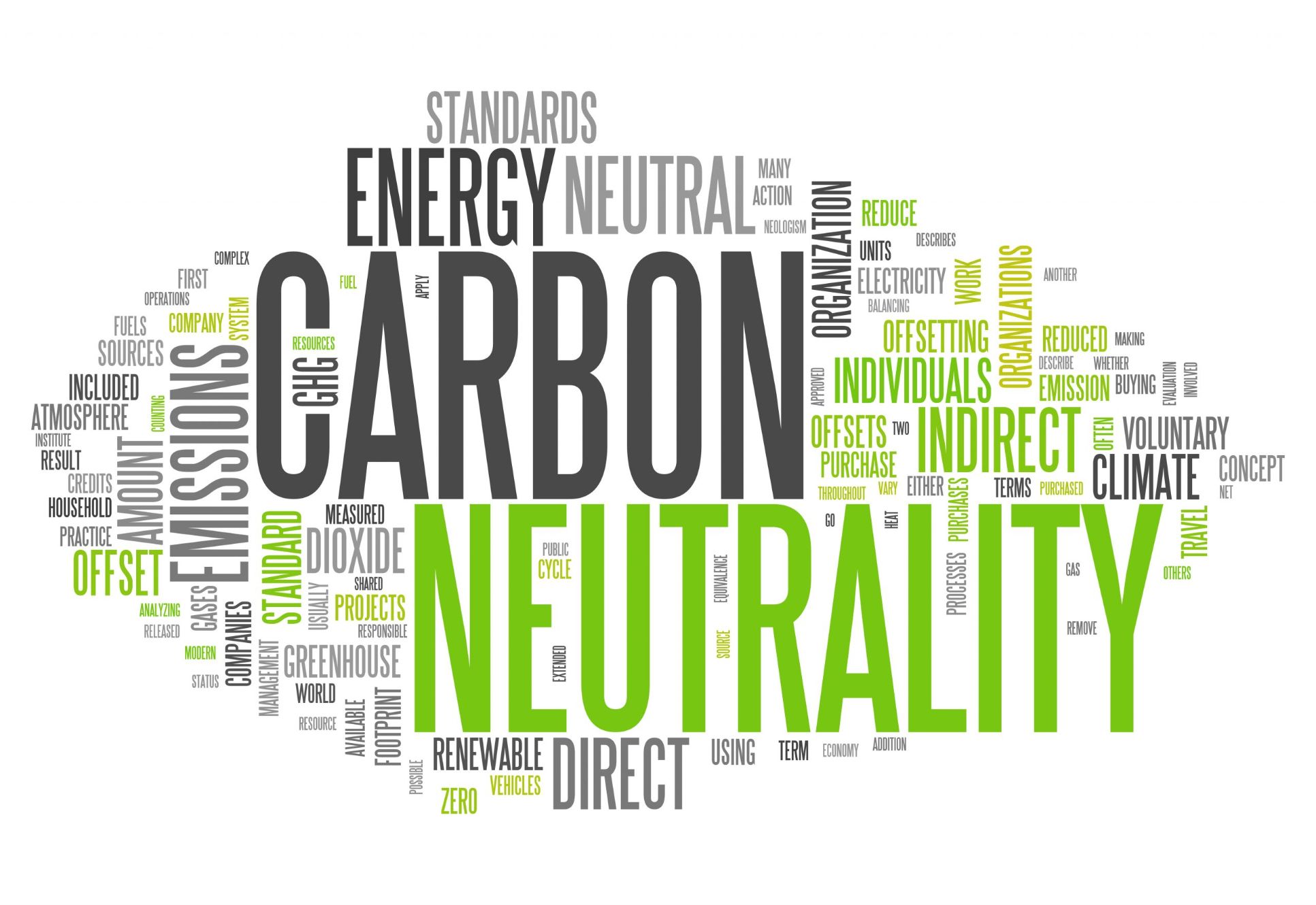
カーボンニュートラルはなぜ、今必要なの?
温室効果ガスとは
そもそも、「温室効果ガスの排出を2050年までに実質ゼロにする」ことにどんな意味があるのか、という点からご紹介しましょう。
温室効果ガスとは二酸化炭素(CO2)だけでなく、メタンや一酸化二窒素、フロンガスなどを含んだ表現です。2019年度の日本の温室効果ガス排出量は12億1100万トンで、2014年度以降、6年連続で減少しています。しかし、「実質」という言葉が示すとおり温室効果ガスの排出をゼロにすることは非常に難しいと言われています。
そこで植林や森林管理などで温室効果ガスの吸収量を増やし、排出量と差し引いて「実質ゼロ」を目指しているのです。「ニュートラル(中立)」という言葉が入っているのはそのためです。
参考:
国立環境研究所 日本の温室効果ガス排出量データ(1990~2020年度)速報値
経済産業省 資源エネルギー庁 「カーボンニュートラル」って何ですか?(前編)~いつ、誰が実現するの?「「カーボンニュートラル」って何?」

なぜ今なのか
現在は地球温暖化が進んでいますが、その原因となっているのが温室効果ガスです。
既に2017年時点で、世界の平均気温は産業革命以前と比べて約1℃上昇したといわれています。このままの状態が続くとさらなる世界の気温上昇が考えられ、北極海の海氷が溶け出すことによる海面水位の上昇、水害や干ばつ、ハリケーンの増加、気温上昇による感染症の拡大などの恐れが指摘されています。
2020年以降の気象変動問題に関する国際的な枠組みとして、2015年に合意された「パリ協定」では、世界共通の長期目標が決まりました。
- 世界の気温上昇を、産業革命以前に比べて2℃より低く保ち、1.5℃以下に抑える
- そのために21世紀後半には、温室効果ガスの排出量と森林などによる吸収量のバランスをとる
という2点です。これ以上の世界の平均気温上昇を避けるために掲げている方針が、「2050年までのカーボンニュートラル」なのです。
参考:
経済産業省 資源エネルギー庁 「カーボンニュートラル」って何ですか?(前編)~いつ、誰が実現するの?「いつまでに、カーボンニュートラルが必要?」
環境省 脱炭素ポータル 気候危機を回避するため、いまから取り組む必要があります カーボンニュートラルとは
環境省 脱炭素ポータル なぜカーボンニュートラルを目指すのか
カーボンニュートラル実現を目指す国と、世界の現状
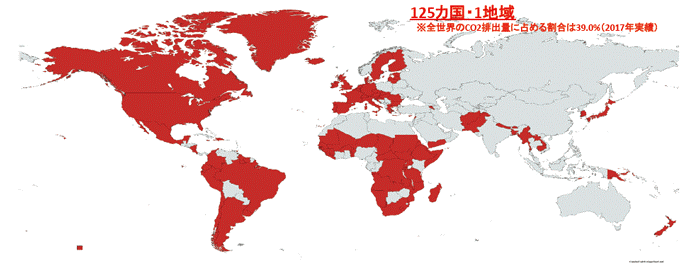
出典:経済産業省 資源エネルギー庁 【第122-1-1】2050年までのカーボンニュートラルを表明した国
2021年4月時点で、日本を含めた世界の125か国と1地域が、2050年までのカーボンニュートラルを実現すると表明しています。全世界のCO2排出量に対し、2050年までのカーボンニュートラルを表明した国々の排出量が占める割合は37.7%です。
また、世界最大の排出国である中国は、2020年9月の国連総会で2060年までにカーボンニュートラルを実現する、と表明しました。世界の排出量に対して中国の排出量が占める割合は28.2%にのぼります。
従って、全世界の排出量の約3分の2を占める国や地域が、カーボンニュートラルに取り組んでいるということになります。
参考:
経済産業省 資源エネルギー庁 第2節 諸外国における脱炭素化の動向
環境省 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて
環境省 地方公共団体における2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況
カーボンニュートラルを実現するために必要なこと

2050年という目標へ向けた対策
日本はカーボンニュートラルを2050年までに達成する、という方針を掲げましたが、大きな努力が求められる課題です。必要な対策は大きく分けて5つあります。
1.省エネルギーとエネルギー効率の向上
CO2の排出量を減らすためには、やはりまずエネルギー消費量を減らすこと、省エネが有効です。節電するだけでなく、エネルギー効率が高い製品を作って使用することでエネルギー消費を抑えなければなりません。
2.CO2排出単位の低減
省エネだけでなく、電力部門では発電時のCO2の排出を抑えることが重要です。非電力部門では、自動車などからのCO2の排出を抑える方法の検討が必要とされています。
3.非電力部門の電化
非電力部門、例えばトラックなどの運輸部門ではガソリンなど化石燃料を使用していますが、CO2を排出しないために電化の推進が検討されています。
4.ネガティブエミッション
いろいろな取り組みをしても脱炭素化できない部門や、どうしても出るCO2があります。セメントの生産や廃棄物を焼却する時に出るCO2です。
5.CO2の排出をゼロに
以上4点の対策を組み合わせて、トータルで脱炭素、CO2の排出を減らす、という取り組みが重要になります。
参考:
経済産業省 資源エネルギー庁 「カーボンニュートラル」って何ですか?(後編)~なぜ日本は実現を目指しているの?
国だけでなく企業も取り組み始めています

脱炭素事業は国だけで進められません。新しい技術を開発してよりCO2排出を抑えるため、さまざまな企業が取り組んでいます。その一例をご紹介します。
ペットボトルリサイクル
食品トレイやペットボトルは廃棄処理をする際、温室効果ガスが出るという問題がありました。
回収されたペットボトルは主として中国へ輸出されていましたが、2017年の輸入規制で余り始めていました。そこで環境省の支援で企業がプラスチックの資源循環に取り組み始めています。
ファッション産業
服は製造にかかるエネルギー使用量が高いわりに、あまり長く使用されません。環境負荷が高いとして国際的な課題になっています。
そこで1着の服と長くつきあい、不要になった服を回収し、リペアやリユース、リサイクルを行うことでより長く活躍できるよう、企業もサステナブルに参加しています。
環境省も地球温暖化対策に関する補助・委託事業をWEBサイトで紹介していて、電化や発電、リサイクル事業や設備開発などでの企業の応募を募っています。
参考:
環境省 脱炭素ポータル 「企業の皆さまができること」「企業の方へ」
2050年までに、CO2排出を実質ゼロにするために

脱炭素といっても、どうやってどのぐらい減らすの?
「CO2の排出量を減らす」と一口に言っても、具体的にはどうするのでしょうか。
当時の菅総理大臣は、温室効果ガスの削減量について「2030年度に、2013年度の排出量から46パーセント削減することを目指す」と発表しています。2022年の時点で、日本が排出しているエネルギー起源のCO2は約10億3,700万トンあります。このうち電気・熱配分後排出量(※)の家庭が占める割合は約15.3%で、約1.58億トンです。この数字は、一人ひとりの行動で変えていけるのではないでしょうか。
一般家庭で消費している電力の内訳で考えると、照明や家電商品の使用が約31%にのぼり、次いで自動車の使用が約25%、暖房・冷房の使用が合わせて約19%、給湯機器の使用が約14%と続きます。家庭では省エネと節電に取り組むことが大切です。
不要な照明はこまめにスイッチを切るように心がけ、家電商品は省エネ性能が高い商品を利用しましょう。冷暖房は健康を守るために不可欠ですが、適切な室温に設定してクールビズやウォームビズを心がけましょう。同様に、給湯器も高すぎる温度設定は避けることがおすすめです。
また、カーボンニュートラルの観点では、自動車よりもなるべく徒歩や自転車を使った移動がおすすめです。公共交通機関を使うことも、家庭からのCO2排出を抑えるためには有効です。自動車での移動が必要な場合、駐車中や長時間停車する際はエンジンを切りましょう。
※電気・熱配分後排出量:発電や熱の生産に伴う排出量を、電力や熱の消費量に応じて各部門に配分した後の値。
参考:
JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センター:日本の部門別二酸化炭素排出量(2022年度)
経済産業省 資源エネルギー庁 「カーボンニュートラル」って何ですか?(後編)~なぜ日本は実現を目指しているの?
カーボンニュートラルのための技術開発も進んでいます

現在、カーボンニュートラルのために日本ではさまざまな技術開発が行われています。
例えば、エネルギー関連産業で注目されているのが、洋上風力発電産業です。日本は特許出願数が多く、世界でも技術力が評価されています。
もちろん洋上風力発電は再生可能エネルギーで、カーボンニュートラルにも適しています。現在はヨーロッパを中心とする海外での導入が先行していますが、今後は島国で海に囲まれた日本でも導入が増えることが期待されています。
また、今後重要となる自動車・蓄電池産業でも、日本の技術力の高さは評価されています。
カーボンニュートラルを目指すためには、現在のガソリン車やディーゼル車などを電気自動車(EV)や燃料電池自動車等に切り替えることが推進されています。
まだ普及が進んでいませんが、国内の電気自動車の販売量は徐々に増加しています。以前は走行距離が短いとか、EV車が高額という問題がありましたが、2017年に発売された新型のEV車は1回の充電で約400km走行できるなど、性能が高いことで評判になりました。価格も手に入りやすくなりつつあります。今後、性能面でもコスト面でもより優れたEV車が開発されることが期待されています。
蓄電池は名前のとおり、充電して繰り返し使える電池です。身近なところではスマートフォンやノートパソコンなどのバッテリーが代表的な商品です。しかし今後は、住宅用の太陽光発電で発電した電力を蓄電池に蓄えて自宅で使ったり、電力使用が多い時間帯や災害時に蓄電池に蓄えた電気を使用するなど、蓄電池が活用される場面が増えると思われ、技術開発の進歩が望まれています。
その他には、家庭に直結する産業として住宅産業があります。家庭のエネルギー消費で少なくない割合を占める冷暖房ですが、この消費を抑えることでカーボンニュートラルに貢献できます。
そのためには冬に熱を逃がさない「断熱」で暖房費を、夏に熱を遮断する「遮熱」で冷房費を抑えることが大切です。そんな省エネ住宅として、ZEH(ゼッチ)(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の実現と普及に向けた取り組みが進められています。
参考:
経済産業省 資源エネルギー庁 「知財」で見る、世界の脱炭素技術(前編)
カーボンニュートラルに向けた産業政策“グリーン成長戦略”とは?
国土交通省 洋上風力産業ビジョン(第1次)(案)概要 3ページ【参考】洋上風力発電導入の意義
経済産業省 資源エネルギー庁 電気自動車(EV)は次世代のエネルギー構造を変える?!
知っておきたいエネルギーの基礎用語 ~「蓄電池」は次世代エネルギーシステムの鍵
省エネポータルサイト 家庭向け省エネ関連情報 省エネ住宅
私たちが日常生活でできる取り組みがあります

家電製品の買い換えも温暖化対策になる
家庭の中で電力消費量が多い家電のランキングで、1位に冷蔵庫、4位にエアコンが入っており、買い換えの際には省エネ性能が優れている商品を選ぶのがおすすめです。
現在家電商品には「統一省エネラベル」といって、省エネ基準達成率を星の数で評価されたラベルがついています。中でも省エネ性能が高い5つ星製品を選びましょう。
参考:
環境省 地球温暖化対策のための国民運動 「COOL CHOICE」 省エネ家電に買換えよう!
電球をLEDに交換して電気代も節約できる
家庭の中で電力消費量が多い家電の2位が照明器具です。
最新型の家電に買い換えることで得られる省エネ効果は、一般電球をほぼ同じ明るさの電球型LEDランプに交換することがもっとも高いとされています。
家で使っている照明器具を一度に全部交換は難しいかもしれませんが、少しずつ換えていくことで電気代も節約でき、ひいては温暖化対策にもなります。
参考:
環境省 地球温暖化対策のための国民運動 「COOL CHOICE」 省エネ家電に買換えよう!
ウォームビズとクールビズ
環境省が推奨する室内温度は、冬は20℃、夏は28℃です。
冬は機能性素材を使った上着や下着などを活用し、太い血管のある首や手首、足首の「3つの首」の熱を逃がさないことで体全体をあたため、暖房を効率的に使いましょう。
家の中の暖気を外に逃がさないことも大切です。家全体の熱の約50%は窓から流出するといわれているので、二重サッシや複層ガラスに換えるか、難しければ断熱シートを貼ったり厚手のカーテンに付け替えたりして熱を逃がさない工夫をしましょう。
夏はエアコンの設定温度を下げすぎないようにし、暑いと感じる場合には電力消費量の少ない扇風機を併用するのも良い工夫になります。また、サーキュレーターで冷えた空気を室内に循環させれば、冷房効率を上げられます。
外出する際はカーテンを閉めて室温の上昇を防ぐ、ブラインドや遮熱シートを使って室内に熱がこもらないようにするなどの工夫をしましょう。うちわなどで体感温度を下げたり、冷却ジェルシートや氷のうを活用したりするのもおすすめです。
夏冬どちらでもできる取組みとしては、家族が一つの部屋に集まって団らんすることで、余分な暖房や冷房を節約することができます。意識して取り組んでみてはいかがでしょうか。
参考:
環境省 令和3年度 ウォームビズについて
ウォームビズ(WARMBIZ)とは
環境省 地球温暖化対策のための国民運動 「COOL CHOICE」CoolBIZ 家庭編
宅配便はなるべく一度で受け取ろう
コロナ禍もあって近年通信販売の業績が大きく伸び、宅配便の取扱個数も急増しています。しかし全体の約2割が再配達になっているということはご存知でしょうか。
配送はトラックなど自動車で行われている場合がほとんどで、排出されるCO2も減らさなければなりません。荷物の再配達は配送ドライバーだけでなく、地球環境にとっても負荷になります。
自分で注文した商品がいつ配達されるかを把握して、置き配や宅配ボックスの活用、最寄りのコンビニでの受け取りなど、できることに取り組みましょう。
参考:
環境省 地球温暖化対策のための国民運動 「COOL CHOICE」 できるだけ1回で受け取りませんかキャンペーン
国土交通省 宅配便の再配達削減に向けて
使い捨てはやめて、「3つのR」でエコな暮らし
ごみを減らすことは、私たちができる身近で大切な取り組みのひとつです。
ごみになるものは受け取らず、ものを使い捨てするのはやめて、使えるものはリサイクルするという働きかけが、自治体主導で社会的にも進んでいます。経済産業省など関係7省が後援し、環境対策と経済が両立した循環社会を目指す「3R政策」という取り組みです。
3Rとは、製品を作る時に使う資源の量や廃棄物の発生を少なくするReduce(リデュース)、使用済製品や部品等を繰り返し使用するReuse(リユース)、廃棄物等を材料やエネルギー源として利用するRecycle(リサイクル)の頭文字、3つのRを総称したものです。
リデュースの観点で言えば、レジ袋はもらわずマイバッグを持参し、使い捨てをせず耐久性の高い商品を長く愛用することで、ごみになるものを減らせます。
リユースの面では、商品を消費した後のビンやカップ等の容器を販売店が回収し、商品に再利用するリターナブル容器を使った商品を選ぶことが、廃棄物の削減につながります。
リサイクルでは資源ごみの分別回収に協力し、リサイクル用品を積極的に使用しましょう。
ごみを減らし、使えるものを繰り返し使い、資源を再利用する循環型社会を目指すため、ご家庭でもできることにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
参考:
リデュース・リユース・リサイクル推進協議会 3Rとは
経済産業省 3R政策
▼まとめ:私たちが住む地球の環境を守るため、できることを実践していきましょう

難しい話がたくさん出てきましたが、カーボンニュートラルは国や企業でなければ取り組めないわけではありません。
CO2を排出しないような暮らし方を選び、EVなどのエコカーへの乗り換えや、公共交通機関を利用することでも貢献できます。日常生活では電球をLEDに変えたり、節電に取り組んだりすることもでも貢献できます。焼却する時のCO2の排出を考え、普段からゴミを減らしてリサイクルを意識することでもカーボンニュートラルにつながります。
ちょっとした設備や生活の見直しが、温室効果ガスの抑制につながります。ぜひ一度、ご家族で検討してみてはいかがでしょうか。
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事


























