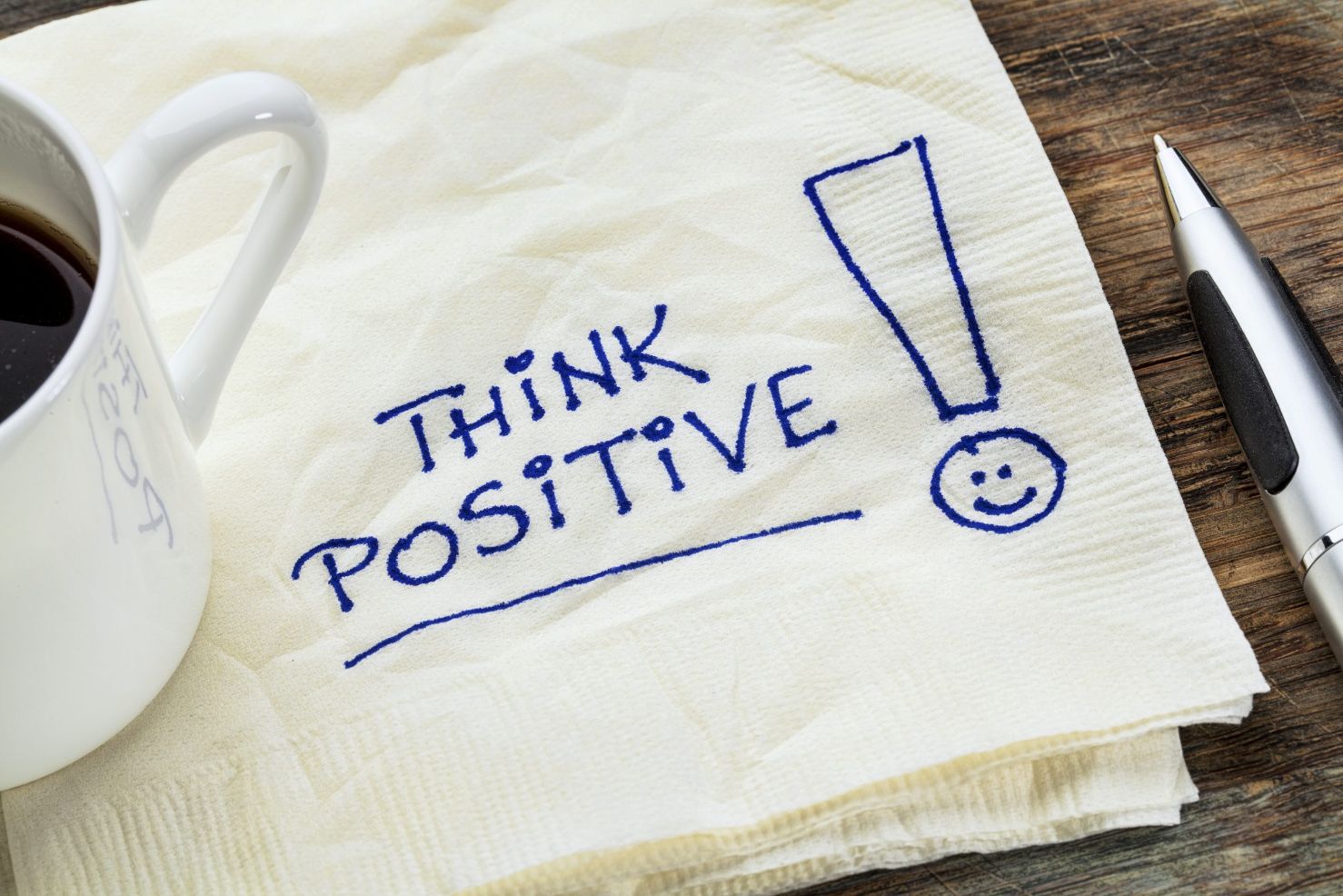
言い方ひとつで印象が変わる!いい人間関係を作るための「ポジティブな言葉」
ここでは心理カウンセラーの植西 聰氏の著書『人間関係で「疲れない心」に変わる言いかえのコツ』(講談社)と共に、いい人間関係を築くポイントを学んでいきましょう。
社交・挨拶の言葉
あなたは人に久しぶりに会ったときや、エレベーターで乗り合わせたときに何を口にしたか覚えているでしょうか。何気ない挨拶や、別れ際にかけた言葉ひとつで、相手が受け取る印象は大きく違ってきます。意味は同じでも、ものの言い方によって相手の印象や反応はガラリと変わってくるのです。ここでは、そのちょっとした一言のポイントをご紹介します。

挨拶ひとつで印象が決まる
挨拶ひとつで「この人はデキる」「つきあいにくそう」といった印象をあたえてしまうことがあります。しかも、挨拶や社交の言葉は短く、いわば瞬間芸のような印象づけが必要です。
本当に、「挨拶ひとつもおろそかにできない」のです。
例えば、長く会っていなかった友人には「おひさしぶり」とだけ挨拶するのではなく、「元気そうでうれしい」と喜びの言葉を加えるほうが、より相手にいい印象が伝わるでしょう。
また、ネガティブな表現を避けるのもポイントです。挨拶のお決まりの話題として「その日の天気の話」があります。天気が悪い日であっても「朝から、うっとうしい雨ですね」などと、ネガティブな言葉を見直してみて、「空気がしっとりとしていいですね」「久々に恵みの雨ですね」などとポジティブに言いかえます。そうすれば、あなたも相手も前向きな気持ちになれるはずです。
別れ際も気を抜かない
別れは「もう二度と会えない」という気持ちで笑顔と言葉を投げかけましょう。別れぎわの印象がいいと、そのいい印象が、その後も長く持続します。
いい印象のコツは「また近々」と再会の希望を匂わせるのではなく、「お目にかかれるのを心待ちにしています」と強く気持ちを伝える言葉を添えると良いでしょう。
感謝するときの言葉
「ありがとうございます」は感謝の気持ちを伝える言葉ですが、いつも通り一遍の感謝ですませていると相手に感謝の心が伝わらないかもしれません。「この人は本当に感謝している」と感じてもらうためにはどのような言い方をすればよいか、次の項目でご紹介していきます。

感謝は人を引き寄せる
感謝は「本当に助かりました」ときちんと伝えましょう。「あ。どうもすみません」と照れた様に素っ気ない言い方では逆効果です。相手に頭を下げるようで嫌だという人もいますが、感謝の言葉を口にすると心の中で幸福度が増していきます。感謝の言葉をたくさん口にすることは重要なのです。
また、褒められたときに「まだまだです」と、とっさに謙遜してしまうことはありませんか?そんなときは「おかげさまで」と言いかえてみましょう。言われた同僚、お客様、上司は自分のバックアップが活かされたと実感して、感謝された印象が強くなるはずです。そして、さらに応援したくなり、人が集まってくるようになるのです。
断られても感謝を口に出そう
相手に断られて嬉しいという人はあまりいないですよね。「それぐらいしてくれてもよさそうだけど」と不満をもらすのではなく、「話を聞いてくれて、ありがとう」と感謝の言葉を伝えましょう。その後の人間関係も穏やかですし、自分自身もポジティブになれるはずです。
不満があるときにも感謝を口にするには心の習慣を身につける必要があります。その心の習慣とは「相手への要求水準を下げるようにすること」です。
要求水準を下げると「もう少しやって欲しかったなぁ」が「ここまでやってくれて、ありがとう」に変わります。そうすれば、相手は「次も手伝おう」と思ってくれるのではないでしょうか。ほどほどのところで満足することが大切なのです。
謝る・許すときの言葉
謝ることや謝罪を受け入れる場は、明るい雰囲気ではないですよね。相手は怒っていたり、腹を立てていたりすることも多いでしょう。そんな悪い雰囲気からプラスの感情を作る方法を見ていきましょう。

謝ることは信頼を生む
謝るときには弁解がましいことは言わず、「私の力不足で」と謙虚に頭を下げましょう。弁解があると「ふだんはこんな失敗はしない」と伝えたいだけなのかと悪印象になってしまいます。
「言い訳はしません」といさぎよさを前面にして謝ると印象は良さそうですが、必ずしもそうではありません。実際には説明しなければならないこともあるからです。特に、まだ仕事が続く場合には「では、どうするか」を前向きに話し合わなければなりませんよね。そこで、しっかりと謝罪をして説明をすることで信頼が生まれてくるのです。
相手にプラスの感情を与える許し方とは
相手が謝ってきたときには「自分もやりかねない」という心構えを忘れてはいけません。謝りにくる相手は、後ろめたさなどネガティブな感情でやってきます。
例えば、遅刻などで遅れてきた相手には「待っていた」とは言わず「本読んでいた」と笑顔で言ってあげましょう。許せないほど大きな迷惑を掛けられたときでも「気にしなくていいよ」と許してあげるのです。
このように寛大な心で許されたほうが、相手は二度と迷惑をかけられないと反省をしますし、イヤな気持ちを引きずることがありません。何より自分自身が、怒りという感情に振り回されて苦しまずにすむのです。
お願いするときの言葉
人になにかをお願いするということは意外と難しいもので、気が引ける、断られたら嫌だなと思う人は多いのではないでしょうか。能力のある人ほど忙しそうで、とても頼み事ができる雰囲気ではない…と尻込みしてしまうこともありますよね。ですが、次に紹介する「頼み方のコツ」を知ることでそんなストレスを減らすことができるのです。

「何かしてあげたい」を上手に引き出す
人間には誰かのために何かをしてあげたいという感情があります。どれだけ自分が大変な状態かを説明するよりも「やっていただけるとうれしいです」「引き受けてもらえれば、とても助かる」と先に感謝をして感情に訴えると、「何かをしてあげたい」という意識を上手に引き出すことができます。
主語を「私」にするのも効果的です。「あなたは私を手伝ってくださいよ」ではなく、「手伝ってくれたら私はうれしい」と頼むほうが、相手は抵抗なくやる気になってくれるものです。主語は言葉に発さなくても良いですが、意識するように心がけましょう。
自分の事情を押し付けない
自分の都合を言うと「こっちも忙しいのに」と断られてしまいます。人は「自分の意思で行動したい」という心理があるので、「こうして」と圧力をかけられるのは好まないからです。
一方で、断わるというのは相手に精神的な負担をかけてしまいます。もし断られたら「お忘れください」と明るい笑顔で言いましょう。頼むときには断ってくれてもかまわないという心構えが大事なのです。
断わるときの言葉
何かを頼まれたときにノーというのは大変ですが、全てを引き受けてしまっては疲れ切ってしまいます。いい人間関係を保ちながら上手にノーというにはどうすればよいでしょうか。
ありがとうは断わるときにも使える
「申し訳ない。ダメなんだ」と謝罪と断わる言葉を組み合わせることが多いのではないでしょうか。より印象をよくするには「ありがとう、でもダメなんだ」と先に感謝をしてから謝る方法があります。「サンクス・バット」と呼ばれる話法で、お客様からのお問合せ対応でもよく用いられています。
外的な理由だと断りやすい
頼まれたり誘われたりした時には「物理的に」「予算的に」「時間的に」など、外的な理由で断りましょう。
例えば「私には難しいようです」「気乗りしないので」という言い方は内的な理由で、相手が受取る印象も悪くなります。
相手を助けながら断わろう
「これってどうやるのか知っていますか?」と聞かれて、分からなった時には相手が次のステップへ進む手助けをするのがポイントです。「私にはよくわからないけど、〇〇さんは詳しいから、聞いてみたら?」と橋渡しをして、わからないで話を終わらせないようにしましょう。
引き受けるときの言葉
相手からの依頼や誘いを引き受ける時、「できる」イコール「引き受ける」と考える必要はありません。引き受ける側の有利な立場は、時として相手との関係を悪くしてしまうこともあるため、断るとき以上に慎重にイエスという事が賢明です。
次項では、依頼を引き受けるときに気を付けたいポイントと心構えをご紹介します。

謙虚さを心がけよう
「忙しいけど大丈夫ですよ」と恩に着せたり、「面倒だけど」とつい口走ったりしてしまいますが、口にしないほうが懸命です。この人に頼むんじゃなかったと思われて、今後のチャンスを失うことになってしまいます。
逆に「あなたに頼まれて、うれしいくらいだよ」と感謝を込めた前向きな言い方をすると、相手のプライドをくすぐります。この人に頼んでよかったと相手に思わせるのが重要です。
褒めたり励ましたりするときの言葉
褒めたのに相手の機嫌を損ねてしまった、励ましたつもりなのにさらに落ち込ませてしまった、というような経験はありませんか?よくある失敗談ですが、相手に応じて言葉を選べば防ぐことができます。

外見より内面を具体的に褒める
同僚の自宅に招かれたときには「素敵なお家ですね」と褒めることは多いのではないでしょうか。ですが、外見的な面ばかりだとお世辞だろうと感じられてしまうかもしれません。
人間は教養や知性といった内面的なものを褒められたほうが、自尊心を満たされてよりうれしく感じる傾向があります。例えば本棚があり歴史書、哲学書があれば「教養あふれる本棚ですね」と内面に着目するのが気のきいた褒め方です。
褒めるときには具体的に褒めてあげるのも大切です。具体例がないと感情がこもらず、相手の心に響きません。おだてているだけだろう、実はイヤミなのではと疑われて相手の心が冷めてしまうこともあります。
例えば、「さすがです」というだけではなく「短期間でこれだけの企画書を作るなんて、さすがです」といった具合に、相手のどこが素晴らしいのかを伝えるようにしましょう。
落ち込んでいる人には寄り添う言葉をかける
よく使われる「がんばってね」は好調で元気いっぱいの人を励ますには最適です。ですが、すでに一生懸命に努力しているのに上手く行ってない人からすれば「これ以上がんばるなんて無理だ」という気持ちになってしまいます。
こういった場合では「一緒に考えてみよう」と協力する言い方をして相手を安心させましょう。安心すれば気を取り直すことができます。
自尊心を取り戻させるコツ
失敗をしてしまった人には「あなたらしくないね」と励ましてあげると効果的です。あなたらしくないねという言葉は「あなたは本当ならもっとできるはずだ」という意味が込められているからです。
逆に「あなたらしいね」はイヤミとして伝わってしまう難しい言い方ですので、使わないほうが懸命かもしれません。
褒める励ますは自分も元気にする
人を褒めたり励ましたりすることは大切だと分かっていても、なかなか出来ないことでもありますよね。仕事や人間関係の疲労やストレス、時間に追われているとネガティブな言葉が増えてしまいます。
そんなゆとりのない精神状態になっているときほど、意識して褒めたり励ましたりしましょう。人を褒めることでストレスがやわらぎ、心に余裕が生まれることがあります。人を励ますことで身近にいる人が元気になり、その元気を貰って自分を回復させることもできるからです。
まとめ
言い方ひとつで相手から好かれ、自分の味方になってくれたり、反対に相手から反感を買ってしまい、やりづらくなってしまうこともあります。同じ内容のことを言っているのに、自分の言い方ひとつで相手の印象や反応はガラリと変わってしまうのです。
ネガティブな言葉をポジティブな言葉に変えるためには練習が必要であり、すぐには言葉が出てこないかもしれません。ですが、そのポジティブな言葉は、よい人間関係を育てます。周囲の人の成長や幸福はあなた自身を幸福にしてくれるでしょう。
引用書籍:『人間関係で「疲れない心」に変わる 言いかえのコツ』(植西 聰 著/講談社)2021年10月出版
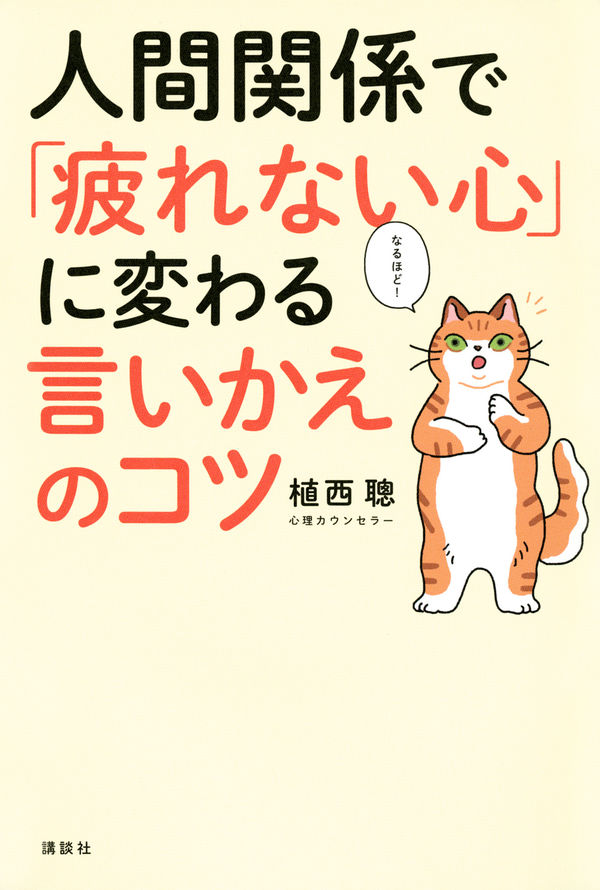
出版社・書籍紹介:『人間関係で「疲れない心」に変わる 言いかえのコツ』(植西 聰 著/講談社)2021年10月出版
Amazon
楽天ブックス
紀伊國屋書店
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事


























