
財布は一緒派?別々派?夫婦1年目のお金との付き合い方を考えよう
今回は、坂下仁氏の著書『夫婦1年目のお金の教科書 夫婦生活はお金の相性で決まる!』(ダイヤモンド社)をもとに、夫婦1年目のお金のコトについてまとめました。
目次
夫婦1年目で知っておきたいお金の基本
夫婦1年目ではどんなお金の問題が発生するのでしょう。本著では、お金のことについて世帯年収が約800万円の夫婦を想定して解説されています。
結婚すると、将来のことを見据えて「貯金しなければ」という意識が芽生えます。そこでまず知っておきたいのが「三大出費」である、教育費・住宅費・老後資金です。ざっくり計算すると、約6,600万円必要になります。内訳については以下です。
- 教育費:約1,000万円(子供2人の場合)
- 住宅費:約3,600万円
- 老後資金:約2,000万円
教育費
国公立で通した場合、幼稚園から高校まで約541万円(※1)、大学4年間は約539万円(※2)かかります。合計すると1,080万円。もちろん私立や学部などで、学費は変わります。大学は奨学金もあるので、子供1人につき幼稚園から高校までの541万円は最低必要となります。また、児童手当が1人あたり15年間で、約200万円もらえます。
これらを考慮すると、学費以外に塾代や習い事も含めて、子供2人で幼稚園から大学まで国公立の場合、約1,000万円を確保すると良いでしょう。住宅費と、老後資金については、後で詳しく解説します。その前に、普段の生活に関わる費用について説明していきます。
生活費
家計にはどんな費目があるのでしょうか。費目は、使い道別に分けると20個以上になります。毎月の支出が一定の費用を「固定費」、支出が上下する費用を「変動費」と言います。
固定費
- 住宅費
- 水道光熱費
- 保険代
- 通信費
- 新聞図書費
- 教育費
- おこづかい
- 税金
- 社会保険料
変動費
- 食費
- 外食費
- 日用品費
- 交際費
- 交通費
- 車両費
- 美容費
- ペット費
- 衣服費
- 医療費
- 趣味費
- 教養娯楽費
- 冠婚葬祭費
- 特別費
普段家計簿をつけている家庭なら、この仕訳作業は行っているでしょう。その時、おすすめしたいのが「なぜ使うのか?」と考えて目的別で分けること。出費は、税金等を除いて「生活費」「あそ費(び)」「おこづかい」「特別費」しかありません。これに、先述した三大出費に備える「貯蓄」が加わります。
- 生活費:健康的に生きるために必要不可欠な費用(住宅費や食費など)
- あそ費(び):家族みんなが楽しむための費用(家族での外食や教養娯楽費など)
- おこづかい:自分一人が楽しむための費用(個人的な趣味や嗜好品など)
- 特別費:たまに発生する出費(冠婚葬祭や車検、引っ越し、旅行など)
+
- 貯蓄:三大出費(教育費・住宅費・老後資金)のような将来の出費に備える
これらを「なぜ使うのか?」を重要視して、ざっくり「見える化」して管理すると、お金が足りなくなったり、思うように貯蓄できなかったりする原因が見えてきますよ。
理想的な費目の割合は、「生活費4割、あそ費2割(特別費含む)、おこづかい2割、貯蓄2割」ですが、世帯収入や生活スタイルによって異なるため、家族会議で心地いい割合を見つけておくとお金のトラブルも少なくなります。
夫婦のお金は一緒にすべきか、別々にすべきか

恋人と夫婦との決定的な違いは「お金」です。夫婦生活はお金の相性で決まると著者は考えています。そこで、夫婦円満のカギを握るのが「お金の見える化」です。
お互いの給与明細を見せるかどうか
まず、給与明細を見せるべきかという問題ですが、著者の考えは「YES」です。お金を隠していると、余計な心配を与えかねません。収入が夫婦合わせて2倍になれば、二人で一緒に上手に使えるので、そういった意味でも、収入全体を見える化するメリットはあるでしょう。
次に、財布を一緒にする方がいいかという問題ですが、こちらも著者の考えは「YES」です。夫婦の財布は一本化した方が、シンプルで分かりやすいです。生活口座も一本化しましょう。クレジットカードの引き落としや公共料金、家賃の支払いはすべてここから引き落とします。
夫婦どちらかの給料振り込み口座を生活口座扱いにして、収入と支出を可能な範囲で集約し、ガラス張りに近い状態にしておくと良いでしょう。
財布の紐はどちらが握るか
そして、財布の紐をどちらが握るべきかの問題ですが、著者の考えは、お金の流れが見えればどちらも握る必要はありません。一般的には、主に買い物を担当する妻が財布を握ることが多いようですが、あえて握らなくても大丈夫です。
著者が一押しするのが、「家族会議」に財布を握らせて、ざっくり「見える化」する方法です。家族会議では、家計のルールや大きな支出についてざっくりと話し合います。「見える化」した家計を一緒に眺めて、「今月は生活費が少なかったから、来月はおいしいものでも食べに行こう」と言った、雑談レベルの会話で十分です。
家族会議で家計のルールを決めると、夫婦のどちらかが財布を握って、上下関係が生まれることをある程度防いでくれます。きちんとした家計簿はなくても大丈夫です。家計簿アプリを使ったり、レシートを貼るだけの家計簿を作ったり、続けられる方法でお金の「見える化」をしましょう。
おこづかいはどれくらいに設定すべきか
家計を安定させるためには、おこづかい制がいいのかという問題ですが、著者の考えは「YES」です。おこづかいは世帯収入の2割が目安。つまり、夫婦で1割ずつとなります。飲み代や、コーヒー・タバコなどの嗜好品、洋服を買うなど、これらはおこづかいで賄います。仮に世帯年収が手取りベースで40万円ある場合は、夫婦それぞれが4万円のおこづかいを受け取れます。
おこづかいの使い道について大切なのは、「お互い一切干渉しないこと」と著者は言います。なぜかと言うと、どんなに仲がいい夫婦でも、自分一人の時間を楽しめないと窮屈に感じてしまうから。おこづかいは、一人で楽しむお金です。使い道は、へそくりとして貯金しようが、趣味のモノを集めようが、そこには干渉しない・詮索しないようにしましょう。
夫婦1年目は、賃貸が安心!住宅費はどれくらい?
住宅費は、人生の三大出費と先に紹介しました。生涯支出の中で、税金・社会保険料に次ぐ2番目に大きな出費です。そのため、「住宅費を上手にコントロールできるかで、人生が決まると言ってもいいほど」と著者は紹介しています。
今回は、夫婦1年目の住宅費のお話をします。
夫婦1年目のライフスタイルは変化が多い
夫婦1年目で、賃貸の方がいいか、借金してまで家を買った方がいいのかという問題ですが、著者の考えとしては「購入は後回しでOK」です。夫婦1年目のライフスタイルは、まず結婚で変わり、子供が産まれてから、そして子供が独立するまでめまぐるしく変化します。そのため、賃貸の方が安心でしょう。
住居の安さと広さ問題
安さと広さどちらを重視するかの問題については、著者の考えは「最初は安く、後から広く」です。なぜなら、裕福になる秘策は住宅費にあるからです。家族が増えたり、転職したりして職場が変わることもあります。仕事や生活などをトータルで考えて、どの場所が最適か、家賃はどのくらいが良いのかを決めます。
家賃は収入のどのくらいの割合が適正か
住宅費は、世帯収入の合計2割以下におさえるのが理想的で、3割以上になるとお金が貯まらないと著者は言います。先述した、理想的な費目の割合「生活費4割、あそ費2割、おこづかい2割、貯蓄2割」にある生活費4割の中で、家賃+管理費などの総額が2割以下という計算です。目安で余った分は、子供の教育資金や老後資金に充てた方が良いです。
老後までにいくら貯蓄すべき?「2,000万円必要」は本当か

誰しもが働けなくなる老後が訪れます。そうすると不安になるのが、生きてく上で必要な老後の生活費です。最後に、「老後の資金はどのくらい残しておけばいいのか」という問題について解説します。
老後資金の貯蓄の目安を考える
現在、老後に2,000万円必要という問題がよく世間で言われています。仮に、その前提で考えてみます。最初に、人生の三大出費は全体で約6,600万円必要だとお話ししました。例えば、夫が正社員、妻が非正規社員という夫婦のケースで試算してみましょう。
著者によると、男性正社員の生涯賃金はざっくりベースで平均すると3億円前後、女性非正規社員で約1億2,000万円前後と推測されていますので、このケースでは、夫婦合算で4億2,000万円と仮定できます。そのうち、税金と社会保険料は合計約2割前後なので、合計で8,000万円強になります。
したがって、給料とボーナスから天引きされる税金と社会保険料と同じ金額を積み立てていれば、6,600万円以上貯められる計算になります。また、手取り合計が3億4,000万円になるので、「6,600万円÷3億4,000万円=約2割」を貯めていく方法でも、三大出費はクリアできます。
では、具体的にどうやって貯めるかという点で著者は「確定拠出年金」「小規模企業共済」「財形貯蓄」「積立定期預金」のような自動積立口座を作る方法をおすすめしています。生活費とは別に、夫婦別々で作ると良いでしょう。そして、お金の貯めどきは、「結婚直後から子育て開始までの間」です。出産を機に、教育費と保険代が家計に重くのしかかるため、子供ができるまでのわずかな期間が貴重です。
ライフスタイルに合わせて老後資金も変わる
日本が存続する限り、収支のバランスを見るはずなので、年金の破綻はないと著者は言います。もちろん貯蓄はあるに越したことはないですが、ライフスタイルによっては2,000万円なくても大丈夫です。
例えば、現役時代の収入が高い人や退職金が多い人、または夫婦共働きを続けて、厚生年金をフルで受給する家庭、他にも、物価の安い地域に移り住む場合や、65歳以降になっても働き続ける人など、その人のライフスタイルによって老後の資金額は変わります。
まとめ
夫婦になったら、まず家計の「見える化」を行いましょう。理想的な費目の割合は、「生活費4割、あそ費2割(特別費含む)、おこづかい2割、貯蓄2割」です。夫婦1年目はライフスタイルの変化も多いので、借家住まいから始めるのが安心でしょう。
老後の備えは、働ける今のうちから貯蓄するに越したことはありません。「税金+社会保険料」と同額、つまり手取りの約2割を生活費とは別に、夫婦別々で貯めていくのがおすすめです。将来のなりたい家庭像を夫婦で話し合って、そのスタイルに合わせてお金と上手に付き合っていきましょう!
書籍紹介:『夫婦1年目のお金の教科書 夫婦生活はお金の相性で決まる!』(坂下仁著/ダイヤモンド社)2020年3月出版
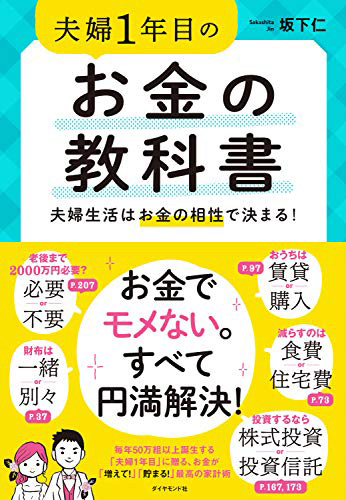
出版社書籍紹介:『夫婦1年目のお金の教科書 夫婦生活はお金の相性で決まる!』(坂下仁著/ダイヤモンド社)2020年3月出版
・Amazon
・楽天ブックス
・紀伊國屋書店
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事


























