
今年の汚れは今年の間に落とす!掃除が苦手な人におすすめの方法を紹介
目次
今年の汚れは今年の間に落とす!掃除が苦手な人におすすめの方法を紹介
掃除に対して苦手意識がある人や、掃除が嫌いだと思っている人が厄介だと思っているのが、年末の大掃除ではないでしょうか。「どこから手を付けたらいいか迷ってしまう」「部屋の各箇所をどうやって掃除するのかわからない」と悩んでしまいますよね。「忙しいし、後にしよう」と後回しにして、結局大掃除をしないという経験がある人もいるかもしれません。
この記事は掃除が苦手な人のために大掃除の方法を紹介する記事です。大掃除をする前に意識したいことや、部屋の各箇所の掃除の方法、掃除への苦手意識を克服するポイントを解説します。
今年出た汚れは今年の間に落としてしまいましょう。
今年の汚れは今年の間に落とそう

まずは掃除が苦手な人が陥りがちな状態について解説をしていきます。
掃除が苦手だと後回しにしてしまいがち

「できるなら掃除をしたくない」「掃除をするといっても何をしていいかわからない」と掃除に対して苦手意識を持っている人もいますよね。
そんな人が師走になると頭を悩ませるのが「年末の大掃除」ではないでしょうか。日頃から掃除をする習慣がないと、手を付ける箇所が多すぎて、「忙しいし、次の休みになったら考えよう」と先送りにしてしまう人も少なくないはず。嫌いなことや苦手なものはついつい後回しにしたくなるでしょう。
後回しにすると、結局やらなくなってしまう

掃除が苦手な人が、大掃除を「また今度にしよう」と後回しにしてしまうケースは珍しくありません。そして後回しにした結果「大掃除をしないまま年を越してしまった」となってしまうこともあります。
掃除に苦手意識があると、先送りにしても掃除をやる気にはなかなかなれないかもしれません。でもいつかはやらなければならなくなりますよね。
「今年ついた汚れは今年中に落としてしまおう」そんな気持ちを持って今年こそはしっかり大掃除をしましょう。
大掃除が苦手な人が意識したいこと

ここでは大掃除が苦手だと思っている人がなるべく効率よく掃除に取り組むための方法を紹介します。
やみくもにやらずにスケジュールを立てる

大掃除は、目についた場所からやみくもに手をつけていくよりも、スケジュールを立てて効率的に行動したほうがスムーズに行えます。
順番は以下を意識するのが基本です。
・部屋の奥から手前に向かっていく
・上部の掃除から下部へ向かう
玄関から見て手前の部屋や床の掃除からはじめてしまうと、奥のゴミを運び出すときや、エアコンや天井など上部の掃除をしたときに再び汚れて二度手間になります。
動きやすくて、汚れてもいい服装でやろう

部屋の掃除とはいっても、普段着で行うと「動きにくい」「服が汚れてしまった」となってしまいます。大掃除をするときはジャージなど動きやすくて、汚れてもよい服装で行うのがおすすめです。
さらにエプロン、スリッパ、ゴム手袋を用意しておくと効率的に大掃除ができるでしょう。
足りない道具は100均でもそろう

日頃から掃除をする習慣があまりないと「掃除道具を持っていない」という人もいるでしょう。掃除道具や掃除に使えるアイテムの多くは、100円均一のショップでも購入できます。
ほうきや雑巾はもちろんのこと、手袋型の掃除用クロスや、洗面台の汚れ落とし用の不織布、フローリングドライシートなどさまざまな掃除グッズを揃えることが可能です。
自宅に掃除グッズがない人で「手頃な価格で揃えたい」と考える人は、一度100円均一ショップに行ってみましょう。
1日でやるのが苦手な人は日を分けてやる

「大掃除を1日で終わらせる自信がない」という人は、無理に1日で終わらせる必要はありません。日を分けて少しずつ大掃除を進めて行くのもおすすめの方法です。「今日は水回り、来週は居間」などスケジュールを決めて行いましょう。
また完璧を求めすぎるのもやめましょう。大掃除は普段あまり掃除をしない場所も掃除します。そういった場所を掃除するのは時間がかかります。「いくらやっても、なかなかきれいにならない」となる場合もあるでしょう。
あまり完璧を目指さずに自分の時間と体力を考えながら、ある程度で切り上げる気持ちも大切です。
今年の汚れは今年中に落とす!水回り編

ここからは具体的な掃除の方法を紹介します。まずは水回りからみてみましょう。
コンロ

コンロには重曹を使うのがおすすめです。こびりついた油汚れや食品のカスなどを取るのが楽になります。落ちにくい汚れは、重曹を溶かしたぬるま湯につけ置きしましょう。
IHコンロの場合はセスキ炭酸ソーダをふりかけて、アルミたわしなどでこすると、焦げつきをキレイに落とせます。
ただし、重曹やセスキ炭酸ソーダはアルカリ性のため、肌荒れの原因になることもあります。肌荒れを起こしやすい人はゴム手袋を着用することをおすすめします。
シンク

キッチンのシンクは排水溝のぬめりや、水垢、石鹸カスなどが気になりますよね。ステンレスのキッチンシンクは、細かい傷に汚れがたまりやすい場所です。
排水溝のぬめりや石鹸カスには重曹を使いましょう。水垢はクエン酸を使うと落としやすいですよ。
ただし、酸性のクエン酸は塩素系漂白剤と混ぜると有毒ガスを発生させてしまいます。塩素系漂白剤はカビの除去など掃除でも使う機会の多い洗剤ですので、注意書きを確認し、決して一緒に使わないようにしましょう。
冷蔵庫

まずは冷蔵庫の中のものを出します。冷蔵庫の中に消費期限が切れた食品や、使わない調味料などが入ったままの人もいるのではないでしょうか。もう食べられない、使わないものなどは衛生面で不安もあります。まずはそれらを処分してしまいましょう。
冷蔵庫の中は重曹水や除菌シートで除菌や除臭をしてください。カビや雑菌が発生しにくくなります。
換気扇

キッチンの換気扇は油やホコリの汚れがたまります。普段あまり換気扇回りの掃除をしない人は大掃除のタイミングでしっかりキレイにしておきたいもの。換気扇で掃除する箇所はファン、フィルター、フードです。
ファンとフィルターは、重曹やセスキ炭酸ソーダなどアルカリ性洗剤を60℃程度のお湯に溶かしたものに、30分~1時間つけ置きましょう。つけ置きすることで軽度の汚れであれば簡単に落とせるようになります。
アルカリ性の洗剤を使用する際の注意点を、以下に記載するので参考にしてくださいね。
【弱アルカリ性洗剤(重曹やセスキ炭酸ソーダなど)】
・長時間使用する場合、または肌の弱い方は、手袋を着用して洗剤が皮膚に触れないようにしましょう。
・目に入ってしまった場合は流水でよく洗い流しましょう。
・飲み込んでしまった場合は、吐き出さずによく口をすすぎ、水を飲みましょう。
・異常がある場合には医師に相談してください。
【アルカリ性洗剤(合成洗剤など)】
・合成洗剤の中には、重曹やセスキ炭酸ソーダよりも強いアルカリ性を示す洗剤もありますので、より慎重な取り扱いが必要となります。
・皮膚についた場合は、すぐに水で十分に洗い流しましょう。
・目に入ったときは、すぐに流水で15分以上洗い流しましょう。異常を感じなくてもすぐに眼科医を受診しましょう。
・飲み込んでしまった場合は、吐き出さずによく口をすすぎ、水を飲みましょう。異常を感じなくてもすぐに医師に相談してください。
お風呂

お風呂は掃除をする箇所が多いです。普段はあまり手を付けない、ぬめりやカビ、換気扇などを大掃除の機会にキレイにしましょう。
・水垢
鏡や洗面器、蛇口などに付いている水垢は、クエン酸を使用するのがおすすめです。クエン酸をスプレーなどで吹きかけて10分程度放置してからスポンジでこすって落としましょう。
また水垢はクエン酸を吹きかけてキッチンペーパーを貼り付けておくと、やわらかくなり落としやすくなりますよ。
・カビ
カビ取りには塩素系漂白剤が効果的です。乾いた雑巾でカビ部分の水分を拭き取ります。続いて塩素系漂白剤をカビにつけて、キッチンペーパーで覆ってください。
さらにキッチンペーパーに塩素系漂白剤をかけてラップを貼り付けます。30分ほど放置して水で洗い流しましょう。
塩素系漂白剤は刺激が強いものもあるので、肌や衣類に付かないように注意してください。ゴム手袋を着用して使用するのがおすすめです。
お風呂掃除で使用する機会が多い塩素系漂白剤は、クエン酸を含む酸性の洗剤と混ざると有毒な塩素ガスが発生します。十分に注意して使うようにしてくださいね。
トイレ

便器や便座の掃除はクエン酸を水に溶かしたものをスプレーボトルに入れて使うのがおすすめです。クエン酸はアルカリ性の尿石を落とすのに役立ちます。気になる箇所に吹きかけて拭き取りましょう。
余力があれば天井や壁も大掃除のタイミングでキレイにしてみるのもおすすめです。
洗面所

洗面所も毎日使用する箇所なので、水垢、手垢、化粧品などの油汚れなどさまざまな汚れが付きます。これらの汚れはクエン酸や重曹で落とせるものがほとんどです。水垢、黒ずみにはクエン酸、油汚れには重曹を使って、キレイにしましょう。
今年の汚れは今年中に落とす!部屋周り編

続いて部屋の掃除方法を紹介します。
パソコンやデスク
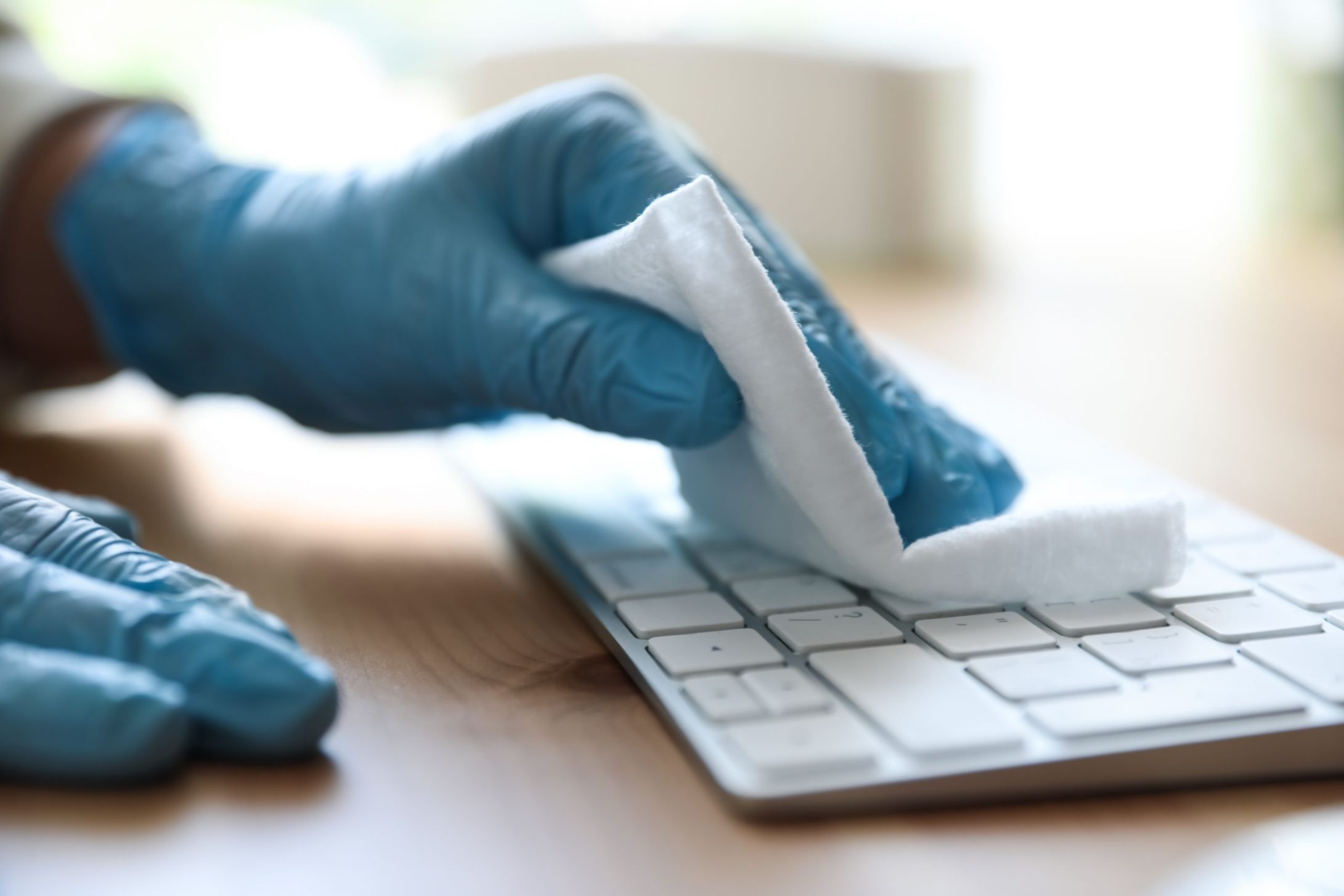
パソコンや設置されているデスクも、ホコリなどで汚れている箇所です。乾いた布で軽く叩くように拭いてモニターのホコリを取り除きましょう。キーボードや端にたまったゴミはエタノールを染み込ませた綿棒を使用すると掃除しやすいです。濡らしすぎには注意してくださいね。
畳

畳の汚れや黄ばみを落とすのは、お酢を使うのがおすすめです。バケツ半分の熱湯に対してカップ半分程度のお酢を入れましょう。それを布に浸して畳を拭くとキレイに汚れが取れます。
畳の縁は変色する場合もあるので、拭かないようにしましょう。
フローリング

普段は掃除機で済ませているフローリングも大掃除のときは水拭きをしてみましょう。その際には米のとぎ汁を使うのもおすすめです。とぎ汁を含ませた布で拭きます。その後に拭き残しがないようにキレイに乾拭きするとフローリングにツヤが出ます。
カーペット

カーペットの掃除は前日から準備をしておくと、よりキレイにできておすすめです。重曹を前日の夜間に振りかけておき、大掃除当日に掃除機をかけて吸い取ると重曹が汚れや匂いを吸着して取り除けます。
カーペットの内部に入り込んだ糸くずやペットの毛などはタワシで表面にかき出してからテープを使って剥がすとキレイになりますよ。
カーテン

カーテンは洗濯機で洗える素材のものならば、洗濯ネットにいれて丸洗いしてしまいましょう。カーテンなどの布類はホコリや汚れが付きやすい製品なので、大掃除の最後に洗うのがおすすめです。部屋の掃除で出たホコリや汚れを吸着させずにすみます。
ベッド・ソファ

ソファやベッドには手垢や皮脂汚れが多く付いています。セスキ炭酸ソーダを振りかけて2時間ほど放置しましょう。その後、掃除機で吸い取れば手垢や皮脂汚れが取れてキレイになりますよ。
掃除が苦手な人がしておきたいこと

ここでは掃除が得意ではない人のために、苦手を克服するポイントを紹介します。
完璧を求めすぎない

「どれだけ掃除しても、納得できる結果にならないのが不満」というのが理由で掃除に苦手意識を持っている人もいるでしょう。
掃除に完璧を求めすぎると、いつまでも納得ができずにストレスになってしまいます。朝や夕方、曜日ごとなどに掃除する場所を決めて、負担にならない程度に続けていけば習慣化できるのでおすすめです。
片付けと掃除は別物と理解する

掃除が苦手な人は「片付け」と「掃除」を混同して考えてしまうところがあります。この2つを同時に行おうとするので「掃除は大変だな」と手間に感じがちです。
片付けは物を収納したり整理したりすることで、掃除はホコリや汚れを取り除いて部屋や家具などをキレイにすることです。この2つを同時にやろうとしないで、まずは片付けを行いましょう。部屋が整頓された状態になってから掃除をするほうが、効率よくできます。
正しい掃除の方法を知る

正しい掃除の方法を知らないと、思ったようにキレイにできません。どんなことも同じですが、掃除も上手にできないと楽しいとは思えませんし、続けるのも嫌になってしまいます。
掃除が苦手だと思っている人は正しい掃除の方法を覚えるのがおすすめです。掃除をしている場所がどんどんキレイになっていくと、掃除をするのが楽しくなり、苦手な意識もなくなりますよ。
▼まとめ|工夫次第で掃除への苦手意識は消える!今年の汚れは今年中に落としましょう
大掃除を後回しにして「掃除しないまま年を越してしまった」という人もいるでしょう。掃除が苦手なのは「どのように掃除をしていいのかわからない」が理由になっているケースもあります。まずは掃除の正しい方法を知るのも大切なポイントです。
正しい方法で効果的な掃除ができると、掃除の楽しさが理解できるでしょう。ぜひ、今年の汚れは今年中にキレイにしてくださいね。
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事

























