
ぽかぽか習慣で健康生活 無理なくはじめる「温活」のすすめ

あなたの体は冷えていませんか。また、冷えを感じているのに「特別なことをするのは面倒」とあきらめてはいませんか。「温活(おんかつ)」とは、健康を維持するために、適正な温度に平均体温を保つ活動のことです。ここで紹介する項目を、無理なく日常生活に取り入れつつ、ほっこりと過ごすヒントにしてください。
ぽかぽか習慣で体と心を整えよう

適正な温度に体温を保つと、体と心のバランスが心地よく整います。そして、筋肉や血流が正しくめぐり出し、快適な毎日を過ごせるようになるでしょう。まずは、温活の基礎知識を紹介します。
温活で「ゆるむ」「めぐる」「治る」
温活による効果として、3つのメリットを挙げることができます。
(1)ゆるむ
体を温めると、筋肉と関節の緊張がゆるまり、体がふっと柔らかくほぐれます。同時に、心の緊張もゆるんで、気持ちがラクになるでしょう。体と心が動かしやすくなることによって、新しいことにチャレンジする勇気が湧いてくることもあります。
(2)めぐる
体が温まって末端の血流がめぐり出すと、体のすみずみまで酸素と栄養を含んだ血液を届けることができます。
(3)治る
体温が上がると免疫力が高まり、病気にかかりにくく治りやすい体になるといわれています。さらに、自律神経とホルモンバランスが整い、不安感や不眠など心の不調も改善できるといわれています。
温活の5つの心得
心身の不調の原因となる冷えを解消するためには、日頃から5つの心得を意識しましょう。
(1)生活習慣の改善
日頃の生活で体を冷やしているとしたら、生活自体を改善しないことには、温活の効果も半減してしまいます。まずは生活習慣を見直して、冷えの原因を探りましょう。
(2)バランスのよい食事
食事は体をつくるうえで重要な要素です。自分の体質や体調、食べるタイミングなどを総合的に判断し、どんな食材が適しているのかを正しく選びましょう。
(3)体の力を引き出す
冷えを解消するには、自分で熱を生み出せる体になることが重要です。適度な運動で筋肉量を増やしたり、マッサージで血流をよくしたりなど、健康的な体づくりを目指しましょう。
(4)漠然と温めない
何でもかんでも温めればいいという考え方は禁物です。体を極度に温めると、不調をきたしてしまうこともあります。体質や体調に合わせて、適切に体を温めましょう。
(5)続けることが大切
温活はすぐに効果が出るものではありません。毎日の習慣に落とし込み、継続することが大切です。我慢や無理をせずに、自然体で続けられるものを取り入れましょう。
ぽかぽかさんの生活習慣とは
温活は日頃の積み重ねが大切です。体を温めるための理想的な1日を紹介します。
(1)朝起きたら
朝起きたら、カーテンを開けて朝日を浴び、眠気をリセットしましょう。朝食は温かいスープなどを中心にして、あまり食べ過ぎないように心がけましょう。
(2)通勤中や仕事中
駅での階段の利用や、電車内でのかかとの上げ下げで、血流を促すことができます。適度な筋肉がつくとポンプ作用が鍛えられ、より血流がよくなります。テレワークが続くと運動不足になりがちなので、意識して体を動かしましょう。
デスクワーク中は正しい姿勢を意識し、30分に1度は立ち上がって血流を促しましょう。ひざ掛けやレッグウォーマーで冷えを防ぐことも大切です。ランチや休憩時間は、温かいスープや味噌汁、ショウガ入りの紅茶などを飲んで、体を温めましょう。
(3)帰宅から就寝まで
夕食は温かい鍋料理がおすすめです。アルコールは血流をよくするので、適量なら問題ありません。おつまみには、胃腸に優しく栄養価が高い、豆腐や煮魚、発酵食品などが適しています。
入浴時と就寝時のポイントは、下記で紹介しています。就寝の2~3時間前にストレッチを行うと、筋肉がほぐれて眠りやすくなります。
冷えない暮らしは食を意識しよう

温活をする上で外せないのが、体を内側から温める、食べる温活です。自分の体と相談しながら、必要なものを食べるように意識しましょう。
温まる食べ物と食べ方
食べる温活では、体温のリズムを意識することが大切です。人の体温は基本的に、早朝が最も低く、しだいに上がって夕方が最も高くなります。朝は代謝を上げる食事で体の活動を促し、昼は体温を上げるバランスのよい食事を、夕方は消化がよく体温を発散する食事を意識しましょう。三食の中に特に取り入れたい食材がこちらです。
(1)日本食
味噌汁や納豆などの発酵食品や、DHAやEPAを含む魚、だしの旨みを利かせた減塩レシピなど、日本食には温活に適した料理がたくさんあります。旬の食材を取り入れながら、体を温める食事を取り入れましょう。
(2)ネギ類
ネギやニラ、ニンニクなどのネギ類には、体を温めて血行をよくする効果が期待できます。免疫力アップに関する研究もされているので、毎日の食事に効果的に取り入れましょう。
(3)トマト
トマトに含まれるリコピンという成分には、血行をよくして体を温める効果が期待できます。温かいトマトスープは特におすすめです。
(4)発酵食品
味噌や納豆、しょう油、チーズなどの発酵食品に含まれる酵素成分は、血行や代謝を促すといわれています。
ショウガパワーの秘密
青果店やスーパーで、季節を問わず手軽に購入できるショウガ。発汗を促して代謝を上げるとされる「ショウガオール」と、血行を促進して体の表面を温めるとされる「ジンゲロール」の、食べる温活を支えるふたつの成分が含まれています。
1日に摂取する適量は、生ショウガなら10g程度で親指大の2片くらい、乾燥ショウガなら3g程度が目安となります。加熱調理をするとより温活効果が高まるといわれているので、豚肉のショウガ焼きをはじめ、炒め物や揚げ物など、食材を選ばずに使うことができます。
ショウガとネギと炒めて豆板醤を加えた「食べるラー油」や、お湯に生ショウガの絞り汁とハチミツを注いだ「ショウガドリンク」、紅茶に絞り汁やスライスを入れた「ジンジャーティー」などもおすすめです。
温活でアンチエイジングをしよう

体を温めて血流をよくすることで、適正な体重に導くダイエット効果や、肌のトラブルを改善するアンチエイジング効果を期待できる場合もあります。温活で健康的な体を目指しましょう。
温活で「痩せる」「きれいになる」
温活で体を温めると、基礎代謝が高まります。すると、脂肪が燃焼しやすい体を目指すことができ、太りにくく痩せやすい体をつくることが期待できます。
また、体を温めると血流がよくなるため、酸素や栄養が体のすみずみへ届きます。すると、肌がきれいになり、吹き出物ができにくくなるなどの効果が期待できます。加えて、水分代謝の機能が整うため、むくみやすい人は余分な水分が排出され、乾燥しがちな人は水分を保持する機能が働くようになるでしょう。
ちなみに、血流を促すためのマッサージは、ツボをそっと押したり、やさしくなでたりするのがおすすめです。強くこすったり、無理に動かしたりするのは、シワやシミの原因になることもあるので注意しましょう。
温活入浴のすすめ
毎日の入浴は、温活を成功させるためのカギとなります。浴槽のお湯は、40℃前後で胸の下くらいまで。少なくても10~15分程度浸かって体を温めるのが理想的です。バスタイムの6つのステップを意識しましょう。
(1)かけ湯からスタート
入浴すると体温とともに血圧が変化します。まずは、かけ湯で体をお湯になじませましょう。心臓から遠い手や足から徐々にかけ湯をします。
(2)入浴剤でポカポカに
重炭酸の入浴剤は、毛細血管を広げて血行を促進する効果が期待できます。天然ハーブやバスソルトなど、好みの入浴剤でリラックス効果を高めるのもいいでしょう。
(3)温冷交互浴が効果的
熱いお湯と、冷水(または、冷たいくらいに感じるお湯)で交互に刺激を与えることで、血管が拡張と収縮を繰り返して血流がよくなります。すると、疲労物質の乳酸などが排出され、疲労回復効果が期待できます。体調と相談しながら上手に取り入れましょう。
(4)体の洗いすぎは厳禁
体をナイロンのタオルなどでゴシゴシと洗いすぎてしまうと、強い摩擦が肌への刺激になるほか、必要な皮脂まで洗い流されてしまうことがあります。石鹸を泡立ててやさしく手洗いする程度で十分です。
(5)入浴しながらマッサージ
体が温まっているときは、マッサージに最適な時間です。特に、入浴中は水圧によって老廃物が流れ出やすくなるため、効果がアップすると考えられます。こりやむくみをほぐしなら体を整えましょう。
(6)お風呂上がりのポイント
お風呂では自覚がなくても汗をかいているので、入浴後の水分補給は忘れずに行いましょう。また、お風呂上がりの肌は乾燥しやすいので、化粧水を早めにつけ、落ち着いたら乳液で潤いを閉じ込めましょう。髪の毛はしっかりと乾かして、冷えの原因にならないようにしましょう。
理想の睡眠方法
体温を整え、冷えない体づくりを目指すには、正しい睡眠への意識も不可欠です。まず、体温が高いと眠りづらくなるため、入浴は眠る60~90分前に行うのが理想的です。同じ理由から、冬の暖房の温度設定は16℃程度、夏の冷房は25~27℃、湿度は40~60%を目安としましょう。
寝具やパジャマは、吸水性や放湿生に優れ、体の放熱を妨げないものを選びましょう。足先に寒さを感じても、靴下の着用は血行や体温の調整を妨げることも考えられるため、避けたほうがいいでしょう。締めつけのゆるいレッグウォーマーや、じんわりと温まる湯たんぽが適しています。
まとめ
温活とは、健康を維持するために、適正な温度に平均体温を保つ活動のことです。「ゆるむ」「めぐる」「治る」などのメリットが期待できるので、日頃の生活から体を温めるための行動をとり、継続することを目標にしましょう。
なかでも毎日の「食事」や「入浴」は、温活を続ける上で大切な要素となります。日本食やショウガなどを食事に取り入れるように心がけ、バスタイム40℃前後のお湯に10~15分程度は浸かるように意識し、体を冷えから守りましょう。
書籍紹介:『はじめての温活』(日本温活協会監修/宝島社)2021年10月出版
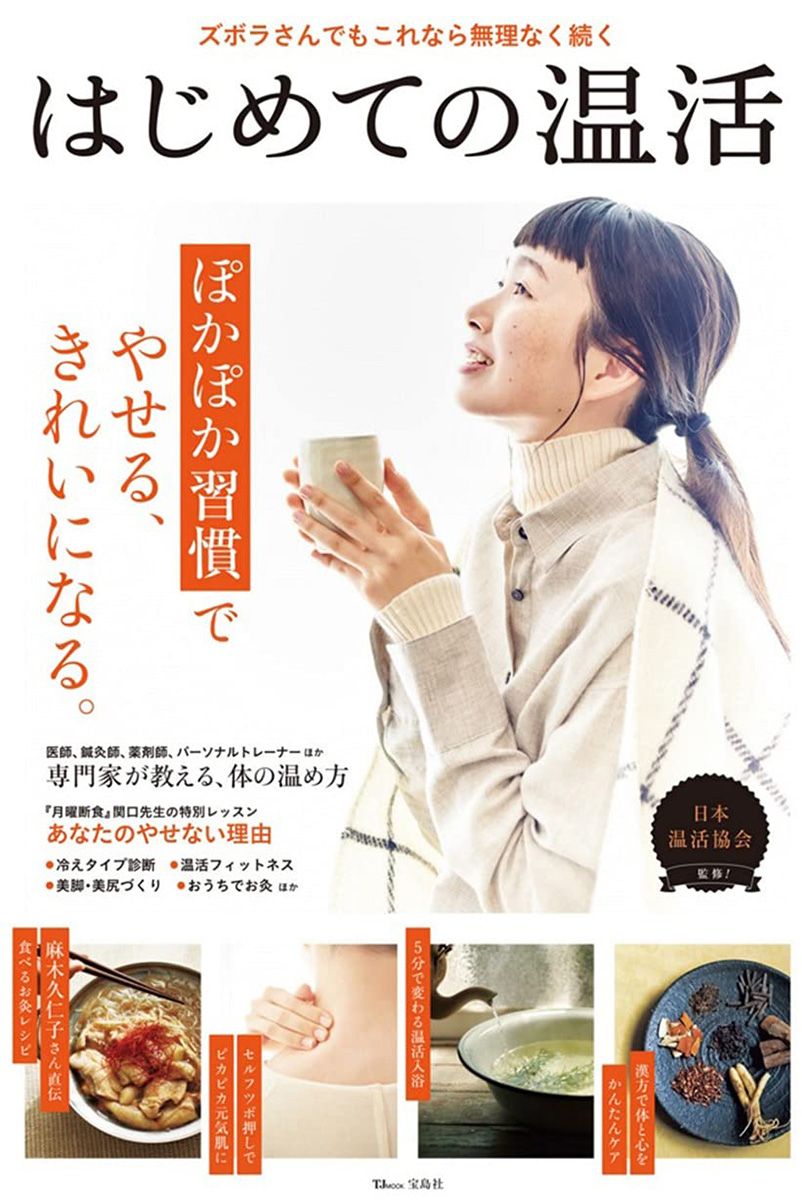
出版社書籍紹介:『はじめての温活』(日本温活協会監修/宝島社)2021年10月出版
・Amazon
・楽天ブックス
・紀伊國屋書店
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事


























