
iDeCoで老後資金を賢く貯める!仕組みやメリット、運用方法を紹介
今回は、ファイナンシャル・ジャーナリストである竹川美奈子氏の著書『[改訂新版]一番やさしい!一番くわしい!個人型確定拠出年金iDeCo活用入門(ダイヤモンド社)』をもとに、 iDeCoの概要や活用するメリット、運用方法などを解説します。仕組みを知って、老後資金をしっかり貯めていきましょう。

目次
iDeCoとは?基本情報や活用メリット
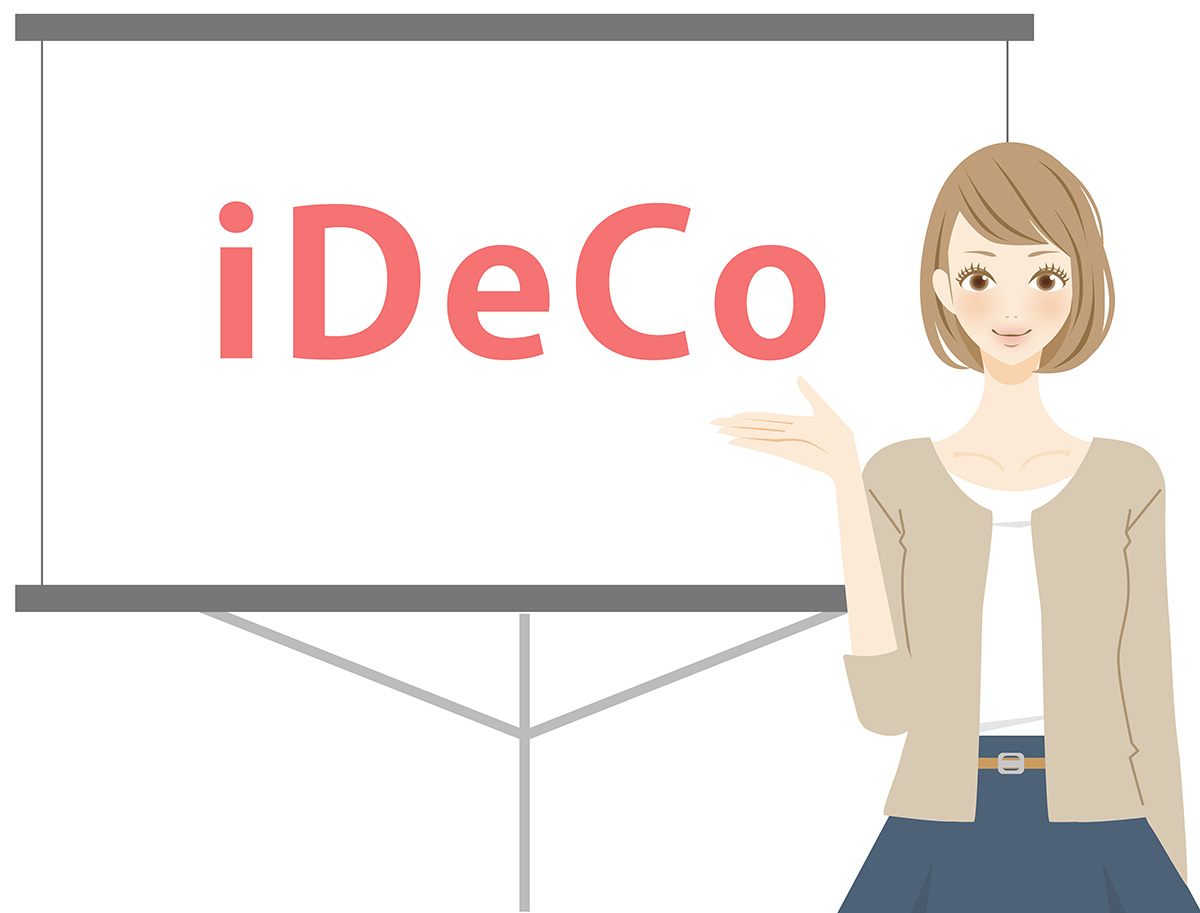
iDeCoとは個人型確定拠出年金のことです。確定拠出年金にはiDeCoのほかに企業型DC(企業型確定拠出年金)がありますが、今回は個人型のiDeCoに絞って解説します。まずは、老後を支えるお金についてと、iDeCoの基本的な仕組み、活用するメリットについて見ていきましょう。
老後を支える3つのお金について知る
まずは老後に受け取れるお金について見ていきましょう。老後を支えるお金は、大きくわけて3種類あります。1つ目が、国から受け取る「公的年金」です。日本では20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入することになっていて、老後に「老齢基礎年金」として受け取ることができます。それに加えて、会社員、公務員の人は「老齢厚生年金」も受け取れます。
2つ目は、会社から受け取る「退職給付」です。「退職一時金」や「企業年金」がこれに該当します。そして3つ目が、「自分で準備するお金」です。自営業やフリーランス、会社から受け取る退職一時金や企業年金がそれほど多くない中小・ベンチャー企業などに勤める人は、とくに意識して準備する必要があります。
では、どのように自分で準備するお金をつくっていけばよいのでしょうか。そこで挙げられるのがiDeCoの活用です。
iDeCoの概要と流れ
iDeCoは、自分でお金を出して、預金や投資信託などで運用していき、60歳以降に運用してきたお金を受け取る仕組みです。国の法律で定められたれっきとした制度で、運用益が非課税になる(※1)ほか、掛金を払ったときも税金が安くなるなど、メリットも多いです。老後に向けてコツコツ資産形成をしたい人におすすめの制度と言えるでしょう。
※1:現状は非課税。運用資産に対して課税される特別法人税については現在課税が凍結されています。
【1.加入する】
金融機関を決めて加入手続きをします。
【2.拠出する(掛金を払う)】
毎月一定の掛金を銀行の預金口座から口座振替、または給与天引きで払っていきます(※天引きの可否は勤務先により異なります)。
【3.運用する】
金融機関が取り扱う金融商品(預金、保険商品、投資信託)の中から、自分でどの商品を何%ずつ買うか配分を決めて、運用していきます。
【4.給付】
運用してきたお金は原則60歳以降に、一時金(一括)か年金で受け取ります。なお、60歳を過ぎても引き続き70歳(※2022年4月以降は75歳)になるまで運用を継続することも可能です。
掛金はいくらまで設定できるか?
iDeCoの掛金には上限があります。拠出限度額ともいい、iDeCoに加入した時の「加入区分」によって掛金の上限額が決められています。 例えば、自営業やフリーランスなど国民年金の第1号被保険者にあたる人は、月額6万8,000円(年額81万6,000円)まで掛金を払うことができます(※2)。また、企業年金のない会社員や、専業主婦・主夫など国民年金の第3号被保険者にあたる人は、月額2万3,000円(年額27万6,000円)が上限となります。掛金は月額5,000円以上1,000円単位で自由に決めることができます。
※2:国民年金基金との合計額
iDeCoを活用するメリット
iDeCoの最大のメリットは税優遇があることです。「掛金を払うとき」「運用している間」「運用してきたお金を受け取るとき」それぞれの段階で優遇があります。毎月積み立てた掛金については、全額が「所得控除」の対象となるため、将来のために積み立てをしながら、所得税と住民税を軽減できます。また、iDeCoは原則60歳まで引き出すことができないので、長期で運用していくことになりますが、その間の預金の利息や投資信託の運用益は全て非課税(※1)となります。そのため、効率的に資産を増やすことができます。
※1:現状は非課税。運用資産に対して課税される特別法人税については現在課税が凍結されています。
仮に、毎月2万3,000円を30年間積み立てたとします。その場合、元本は合計828万円ですが、年3%で運用できると約1,340万円になります。掛金の上限額は加入区分によって決められていますが、累積投資額つまり積み上げていくお金の総額には上限がありません。ですから、早く加入して長い期間運用していくことができれば、その分、運用できるお金も積み上がっていきます。
iDeCoで運用できる商品について知る

iDeCoで運用できる商品は、「投資信託」「定期預金」「保険商品」です。1つの商品を選んでも良いですし、複数の商品を選んで配分割合を決めて、毎月積み立てていくこともできます。それぞれの商品について仕組みや特徴、留意点を紹介します。
投資信託・定期預金・保険商品について
投資信託とは、投資家からお金を少しずつ集めてひとまとまりにし、そのお金を運用会社が運用してくれる金融商品です。一人ひとりが出すお金はそれほど多くなくても、まとまって数十億円、数百億円単位になれば、個人ではアクセスしにくい地域や国に投資したり、たくさんの株式や債券などに投資したりできます。そして、運用成果に応じて、投資した人に収益が分配されるしくみになっています。
定期預金は、一般の窓口で取り扱われているものと商品内容は同じです。預け入れ時にあらかじめ金利が提示され、満期まで預ければ所定の利息がつきます。元本は保証されるため、確実に積立てができます。
保険商品は、損害保険会社が提供する「積立障害保険」や、生命保険会社が提供する「利率保証型積立年金」などがあります。基本は貯蓄型の保険商品となります。元本とその利息が再投資される点は定期預金と同じですが、一般的には同じ期間の定期預金に比べると、利率が高いケースが多いです。
投資信託を中心に商品を運用するのが◎
iDeCoでは長期で効率的な運用ができるため、金融資産全体で考えて、なるべく期待リターンの高い商品で運用するのが合理的です。そのときに基本となるのは「株式」です。株式は長期的に高いリターンをもたらしてくれるため、運用期間を長くとれる人は、株式に投資する「投資信託」を中心に運用した方が、大きくお金が育つ可能性が高くなります。なぜなら、長く運用することで得られる複利効果や、非課税の期間も長くなり、そのメリットを大きく得ることができるからです。
投資信託といっても、その中身は多岐にわたります。日本国内の企業の株式に投資する「国内株式型」、日本の国債や国内企業の社債に投資する「国内債券型」、海外企業の株式に投資する「外国株式型」、外国の国債や海外企業の社債に投資する「外国債券型」があります。さらには、日本を含む世界の株式に投資する「全世界株式型」、複数の資産を組み合わせた「バランス型」などもあります。
運用する際は、投資先や投資対象が異なる投資信託を組み合わせることもできますし、1つの投資信託を選択することも可能です。それぞれ商品によって特徴が異なるため、よく吟味して選びましょう。
iDeCoを実践!金融機関はどう選べばいい?

iDeCoに加入するには、自分で窓口となる金融機関を選んで口座を開設する必要があります。どのような金融機関を選べばいいか見てきましょう。
金融機関選びは慎重に
iDeCoの口座は、1人ひとつしか開設できません。取り扱っている金融期間は200以上あり、取り扱う商品や口座を開設してから継続的にかかる費用(口座管理手数料)、利便性・サービスなどは金融機関によって異なります。 iDeCoは、原則60歳までお金を引き出すことができないので、長い付き合いになります。そのため、金融機関の選択は慎重に行いましょう。途中で金融機関を変更することもできますが、時間も手間もかかるのであまりおすすめはできません。
金融機関選びの3つのポイント
金融機関選びのポイントは3つあります。
1つ目は、「手数料」。iDeCoに新規加入するときに、国民年金基金連合会に口座開設の手数料2,829円を支払います。あとは加入中、口座管理手数料がかかります。これは金融機関によって異なり、毎月の掛け金から差し引かれるため、口座管理手数料は金融機関選びで特に気にしたい点となります。他にも、投資信託の保有中にかかる運用管理費用(信託報酬)や、運用してきたお金を受け取るときの手数料などがあります。
2つ目は、「商品の品揃え」です。iDeCoは加入者本人が掛金で、「どの金融商品を」「どういう割合で」購入していくかを指定する必要があります。各金融機関では、定期預金や保険、投資信託といった商品を提供していますが、商品の種類や本数などはそれぞれ異なります。
3つ目は、「使い勝手やサービス」です。iDeCoに加入するにはWebサイトやコールセンター、金融機関の窓口などのチャネルを通じて、口座開設などを行う必要があります。Webでの情報が充実しているか、必要な機能があるかなどを比較すると良いでしょう。
iDeCoを実践!運用してきたお金はどう受け取る?
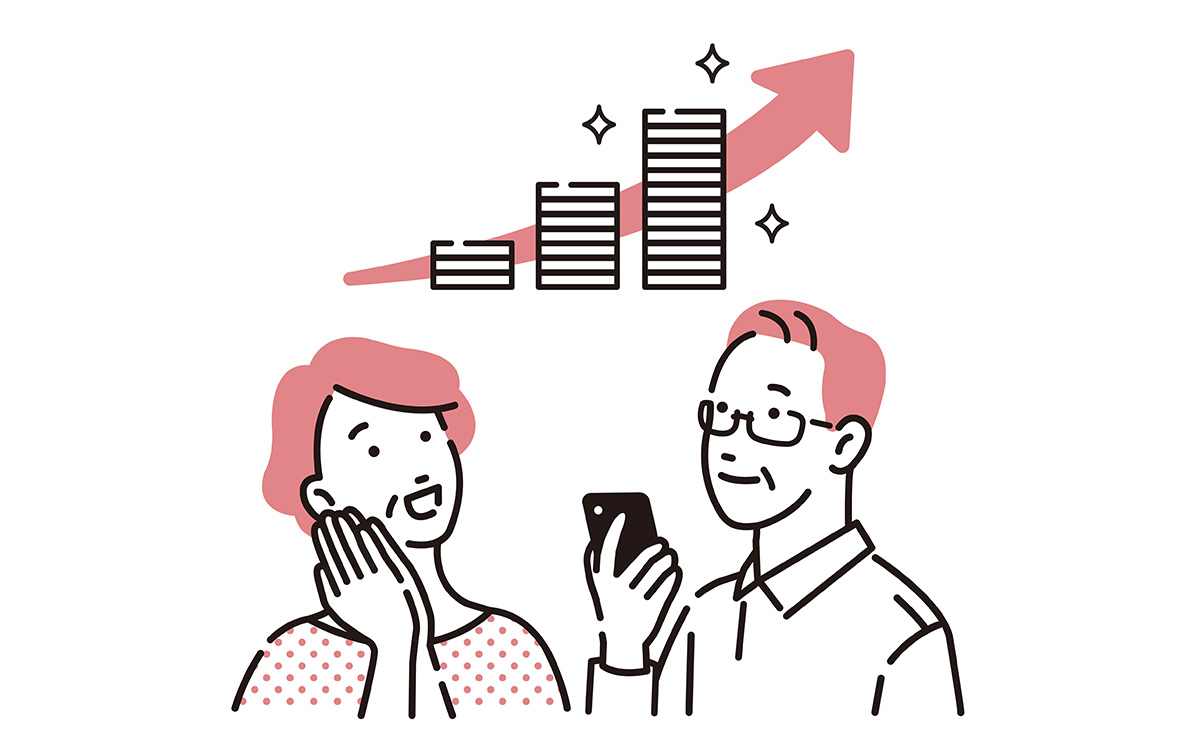
最後に、運用してきたお金を受け取る方法を簡単に紹介します。なお、70歳(2022年4月からは75歳)までに受け取りを開始する必要があります。
受け取り時は、原則課税される
iDeCoでは、運用してきたお金を受け取るときは原則課税されます。ただし、一時金で受け取るときには退職所得控除、年金で受け取るときには公的年金等控除の対象になりますが、一定期間内にほかの退職金など受け取るとそれも考慮しなくてはなりません。そのため、公的年金や退職金などと合わせて受け取り方を検討することが大事です。「いつから受け取りを開始するか」「一時金と年金のどちらかを選ぶか」「年金と一時金を組み合わせる場合に割合をどうするか」などを、老後のライフプランに合わせて考えましょう。
自分にとって最適な給付方法を考える
iDeCoについては、加入期間や受け取る金額、他にも受け取る退職一時金や企業年金などがあるかどうかによって、一人ひとり事情が異なります。受け取り方について正解はありません。自分にとっての最適な給付方法を考えて選択しましょう!
まとめ
iDeCoは、節税しながらコツコツと長期的に老後資金を作っていく、おトクな制度です。少額からでも始めておくことをおすすめします。始める場合は、運用する商品の見極め、金融機関の選定を慎重に行いましょう。将来を見据えて、早い段階から老後資金を賢く貯めましょう!
書籍紹介:『[改訂新版]一番やさしい! 一番くわしい! 個人型確定拠出年金iDeCo活用入門』(竹川 美奈子著/ダイヤモンド社)2021年12月出版
![『[改訂新版]一番やさしい! 一番くわしい! 個人型確定拠出年金iDeCo活用入門』(竹川 美奈子著/ダイヤモンド社)2021年12月出版](/wp-content/uploads/2022/03/N-245_book.jpg)
出版社書籍紹介:『[改訂新版]一番やさしい! 一番くわしい! 個人型確定拠出年金iDeCo活用入門』(竹川 美奈子著/ダイヤモンド社)2021年12月出版
・Amazon
・楽天ブックス
・紀伊國屋書店
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事


























