
仕事や暮らしの中で活きる!生活をより良くするための「交渉」の基本を学ぼう
そこで今回は、慶應義塾大学総合政策学部教授である印南一路氏の著書『交渉学が君たちの人生を変える』(大和書房)より、仕事でも暮らしの中でも活かせる「交渉」の基本をご紹介します。

目次
交渉ってなんだろう
「交渉」と聞いて、皆さんはどのようなイメージをもちますか?テレビの刑事ドラマなどでよく見る「駆け引き」が思い浮かび、堅苦しくて少しネガティブなイメージを持つ方も多いかもしれません。ですが、友達との旅行の打ち合わせ、家族旅行、会社の会議など、普段の生活の中で私たちは何気なく「交渉」をしているのです。
交渉という言葉には、先ほどの例にも上げたように「駆け引き」という意味があります。そのことから、情報操作や意識操作など高度なテクニックを駆使して、1つのものを奪い合って勝ち取るもの、というイメージがついてしまうのです。
ですが、実際の交渉では「駆け引き」をするよりも、相手と仲良くすることでお互いの利益を大きくする、というケースの方が多いでしょう。
また、交渉力というと、大柄で声が大きく、押しのきくタイプを想像しがちですが、外見と交渉力にはほとんど関連がありません。相手の立場にたって冷静に問題を分析できる力と、相手を信頼する気持ちのほうが大事なのです。ですので、交渉力は練習をすることで誰でも身につけることができる力でもあるのです。
交渉をする前に、もとになる考え方やタイプを学んでおきましょう。難しく考えなくても大丈夫。どれも「これを買いたいな」と思ったときに頭によぎっていた事のはずです。交渉にはこれらが影響しているのだと知っておくだけでも、話し合いの場で頭が整理しやすくなりますよ。
ここからは、交渉の基本的な考え方と、そのタイプをご紹介していきます。

4つの考え方とは
交渉の基本的な考え方は、大きく分けて4つあります。
①期待・意欲度
②留保価格
③BATNA(バトゥナ)
④交渉ゾーン
聞き慣れない単語ばかりですが、例をあげて一つ一つ見ていきましょう。
①期待度・意欲度
商品などを「買いたい」人にとって、お店の人が「売りたい」と強く思っていれば話はスムーズですよね。例えば自動車販売店の決算セール中のお店では、「決算だからなんとしても売りたい!」という売り手側の思いが強いため、買い手側の希望が通りやすくなります。逆に、自分が「何が何でも欲しい」ものがあったときは割高でも買ってしまいますよね。
この、「買いたい」「売りたい」という気持ちがどのくらいの程度かを「期待度・意欲度」と言います。
②留保価格
自分が受け入れられる最低レベルの価格のことをいいます。スーパーや家電量販店などに行ったときに、「この商品にはここまでの金額が出せるな」と無意識に考えていることでしょう。もし買いたいとしても、支払える金額を超えていたら、交渉そのものが発生しないということです。それだけ価格というのは、重要な判断の要素になるのです。
③BATNA(バトゥナ)
BATNAとは交渉に関する概念のひとつであり、今自分が行っている交渉がうまくいかなかったときのための最良の代替手段のことをいいます。
例えば、海が見える結婚式場Aで式を挙げたいとして、日程の面で交渉をしているとします。このAの式場が希望の日程で契約できなかった場合に備えて、希望の日程が空いている海の見える結婚式場Bにも話をしておく、というイメージです。
これはとても重要な考え方で、例のように代替の式場Bが見つかればよいのですが、式場Aでしか希望がかなえられないならば日程を妥協してでも契約することになってしまうからです。
④交渉ゾーン
買いたい金額と、売りたい金額の差のことです。この差が発生していることで、お互いに少しずつ歩み寄ることができるのです。
例えば、中古の自動車販売店で、「50万で買いたい」あなたと「60万で売りたい」お店側でしたら、この10万円の差が「交渉ゾーン」です。
やってはいけない方法
話し合いの場では、相手が話をしていることを黙って聞いていた方が良いと思っている方も多いのではないでしょうか。実はこの振る舞いが、「黙って聞いて粘れば、相手が折れる」ことを期待している傲慢な態度として捉えられかねないのです。良かれと思ってやったことが、相手にとってネガティブなイメージになってしまうこともありますので、相槌を打ったり、質問するなどコミュニケーションを取ると一方的にならず良い印象で交渉が進みますよ。
3つの交渉タイプを知ろう
ここまでで交渉の基本的な考え方をご紹介してきましたが、ここからは実際の交渉においてどのようなタイプがあるのかを大きく3つのタイプに分けてご紹介していきます。
①分配型
海外など見知らぬ土地の露天商で、何かの商品を値引きしながら購入する例が典型で、一般的な売り買いの形です。分配型は一度きりの交渉(取引)であるため、商品の保証や交換などは不可能であることがほとんどです。
②利益交換型
自分にとって必要なものを手に入れるために、それほど重要ではないものを譲るという交渉のタイプです。譲るものが自分にとっては重要でなくても、相手にとっては重要である、ということがポイントです。ことわざでいうなら「損して得取れ」と同じで、長い目で見ると得になるということですね。
③創造的問題解決
新しい解決方法を作り出して、問題そのものをなくしてしまうタイプのことです。
例えば、家を買う時に一人は広いキッチンが欲しい、片方はリビングにワークスペースが欲しいと揉めているとします。そこで不動産屋さんから「キッチンの隣に作り付けのデスクを設置すれば、ワークスペース兼作業台として使えますよ」という提案を受けたという解決方法がこれにあたります。
ほとんどの交渉ではこの3つのタイプをすべて含んでおり、お互いがどのタイプなのか分かっていれば、交渉はスムーズに運びやすいのです。
さぁ、交渉を始めましょう!
交渉の基本的な考え方とタイプを見てきたところで、いよいよ実際の交渉に取り掛かりましょう。交渉のテクニックはたくさんありますが、重要なポイントをいくつか知っているだけで、こちらのペースでスムーズに話し合いができるようになりますよ。

事前の準備が結果を左右する
まず、これから行うとする交渉がうまくいかなかった場合に備えて、あらかじめ用意した代替手段があれば、交渉がうまくいかなかった場合でも大きな損失はないでしょう。
これは、交渉の基本で見た③BATNA(バトゥナ)という考え方ですが、代替手段の業者や店舗の担当者ともきちんと交渉をする必要があります。代替といっても、本気で話をしないと相手に失礼になってしまいますし、交渉のもととなる値段や条件も出してもらえません。そのような交渉が面倒であればネットで調べて情報収集しておくだけでも、「あの店ならこの金額で売ってくれそうだな」という一般的な相場や条件がわかるので、いざ話し合いになったとき心に余裕を持つことができますよ。
判断の基準点「アンカリング」とは
交渉と言えば値段のことが問題になることが多いですが、具体的な値段の話をするときには注意が必要です。一度値段を提示してしまうと、そこを基準に話が続くことになり、その基準を無かったことにすることが難しいからです。
このように判断の錨(いかり)を下ろすことを「アンカリング」といいます。
例えば、「ご予算はおいくらですか」と聞かれて、実際の予算よりも高い値段を言ってしまうと、その予算額から交渉がはじまるので、実際には払えない金額でうっかり契約してしまう、ということが起きてしまいかねないのです。
こちらが最初に提示する希望の値段は、相手が「売っても良いかな」と思うギリギリを狙うことが効果的ですが、見極めることは難しいですよね。
そんなときに、代替手段の業者さんから引き出した金額だったり、事前調査した相場などを参考にして交渉をしていくのです。
大事なのは信頼関係
人は、「この人とは長いお付き合いになりそうだな」と思うほど、悪意・害意のある行動は取りにくくなります。一見、もう二度と会わない人・行かないお店だからと思っても、一回きりの関係というのは、実はそれほどありません。特にお店としては、また買って欲しい、口コミや評判を大事にしたいと思う心理が働いているからです。
では、信頼関係を築くにはどうすればよいでしょうか。それはお互いに、相手に伝えても問題にならない情報を少しずつ伝えることです。情報を伝えることで相手も一定の情報を出してきてくれますが、反対に、疑心暗鬼になって何も情報を出さない態度をとると、それが相手に伝わり、相手も同じ態度をとってくるようになってしまうのです。
そうなってしまうと、お互いに不信感だらけになってしまい交渉がうまくいくはずもなくなってしまいますので、とにかく相手をリスペクトし、自分を信じてもらえるような関係を築きましょう。
相手から身を守るためには
信頼関係を築くことは大切ですが、なかには誤解させたり、嘘を織り交ぜたり、また情報を操作しようとする人がいるのも事実です。
例えば、仕事は暇なのに忙しいフリをする、SNSにアップする画像をちょっと盛ってみたりするといったことは、日常的になんら罪に問われることもなく行われていますよね。
こういった「ちょっとしたワナ」が、交渉の場でも行われていますので、自分にとって不利にならないよう「気づく」ことが大切なのです。
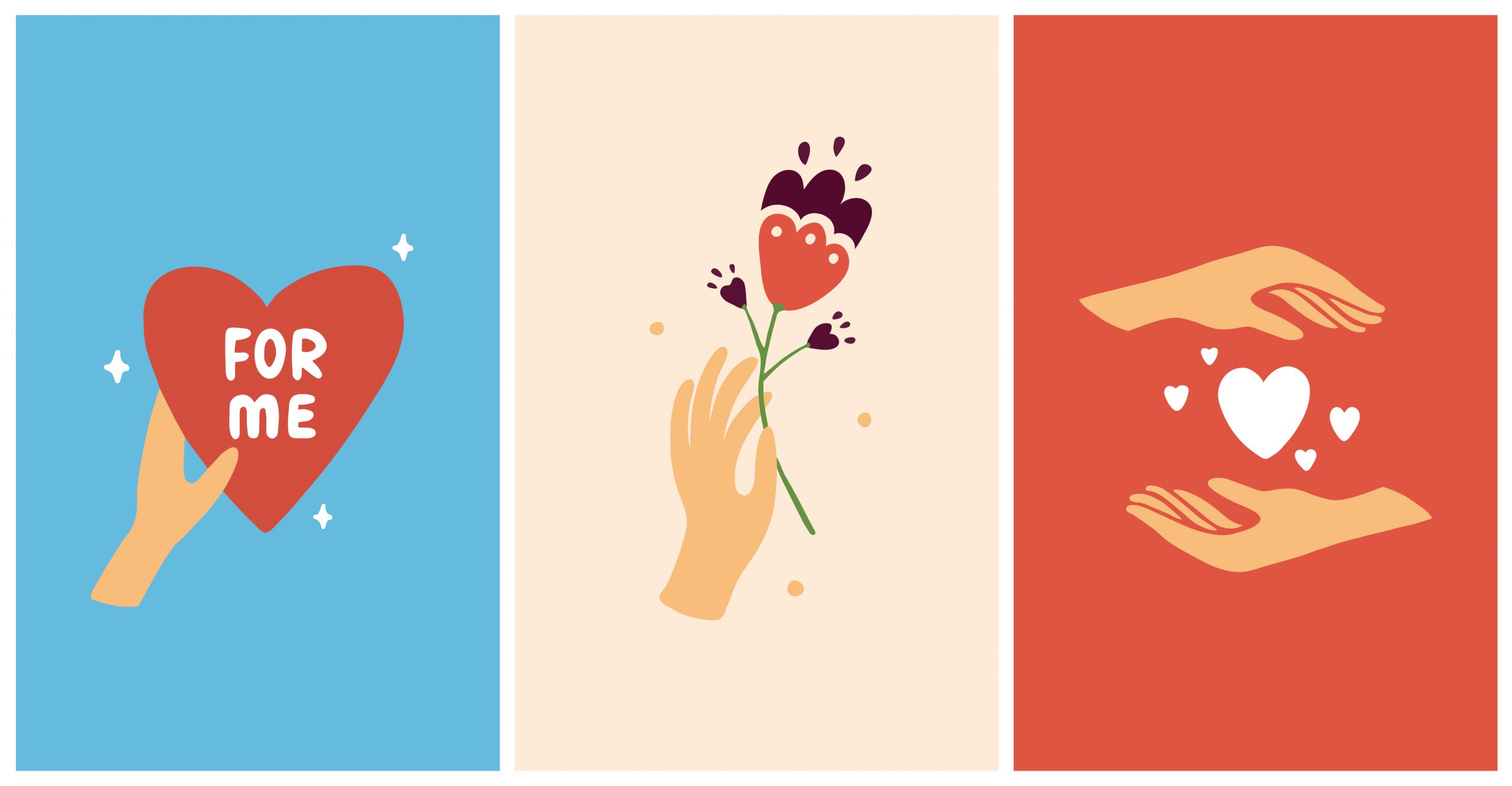
意外なところに罠が潜んでいる
相手から譲歩を引き出すために①「好意を利用するもの」と②「返報原則を利用するもの」があり、日常の風景でもよく見られます。
①「好意を利用するもの」は、セールストークの基本でもあるため思い浮かぶ人も多いのではないでしょうか。服屋さんなどの、「お似合いですよ!」「お客様にピッタリです!」という言葉はまさにこの交渉術が使われています。
②の「返報原則を利用するもの」とは、相手に良くしてもらったことに対してこちらも良くしてあげたいと感じる心理を利用した交渉術のことです。頼まれごとというのは、なかなか断りにくいものですが、とくに日頃から気がきいた手助けやサービスをしてくれる人には強く出にくいですよね。「プレゼント」を貰うことも判断を狂わせる1つとも言えるので、交渉事のときはペースにのまれないよう注意しましょう。
「今だけ」という言葉に惑わされない
「あと1点だけです」「セールは今だけ!」など、急かすような言葉を聞いたことはありませんか?悪気もなく、ただ単にあなたの背中を押すものとも言えますが、状況によっては正しい判断ができなくなってしまう可能性があるのです。
購入を決断させるものには「抽選で当たる!」という見返りがあるタイプや、「今だけ!」と謳い、手に入らなかった未来を想像させるタイプがあります。人は失うときのほうが譲歩してしまう傾向がありますので、そういった言葉には惑わされないよう注意することが大切ですよ。
気づいたら不利になってるかも
インターネットで欲しい商品を見つけたので、お店に行ってみたら「それは売り切れましたが、別のものがありますよ」と、そこまで好きではないものを勧められたとします。せっかくお店まで来たのに何も買えないなんて…と、本当は気に入ってないのに「損をしたくない」「自分は間違っていない」という思いが強くなり、買ってしまうというケースがあります。
また、最終コストよりも見かけ上低い価格を提示されることがあります。これはローボーリングと呼ばれ、例えば、あなたがおトクだと思って「買います」と言った後に、後から付属品やサービスプランを説明され、結局高くついてしまうというケースのことです。
このように、人はいったん意思決定をすると、その後は決断が正しかったと思い込んでしまう傾向があります。契約の最後までいく前に、最初に想像したよりもコストが掛かっていたとしても、途中で自分でストップをかけることは意外にも難しいのです。
良くない交渉をリセットするには
前述の通り、途中でよくない話し合いだと気づいたとしても、始まってしまった話を止めることは簡単ではありません。そこで、交渉をスムーズにする手軽な方法があります。

パートナーと2人で出かけて、1人は商品を買いたい役を、もう1人は冷たく言って足を引っ張る役を演じるのです。売る側は、片方が商品購入に熱心なので、買ってもらえるのではと期待するので交渉をやめられず、同時にもう片方の厳しい要求にも答えなければなりません。また、1人が話す役に集中でき、もう1人は客観的に状況をチェックできることで、正しい判断がしやすくなります。
1人で交渉する場合でも、自分が思ったよりも不利な状況になってしまったら、権限がない振りをして、交渉全体を仕切り直すことができます。例えば、話し合いの最後で「家族に相談してみます。また来ますよ」と言って交渉を打ち切ることができます。これは、準備としての下調べ段階で、話はしたいけど最終決定はしたくないときにも使えますよ。
まとめ
その言葉のイメージから、「交渉」にネガティブな印象を持ってしまう方も多いですよね。ですが、ものを買うときだけではなく、仕事やプライベートといった日常生活でも交渉は無意識に行われています。
交渉は1つのものを奪い合うものではなく、お互いがより幸せになる方法を一緒に見つけ出す作業です。そのためには、お互いの信頼関係が何より大事になってきます。気をつけなければならないこともありますが、交渉の基本を知り、より良い生活を送りましょう。
書籍紹介:「交渉学が君たちの人生を変える」(印南一路 著 / 大和書房 )2018年12月出版
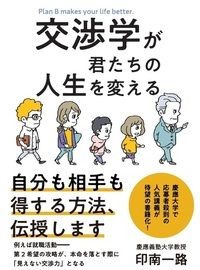
出版社書籍紹介:「交渉学が君たちの人生を変える」(印南一路 著 / 大和書房 )2018年12月出版
・Amazon
・楽天ブックス
・紀伊國屋書店
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事


























