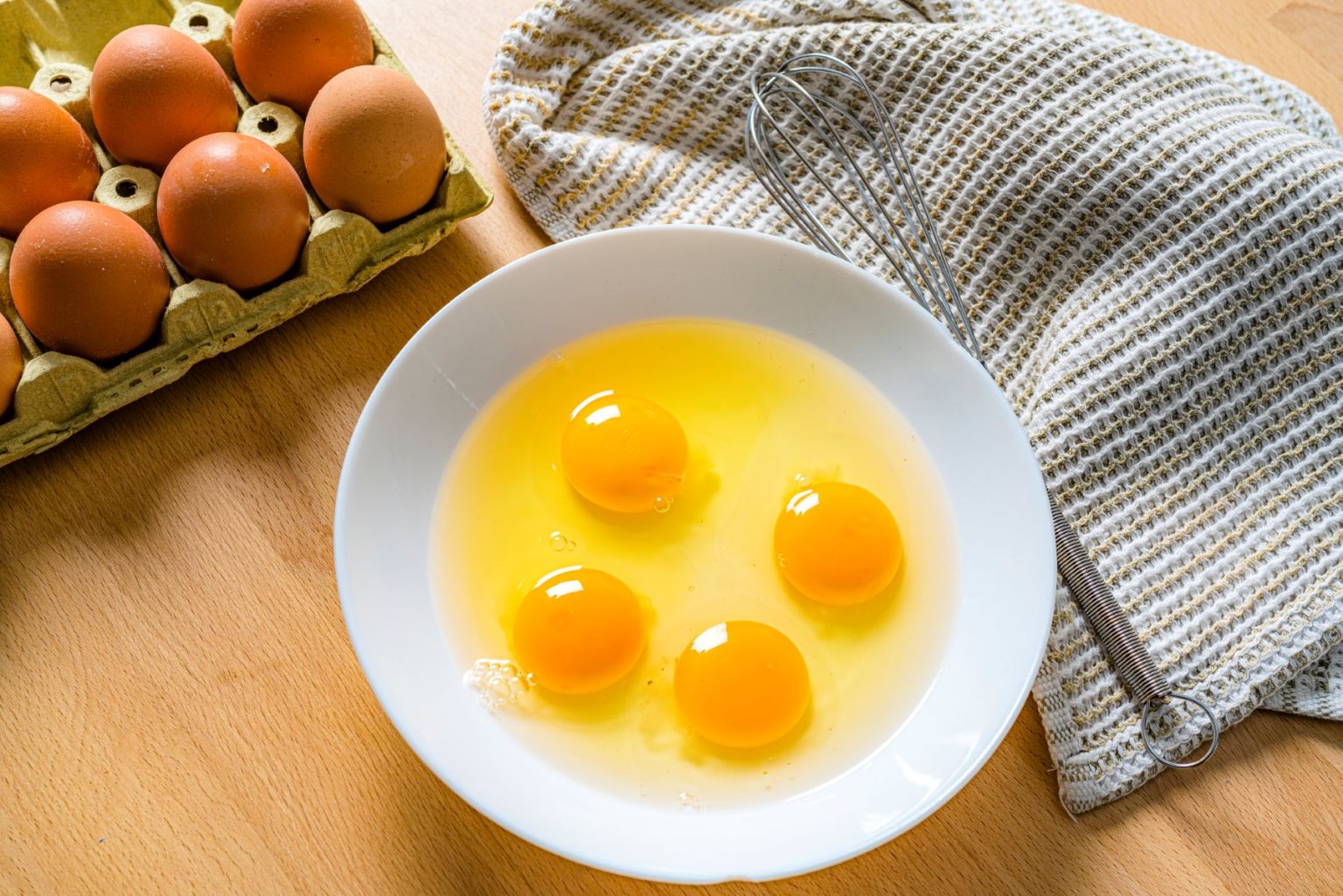
管理栄養士監修:卵の豊富な栄養素とその効果を解説!
この記事では、卵に含まれる栄養素とその効果を詳しく解説します。また、栄養を最大限に活かす調理法や、おすすめのレシピもご紹介します。
監修者
- 端場 愛(はしば あい)
- 管理栄養士・栄養食育ライター
中高生から高齢者まで幅広い世代の栄養管理に従事。食べ物と体の関係を分かりやすく伝えるために、栄養食育ライターとして活動中。“今日よりもちょっとだけ健康になれるような情報”を提供するのがモットー。

目次
卵は栄養価が高い完全栄養食品
卵は「完全栄養食品」と呼ばれるほど栄養価が高く、ビタミンCと食物繊維以外のほぼすべての栄養素を含んでいます。とくに、タンパク質や脂質(コレステロール)が豊富です[1]。
なお、卵黄と卵白では含まれる栄養素が異なります。ここでは、さらに細かく卵に含まれる栄養価を見ていきます。
白身より黄身の方が栄養価は高い
卵は、主に「白身(卵白)」と「黄身(卵黄)」に分けられます。卵黄には、ヒヨコに成長するための栄養が詰まっており、白身よりも栄養価が高いです。
卵白(白身)に含まれる栄養素と特徴
- 良質なタンパク質(アルブミン)
- 脂質はほとんど含まず低カロリー
卵黄(黄身)に含まれる栄養素と特徴
- 脂溶性ビタミン(A・D・E・K)
- 水溶性ビタミン(B群・葉酸)
- ミネラル(鉄・亜鉛・セレン)
- レシチン
- コリン
- ルテイン・ゼアキサンチン
薄皮やカラザにも栄養は含まれている
黄身の周囲の薄皮には、ヒアルロン酸やコラーゲンの元となる成分が、卵黄を卵の中央に固定する役割を持つ白いひも状のカラザには、リンや鉄などのミネラル、ビタミンB群が含まれています。
薄皮やカラザごと食べれば、卵の栄養素を余すことなく摂取できます。ただし、その量はわずかなため、無理に食べる必要はありません。

卵に含まれる代表的な栄養素
Mサイズ(58g~64g)[2]の卵に含まれる栄養素を解説します。
卵に含まれる主な栄養素の含有量は以下のとおりです。一般的な卵は、卵白60%、卵黄30%、卵殻10%で構成されているため[3]、卵の重さを60gと仮定し、全卵54g、卵白36g、卵黄18gで算出しました。
| 栄養素 | 全卵 (54gあたり) |
卵白 (36gあたり) |
卵黄 (18gあたり) |
|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 77 | 16 | 60 |
| タンパク質(g) | 6.6 | 3.6 | 3.0 |
| 脂質(g) | 5.5 | Tr | 6.2 |
| 炭水化物(g) | 0.2 | 0.2 | 0 |
| カルシウム(mg) | 25 | 2 | 25 |
| 鉄(mg) | 0.8 | Tr | 0.9 |
| ビタミンA(μg) | 110 | 0 | 120 |
| ビタミンD(μg) | 2.1 | 0 | 2.2 |
| ビタミンE(mg) | 0.7 | 0 | 0.8 |
| ビタミンB2(mg) | 0.20 | 0.13 | 0.08 |
| コレステロール(mg) | 200 | 0 | 220 |
出典:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」[1]を参考に作成
タンパク質
タンパク質は、筋肉や血液、骨、皮膚、髪など体をつくるために欠かせない栄養素ですが、卵は、良質なタンパク質を含むアミノ酸スコアが100の食品です。
アミノ酸スコアとは、タンパク質を構成するアミノ酸のバランスを数値化したもので、数字が大きいほど良いとされています。卵のほかには、肉類・魚介類・牛乳などがアミノ酸スコア100の食品に該当します。
卵には体に必要な9種類の必須アミノ酸がバランス良く含まれています。必須アミノ酸は体内で生成できないため、卵を食べることで効率良く摂取できます。
脂質
脂質は、効率の良いエネルギー源であり、適度に摂取したい栄養素です。卵には、コレステロール(脂質)も含まれており、とくに、脳の発達や神経細胞の形成に重要な「リン脂質」や「DHA」などが豊富です。
卵は「コレステロールが多いから控えるべき」といわれることがあります。しかし、卵には悪玉コレステロールの値を低下させる作用がある「リノール酸」や「オレイン酸」「レシチン」なども含まれています。そのため、最近の研究では、少量であれば、卵のコレステロールと血中コレステロール値の関連性は低いとされています。
1日に2個程度なら食べても問題ないといえるでしょう。卵の目安量については後述の「▼卵は1日2個程度が目安」で詳しく解説します。
ビタミン
含有量には差があるものの、卵にはビタミンC以外のビタミンが含まれています。とくに多いのは、ビタミンAやビタミンDです。
ビタミンAは、視覚の発達や皮膚の健康維持、免疫機能の強化に役立ちます。また、ビタミンDはカルシウムやリンの吸収を助け、骨や歯の形成に必須の栄養素です。
ミネラル
ミネラルでは、カルシウム・鉄分・亜鉛・マグネシウム・セレンなどが多く含まれています。
鉄分は、酸素を全身に運ぶヘモグロビンの生成に必要な成分です。とくに、卵黄に多く含まれ、植物性の鉄分より吸収率が高いのが特徴です。亜鉛は味覚の発達や免疫機能の強化、タンパク質合成に関わります。セレンは、抗酸化作用があり、免疫力の向上に貢献します。
ミネラルは、健康を保つのに必須の栄養素ですが、体内で生成ができないため、食物から摂取しなければいけません。多くのミネラルを含む卵は、ミネラルを効率良く摂取することにも役立ちます。

卵は1日2個程度が目安
明確な基準は定められていませんが、1日あたりの卵の摂取量は、健康な方であれば、1日2個程度を目安とすると良いでしょう。
卵はコレステロール含有量が多いため、過去には1日1個までという説が一般的でした。しかし、「卵に含まれるレシチンやオレイン酸にコレステロール値を下げる働きがある」「食事で摂取するコレステロール量は、血液中のコレステロール量に必ずしも影響を与えるわけではない」といった理由から、現在ではそこまで気にする必要はない、という説が一般的です。実際に、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」でも、コレステロールの目標摂取量(上限値)の記載は撤廃されています。
ただし、卵のコレステロール含有量が減ったわけではないため、食べ過ぎには注意が必要です。とくに、脂質異常症と診断されている方や、LDLコレステロール値が高い方は1日1個までにした上で、食べる頻度を減らすなどの工夫をしましょう。
また、栄養のバランスを考えた食生活のためには、卵のみならず、野菜類・果物類・魚介類・肉類・乳製品などをバランス良く食べるのが大切です。
卵の栄養素を無駄なく摂るコツ
栄養素には、熱に弱い・水に溶けやすいなどの特徴があり、調理法や他の食材や調味料との組み合わせによって栄養素の摂取効率が変わります。
例えば、脂溶性ビタミン(A、D、E)は、油を使った調理法で吸収率が向上し、水に溶けやすい水溶性ビタミンはスープなど煮汁ごと食べる料理にするとムダなく摂取できます。
ただし、卵には脂質が含まれているため、料理で油を使わなくても大丈夫です。また、水溶性ビタミンも、殻のまま加熱するゆで卵はあまり流出しないため、そこまで気にする必要はありません。
卵料理を日々の食事に取り入れて、効率良く栄養を摂りましょう。
おすすめの卵レシピ5選
ここでは、卵を使った簡単レシピをご紹介します。
切り干し大根とベーコンのオムレツ

食物繊維が豊富な切り干し大根とベーコンの旨味が、卵と絶妙にマッチした一品です。朝食やブランチにぴったりで、作り方も簡単です。
ゆで卵の牛肉巻き照り焼き

柔らかな食感のゆで卵を薄切りの牛肉で包み、甘辛い照り焼きソースで味付けした、見た目も華やかな一品です。お弁当のメインディッシュとしても、夕食のおかずとしても活躍します。
ブロッコリー入りかきたまうどん

寒い日に体を温める、やさしい味わいのかきたまうどんです。ふわふわの卵とシャキシャキのブロッコリーが絶妙なハーモニーを奏でます。栄養バランスも考えられたこの一品は、簡単に作れて満足感も高く、忙しい日の夕食や小腹が空いた時のランチにぴったりです。
小松菜入りツナ玉丼

栄養豊富な小松菜と卵、旨味たっぷりのツナを組み合わせた、栄養バランスに優れた丼物です。緑黄色野菜の小松菜からはカルシウムや鉄分、卵からは良質なタンパク質、ツナからはDHAが摂取できる、一品で栄養満点の料理です。
さつま揚げ入りにらたま

にらの食欲をそそる香りと卵のふんわりとした食感、さつま揚げの旨味が絶妙に調和した「さつま揚げ入りにらたま」。さつま揚げをプラスすることで食べ応えがアップし、より満足感のある一品に仕上がります。シンプルながらも深い味わいが楽しめる家庭料理をお試しください。
まとめ
卵は手軽に入手でき、多様な調理法に対応できる高栄養価食品です。タンパク質やコレステロールをはじめ、ビタミン、ミネラルなど、健康を維持するために必要な栄養素を豊富に含んでいます。
ただし、卵は食物繊維とビタミンCを含まないため、卵料理を作る際は、これらを補う食材を合わせることで、よりバランスの取れた食事を摂ることができます。
卵の栄養素を理解したうえで、本記事で紹介したさまざまなレシピを試してみてください。
-
文部科学省:
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 電子書籍(第2章を除く)[PDF] -
日本卵業協会:
タマゴQ&A -
日本養鶏協会:
たまごQ&A/たまごの知識
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「東京電力 くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事


![[くらしTEPCOエアコンクリーニング(SP)]](/wp-content/uploads/2025/04/エアコンクリーニング_pickup_600×300_250926-_min.png)
![[電化でかしこくおトク!くらし応援キャンペーン(SP)]](/wp-content/uploads/2025/12/sidebar_denkiplan-cp.png)
























