
親子関係を円満にする 感情的にならない話し方
家族も自分も傷つけずに円滑なコミュニケーションを育むためには、「感情的にならない話し方」を意識して使いましょう。精神科医・和田秀樹氏の著書『感情的にならない話し方 人間関係でもう失敗しない!』(知的生きかた文庫・三笠書房)をもとに、親子関係を円満にする話し方を紹介します。
目次
トラブルを防ぐ話し方の三原則

家族に対してイライラしてしまうことは、親側にも子ども側にもあることでしょう。人間は感情の生きものなので、感情的になるのは仕方ありません。
ただし、どんなに感情的になっても、怒鳴ったり傷つける言葉を口にしたりと、その感情を行動化してはいけません。なぜなら、許される範囲を超えた行動は、トラブルに発展するからです。
感情的にならないためには、3つのルールを意識しましょう。これらを心がけていれば、一瞬の油断で感情的になったとしても、すぐに修正ができるはずです。
1.感情を態度や行動に表さないこと
「相手を怒鳴らないこと」「相手を傷つける言葉を口にしないこと」を、最低限のルールとして守りましょう。
たとえ意見が食い違って口論になっても、大声を出したり、言われて傷つく言葉を口にしたりしないと決めていれば、地雷を踏むことはありません。同時に、相手から感情的な言葉を投げつけられたとしても、感情を態度や行動に表さないと決めていれば、怒っている相手を「どうしようもないな」と冷静に見つめることができます。
双方が怒りに任せてしまうと、お互いに引っ込みがつかなくなってしまうので注意しましょう。
2.リラックスして話すこと
いい雰囲気の時間は何も気にせずに会話がはずむように、嬉しいときや楽しいときは、喜びの感情を素直に出すことで共感が高まります。意見を出し合うときも同じで、相手が自分の意見を主張したら、自分も熱くなって構いません。
ただしそのときも、負の感情が表れないように心がけ、頭の中を整理して論理的な思考を保ちましょう。相手の話を聞いて意見を返すときは、カッカして身構えるのではなく、心をゆったりとリラックスさせましょう。
3.話の目的を忘れないこと
話し合いをしていたはずなのに、気づいたら「どうにでもなれ」と、話が宙に浮いてしまった経験はありませんか。感情的になると、怒りにまかせてつい乱暴な結論を出してしまい、「そんなつもりはなかったのに」と後悔する原因になります。
そうならないためには、どんなときでも「なぜ話し合っているのか」「話し合いの目的はなんなのか」を心に留めておきましょう。すると、たとえ感情的になったとしても、怒りに振り回されずに話を元に戻せるはずです。
イライラさせたのはどっちのせい?

家族との会話で感情的になって、「ちゃんと聞くつもりだったのに」「腹が立ったのはあっちのせいだ」とイライラした経験はありませんか。でも、本当に原因は相手だけにあるのでしょうか。険悪なムードにならないための、イライラと上手に付き合う方法を紹介します。
1.どっちのせいか考えても無意味
人と話していて感情的になってしまう原因は、大きく2つあります。それは、自分がイライラしているときと、相手がイライラしているときです。
たとえば、相手に話しかけられて「忙しいんだけど!」と返して口論になったとします。このとき、感情的に答えた原因は、忙しいときに声をかけた相手にあるのでしょうか、それとも、忙しくてイライラしていた自分にあるのでしょうか。
会話は一対一ですることが多いので、片方が感情的になれば、もう片方も冷静ではいられなくなります。話が感情的になったときは、お互いに「相手のせい」と思っているので、「どっちのせい」と答えを求めても意味はありません。自分から話し方を工夫しましょう。
2.言葉は感情のやりとり
相手に断定的な言い方をされたり、見下したような態度を取られたりしたら、理屈では納得できていたとしても、反発が生まれます。対して、穏やかで感情を解きほぐしてくれるような話し方をされたら、ちゃんと聞く気持ちになります。
つまり人間は、理性のフィルターよりも、感情のフィルターのほうが強く働くのです。言葉のやり取りは、意見や考えだけではなく、感情のやり取りの部分が大きいと覚えておきましょう。
とはいえもちろん、感情をすべて抑え込む必要はありません。感情を交えない話し方は魅力がなく、冷淡な印象を与えるからです。嬉しさや楽しさなどの前向きな感情は素直に表しましょう。
3.会話の流れは変えられる
会話の流れの中で、うっかり相手を傷つけたときや、自分が感情的になったときは、素直に謝って訂正しましょう。「自分は正しい」「相手が間違っている」と論理的に言い負かしたところで、相手が自分を拒絶していれば納得させることはできません。
さらに、相手を感情的にさせないことも大切です。ほとんどの人が、自分の意見や考えをきちんと聞いてもらえれば、感情的になることはありません。
自分が正しいとの思い込みを捨て、相手の話を聞く姿勢を心がけてみてはいかがでしょうか。ときには、「気に障ったら許してほしい」「ちょっと言い過ぎたかもしれない」といった一言で、会話の流れがいい方向へ変わることもあるのです。
感情を解きほぐす3つの話し方
家族間はもちろん、人間関係の理想は、言いたいことを言い合える仲です。思ったことを口にできるのは、相手を嫌うためではなく好きになるためであり、信頼を生み出すことにつながるからです。
ここでは、もしも相手が感情的になってしまった場合に、言葉のやり取りをスローダウンさせ、ゆっくりと話すための方法を紹介します。
1.沈黙で間を置く
相手が一方的に自分の考えを押し付けてきたときに、自分が返事をしなければ会話はストップします。そして、短い時間でも間が生まれると、感情がエスカレートするのを防ぐことができます。
反論すれば、ぶつかり合いとなり、こちらも感情的になってしまう可能性があります。しかし、こちらが沈黙すれば、相手は感情的になっている自分に気づき、「言いすぎたかな」と反省するかもしれません。
ほとんどの人は、沈黙に出会えばその意味を考えます。「どうして返事をしないのだろう」と思わせることで、感情を落ち着かせることができるのです。
2.「〇〇と思う」とやわらかく応じる
感情的になると多くの人が、「○○だろ」と断定的な話し方になります。すると、こちらはその意見に従うか、「それは間違いだ」と強い口調で反論するしかなくなります。つまり、断定的な口調の相手へ断定的に返しても、双方が感情的になってしまうだけなのです。
断定的な相手には「〇〇と思う」と応じてみましょう。同じ反論でも、「思う」を付け加えるだけでやわらかい口調となり、ワンクッション置くことができます。しかも、「思う」はあくまでも自分の考えなので、相手の意見の否定になりません。
3.「それだけかなあ」で気づかせる
自分の考えに固執しているときは、ほかの可能性が見えなくなり、「絶対にこうだ」と思い込んでしまいます。そうした状態の相手を咎めたり説得したりしても、怒りが自分に向かってくるだけで手がつけられません。
そんなときは、「たしかにそう言えるかもしれない」と相手の考えを認めたうえで、「ほかにも可能性がある」と伝えましょう。「それだけかなあ」「それもあるだろうけど」といった言葉を使うことで、相手を落ち着かせつつ意見することができます。
相手を受け止めてから話をしよう

家族に対して「なんでわかってくれないんだ」と、不満を覚えたことはありませんか。
自分の気持ちや考えをわかってもらえないとき、人は感情的になってしまいます。
ここでは、相手の性格を受け止めながら、感情的にならずに話を進める方法を紹介します。
1.相手への要求水準を下げる
学歴の高い親ほど子どもの成績に満足しないように、要求水準が高い人ほど、感情的な人間関係を作りやすくなるものです。感情的にならないためには、相手への要求水準を下げるように意識しましょう。
これは決して、人に期待するなという意味ではなく、「こうでなければいけない」「こうすべきだ」との思い込みを捨てるという意味です。
人によって、考え方や性格、得意分野は違います。自分にとって当たり前のことでも、相手にとっては当たり前ではないというケースはいくらでもあるのです。
2.受け入れてから話し合う
相手が自分とは違うやり方を選ぼうとしても、「違う」「そうじゃない」といった言い方はせず、「いろいろなやり方がある」と見守りましょう。
ポイントは、相手の意見とやり方をひとまず受け止め、具体的な話に入ることです。「そういうのもあるね」と受け入れれば相手は安心し、「ちゃんと話ができる」とリラックスするはずです。
それから、「自分の考えはちょっと違うんだ」と切り出せば、頭ごなしに言われるよりも、聞く耳を持ってくれるはずです。
3.やってみようと励ます
親が子どもを「そんなこともできないの」と叱るときには、自分が子どもの頃はどうだったかを忘れています。同様に、できる人ができない人に不満を持つときは、自分にもできない時期があったことや、不得意な分野があることを忘れているのです。
自分が思うほどに何かができていない相手に対しては、できなくても仕方がないという気持ちで、「できなくても気にするな」「できるところまでやってみよう」と励ましましょう。すると、相手はリラックスすることができ、お互いがいい感情で満たされるはずです。
相手への要求水準を下げれば、心の余裕が生まれることを知っておきましょう。
まとめ
人間は感情の生きものなので、感情的になるのは仕方のないこと。ただし、怒鳴ったり傷つける言葉を口にしたりすることは、家族とはいえ人間関係において避けるべきでしょう。
感情を行動に表さないためには、「感情を態度や行動に表さないこと」「リラックスして話すこと」「話の目的を忘れないこと」の三原則を意識しておくことが大切です。
また、感情的になった相手に感情的な言葉を返しても、ヒートアップを招くだけです。相手の話を聞く姿勢を心がけ、「沈黙で間を置く」など、感情を落ち着かせる話し方を意識して使うと効果的です。
家族に対しては要求水準を下げ、「できなくても気にするな」「できるところまでやってみよう」と励ますことで、双方に心の余裕が生まれるのです。
引用書籍:『感情的にならない話し方 人間関係でもう失敗しない!』
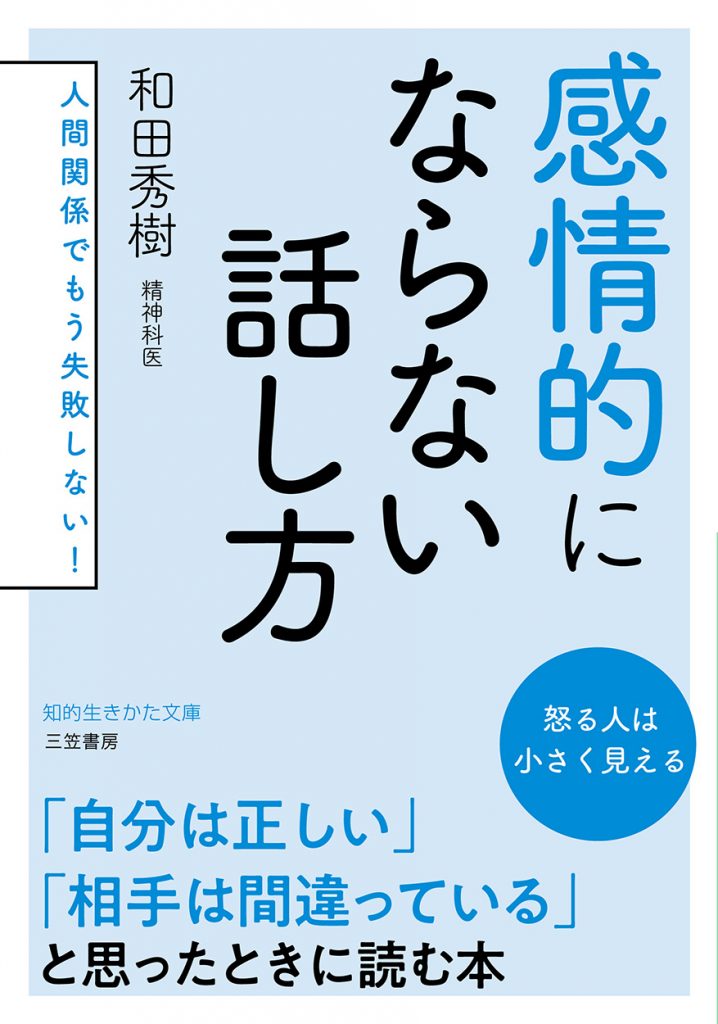
出版社・書籍紹介:『感情的にならない話し方 人間関係でもう失敗しない!』(和田秀樹著/知的生きかた文庫・三笠書房)2020年10月出版
・Amazon
・楽天ブックス
・紀伊國屋書店
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事


























