
寝かしつけに悩むパパ・ママへ! 赤ちゃんの睡眠改善プログラム
今回は日本人初の乳幼児睡眠コンサルタントである愛波文氏(監修 西野精治氏)の著書『ママと赤ちゃんのぐっすり本 「夜泣き・寝かしつけ・早朝起き」解決ガイド』(講談社)より、科学的なエビデンスに基づいた「子供の睡眠」解決プログラムをご紹介します。
目次

子供が眠れない理由とは?
寝かしつけようとしても寝てくれない子供を前に、何を欲しがっているのだろう、何が嫌なのだろうと想像をして、あやしてみたり、声をかけてみたりと試行錯誤している人もいるのではないでしょうか。
ですが、「自分がこれをされたら嬉しいだろう」という大人目線での向き合い方は、子供にとっては眠りを妨げていることが多くあります。
例えば、赤ちゃんは眠っている最中にも少し声をあげたり、一瞬目を開けたりすることがあるという研究結果があります。もしかすると、それに気づかずに声をかけたり抱っこしたりして、寝ている赤ちゃんをわざわざ起こしてしまっていることもあるかもしれません。
また、疲れていればぐっすりと寝るだろうと昼間にたくさん遊ばせてしまうことも、逆効果なことがあります。大人にとって、「疲れていれば眠くなる」というごく自然な体の反応も、子供にとっては眠りを邪魔してしまいます。本来は自然な目覚めを促すホルモンであるコルチゾールは、疲れすぎると過剰に分泌されてしまうからです。
このように、子供は「大人とは違うんだ」ということを頭に入れておくことで睡眠トラブルを減らすことに繋がっていきます。

トラブルを7割改善する「睡眠の土台」
「ねんねトレーニング」という言葉が定着した今、子供をスムーズに寝かしつけて、夜中に起きることもなくぐっすりと寝てくれるようにするためには、第一に「睡眠の土台」を整えてあげることが必要です。
睡眠の土台は「睡眠環境」「親子の幸福度」「生活リズム」の3つからできていて、子供の睡眠を整えるために非常に大切な要素です。
子供は成長段階に合わせて、日中の睡眠回数や食事タイミングがドンドン変わっていきますが、それと同じように、睡眠の土台も継続して調整し続ける必要があるのです。
睡眠の土台をしっかり整えていないと、子供のねんねトレーニングをしても効果をうまく発揮してくれないときがあります。
著者いわく、睡眠トラブルを減らそうとしてねんねトレーニングに取り組まなくても、睡眠の土台が整えば多くの問題が解決することがあり、またなぜ子供が泣いているのかの理由の理解とその対応もスムーズにできるようになるといいます。
眠り続けられる睡眠環境とは?
子供が気持ちよく寝つき、朝まで寝つづけられる環境を整えましょう。
子供はわずかな環境の変化にも敏感なので、寝ついたときから起きるまで、同じ環境が続いているということが重要になってきます。また、睡眠環境は寝るときだけではなく、日中の状況にも影響があるのです。
光や音をコントロールしよう
朝に起きてから日光を15分程度浴びると「セロトニン」という心を安定させるホルモンが生成されます。
そして、睡眠ホルモンである「メラトニン」は、このセロトニンがあって初めて活発に分泌されるようになるのです。メラトニンの分泌は生後3ヵ月ごろから始まりますが、新生児であっても日光を浴びることで少しずつ体内時計が確立し、昼夜の区別がつきやすくなっていくので、朝の日光浴はとても大切です。
また、子供が眠る2時間前にはテレビやタブレットなどブルーライトを発するものは見せないようにするのが理想的です。ブルーライトを見ると脳が活動状態になり、睡眠に必要なホルモンの分泌を抑制して寝付きを悪くしたり、眠りが浅くなったりしてしまいます。
ただし、家事をしている間にテレビやタブレットなどを見てくれていると助かるときもありますよね。時間を決めて、上手に活用しましょう。
眠るときの部屋の明るさは真っ暗な状態が理想ですが、授乳やおむつ交換のときには明かりが必要ですよね。ですが、天井の照明をつかってしまうと子供は覚醒してしまう可能性が高まりますし、天井の常夜灯でも子供にとっては明るすぎます。そこで、足元を照らすだけのおやすみライトを使用するのがオススメです。光は暖色系で2~3ルクス以下のものにして、一晩中つけておくようにしましょう。子供は目を覚ましたときに状況が変わっていると不安になってしまい、夜泣きや覚醒の原因になってしまうためです。
一方、音は光と違って無音では不安を感じてしまうことがあり、特に月齢の低い赤ちゃんほどその傾向があります。子供が安心して眠れるのはテレビやラジオなどの砂嵐の音や、波や小川のせせらぎなどのゆらぎのある自然の音です。これらの音には、眠りを妨げる雑音や生活音を打ち消す効果や、赤ちゃんの声に家族が敏感に反応してしまうことを防ぐ効果もあります。
大人と違う快適な温度・湿度を知ろう
赤ちゃんの睡眠に最適な温度は20~22度で、大人にとっては肌寒く感じるかもしれません。あくまで目安なので子供の体調や室内環境でも変わってきますが、もし子供が夜中に汗をかいている場合や、怖い夢を見て起きてしまう場合は暑すぎる可能性があります。逆に、お腹や背中が冷えている場合は寒すぎるサインです。
また、湿度は40~60%になるように加湿器や除湿機を使ってコントロールしましょう。日本の気候は、夏場は湿度が適正値より高くなりやすく、冬場は乾燥しがちになりますので注意が必要です。
添い寝について
子供と家族が「同じ部屋で寝床が別」という寝方が睡眠を考えたときには理想的ですが、日本では子供と添い寝をする文化があります。
添い寝は授乳や子供の変化にすぐ対応ができ、家族と子供の時間も増えて、よく眠れるというメリットがあります。一方で、子供が途中で目が覚める確率が上がったり、一緒に寝ている家族を蹴って起こしてしまったりすることがありますし、一人で眠れるようになるまで時間がかかってしまうという可能性もあります。
窒息などの事故が起こらないよう安全性への注意を踏まえて添い寝をするかどうか、いつから始めるのかなど検討すると良いでしょう。

子供と家族の幸福度を高めよう
大きなストレスや不安なことがあると眠りが浅くなってしまいますよね。子供もそれは同じで、心が安定していれば、スムーズな眠りにもつながっていきます。ですが、幸福度を高く保つには子供だけではなく、家族の心にも注目をしないと上手く行きません。

家族と子供の感情はリンクする
自分が子供であった頃の記憶を思い出すと、家族の顔色や機嫌を敏感に感じ取っていませんでしたか? 家族の機嫌が良ければ自分も安心し、機嫌が悪ければどうしたのだろうと不安になっていたはずです。
子供は赤ちゃんの頃から家族の感情を感じ取っています。育児や仕事などが重なり睡眠不足になると次第に追い詰められて怒りっぽくなってしまいがちですが、子供がそれを感じ取って不安に思い、夜泣きをするという悪循環に陥ってしまうこともあります。
自分をケアしてあげよう
子供の幸福度を高くするには、まず家族の心が満たされていなければなりません。そのためにはすべて自分でやろうと思わずに「頼る」ことが大事になってきます。
地方自治体による一時保育や一時預かり、ベビーシッターなどを利用して子供から離れて一人になれる時間を作ったり、夕食にデリバリーを利用したりして家事の負担を減らすようにしましょう。ちょっとした息抜きをこまめに入れるように心がけるのも大切です。
子供と向き合う時間をつくる
大人にとっては些細なことでも、子供にとっては大きな変化と感じるものもあり、それがストレスになって睡眠トラブルのもとになることもあります。子供によっても差はありますが、例えばケガをしてしまった、保育園の先生がいつもと違うといったこともストレスになります。
そんなときは、子供に謝る、不安を取り除く、褒める、感謝するなどスキンシップをとって、「大好きだよ」という気持ちを伝えてあげましょう。子供との触れ合いは量より質が大事で、毎日5分や10分と短くてもしっかりと向き合ってあげることが大切です。子供は家族の感情に敏感ですので、何かをしながらではなくしっかりと感情を向けてあげてください。
生活リズムを整えよう
例えば、遊園地でお化け屋敷に入ったときに怖いと感じるのは、この先に何が待ち構えているのか、何が起きるのかが分からないからではないでしょうか。子供も同じで、次に何をするか分かっていれば不安になりにくく、眠りにもスムーズに入りやすくなります。
そのためには「ねんねルーティン」をつくり、毎日同じ順序で寝かしつけるようにしましょう。ねんねルーティンは家庭に合った流れで考え、お風呂から上がって電気を消すまで約45分で終わるのを目標にするとよいでしょう。成長と共に、順序を紙に書いて子供が見えるところに貼り、子供が自分で確認できるようにするのも効果的です。
寝る時間になっても「絵本をもっと読んでほしい」などのリクエストがある場合には、境界線をはっきりさせておくことが大切です。ルーティン以上のことを要求されないように、あらかじめ「何冊までだよ」と伝えてそれ以上には応じないようにしましょう。
ルーティンは一貫性がとても重要なので、最初は大変でも粘り強く続けましょう。
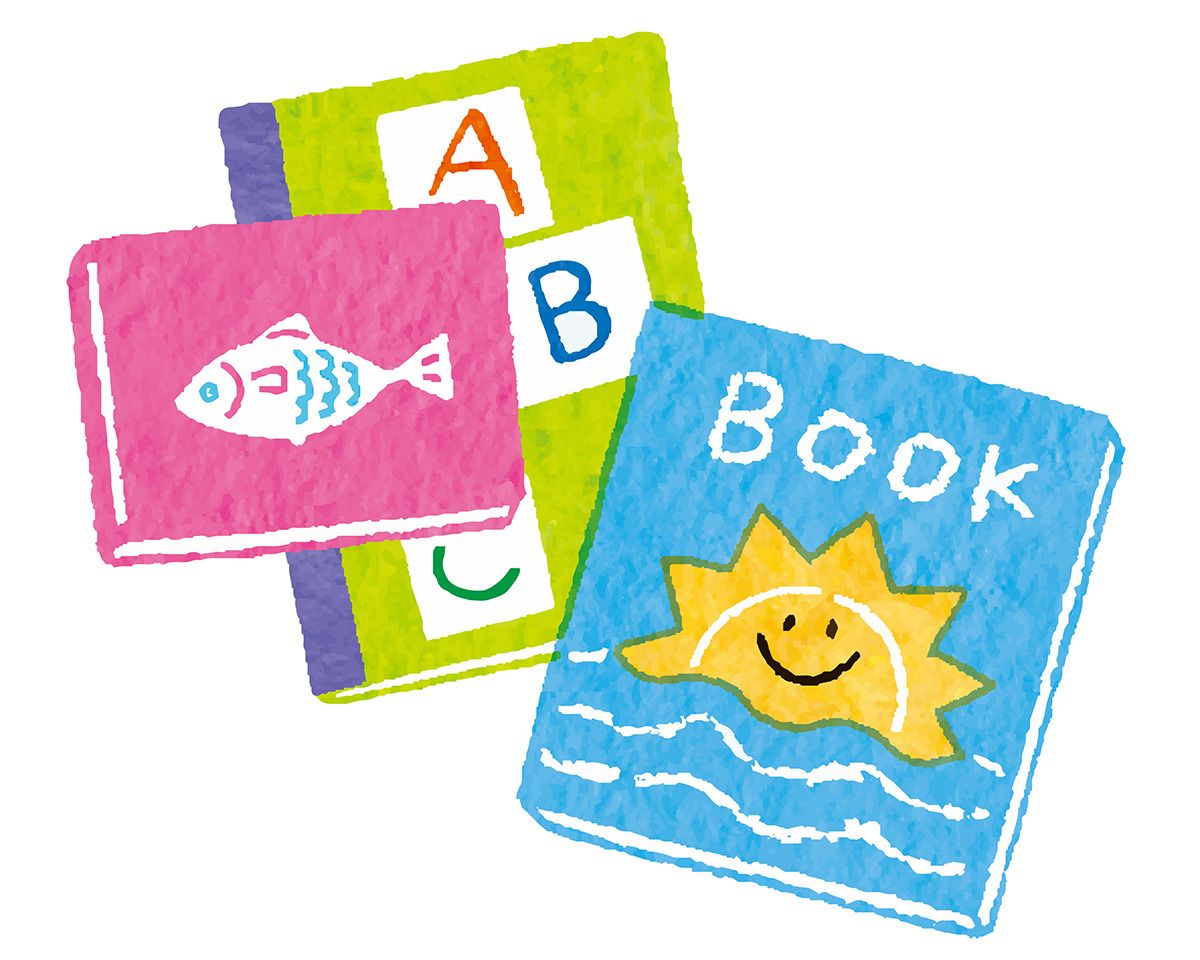
ねんねトレーニングでトラブルを減らそう
子供の寝かしつけが必要なければ、家族の負担も減ってきますよね。多くの子供は添い寝・添い乳・抱っこ・とんとんの寝かしつけの癖がある場合、一人で眠れるようになるために「ねんねトレーニング」が必要になります。タイミングには個人差もありますが、トレーニングを始めるのであれば夜通し寝られるようになる6ヶ月以降から始めましょう。
始める前に確認しておくこと
添い寝をしていても夜泣きなどの睡眠トラブルがなく親子ともに幸せなら、無理してねんねトレーニングをする必要はありません。ですが、悩まされているようならねんねトレーニングは効果的で、月齢が低いほうが比較的短期間で効果を感じるでしょう。
ねんねトレーニングを始める前には医学的に問題がないことと、「睡眠の土台」が整っているかの確認をしましょう。ねんねトレーニングは効果を感じるまで夜は1~4週間、昼寝は1~3ヶ月かかることがあり、今までより泣いてしまう子供もいます。家族にとっては一時的に寝不足など負担が増えてしまうため、心の準備と周りのサポートも整えましょう。
オススメする2つのメソッド
ねんねトレーニングの方法はたくさんあり、家庭環境、育児方針、子供の性格を見て選ぶのがいちばんですが、ここでは寝つくのを見守る2つの方法をご紹介します。
・フェイドアウトメソッド
約2週間かけて子供との「距離」を少しずつ離していく方法で、子供を部屋にひとりにせず、寝るまでサポートをしてあげます。日本人に向いている代表的な方法で、子供によっては泣くことを最小限にすることができます。
目の前で泣かれることに心理的な抵抗があるという方には厳しいかもしれませんが、状況の変化に慣れるまで時間がかかる子供や家族におすすめの方法です。
・タイムメソッド
子供と離れる「時間」を少しずつ伸ばしていく方法で、泣きがおさまるのが比較的早いとされる方法です。これは子供が起きたままの状態で家族は部屋を出ていき、子供が泣いてもすぐには入らず決められた時間の間隔で部屋に入り、決められた時間だけあやします。
少しずつ部屋に入る時間の間隔をあけることで、子供が自分の力で落ち着き、寝てくれるようにガイドをしていくシンプルな方法です。
フェイドアウトメソッドよりも一時的に泣きが激しくなることがありますが、下の子がいる場合でも挑戦しやすいというメリットもあります。
この2つのうちで迷ったら、まずはフェイドアウトメソッドを試してみましょう。
まとめ
子供と大人は「眠り」に違いがあり、大人の感覚でよかれと思ってやっていたことが、逆に寝かしつけや夜泣きに悪影響を与えていることがあります。
また、子供は驚くほど環境の変化や親の感情に敏感だというのも忘れてはいけません。
睡眠環境、幸福度、生活リズムの3つの「睡眠の土台」を整えてあげることで、子供はぐっすりと眠ってくれるようになります。子供の睡眠で悩んでいるようならまずは睡眠の土台が整っているか、今の状況を確かめてみるところから始めてみましょう。
書籍紹介:『ママと赤ちゃんのぐっすり本 「夜泣き・寝かしつけ・早朝起き」解決ガイド 』
(愛波 文 著, 西野 精治 監修/講談社) 2018年6月出版
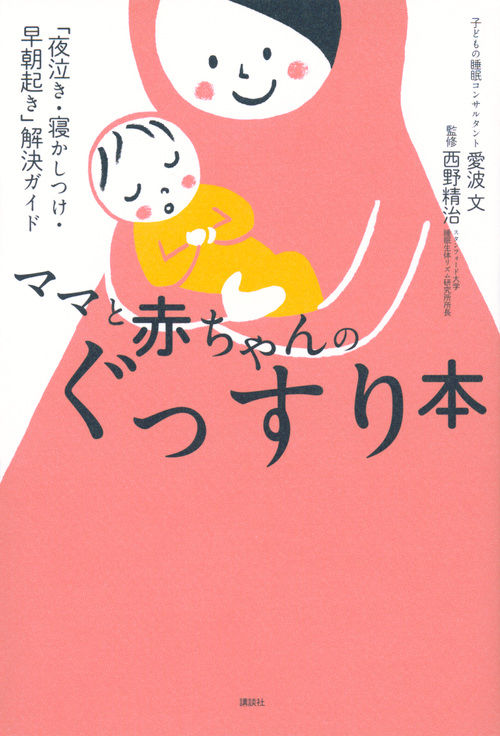
出版社書籍紹介:『ママと赤ちゃんのぐっすり本 「夜泣き・寝かしつけ・早朝起き」解決ガイド 』
(愛波 文 著, 西野 精治 監修/講談社) 2018年6月出版
・著者Home Page
・著者Instagram
・著者Youtube
・Amazon
・楽天ブックス
・紀伊國屋書店
記事編集
- くらひろ編集部
- 東京電力エナジーパートナー株式会社
「くらひろ by TEPCO」は、東京電力エナジーパートナーが運営するWebメディアです。でんきやガスのことはもちろん、あなたの毎日に役立つ知識から、くらしを広げるアイデアまで、“知りたい”に答える多彩な記事をお届けします。

この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事


























