
私たちにできる「災害の備え」とは?避難所立上げ研修を通じて気づいたこと
災害対策における「自助・共助・公助」をご存知でしょうか。「自助」は非常用持ち出し袋を用意したり、被災したときの避難所までの経路を確認したりと、日頃から災害について備えおくこと。「共助」は地域で協力・助け合うこと。「公助」は行政が行うことを指します。
「自助」については各ご家庭で取り組まれていることも多いと思いますが、今回は地域で助け合う「共助」と呼ばれる防災のあり方について理解を深めるべく、「避難所立上げ研修」に参加してきました。
体験した人
- 澄田 直子(すみた なおこ)
- ライター
旅とアウトドアを愛するライター。旅を中心とした仕事が多かったためコロナ禍で生活は一変したが、もともと“自家製”が好きだったため、酵母を起こしてパンを作ったり燻製を作ったり、おうち時間もなかなか楽しい。
目次 [CLOSE]
災害の規模が大きくなるほど「共助」での初動対応が重要に

災害対策でまず思い浮かべるのは、食糧や水の備蓄、救急用品や懐中電灯、携帯ラジオなどを備えた非常用持ち出し袋の用意、避難所の場所やルートの確認などではないでしょうか。これらの対策は自らの安全を自らが守るという防災の基本で「自助」と呼ばれています。
一方で、警察や消防、行政機関による防災支援が「公助」と呼ばれています。各機関とも、常に突発的な災害発生時には迅速に対応できるよう備えていますが、災害の規模が大きければ大きいほど対応は遅く、効力は小さくなります。
そういった状況下で頼りになるのが、となり近所の人々が助け合う「共助」です。過去の震災では、家屋の倒壊や生き埋め、閉じ込めから救出された人の約8割が家族や近所の人々によって助けられたというデータもあります。
参照:内閣府 防災情報のページ 「平成26年版 防災白書|特集 第2章 1 大規模広域災害時の自助・共助の例」
災害発生時に被害を最小限に抑え、復旧までの道のりを短くするには「自助」「共助」「公助」をうまく連携させることが大切です。
例えば、被災し住宅の倒壊やライフラインが断絶してしまったときに、私たちが向かう避難所。避難所自体の確保や避難路の整備などは「公助」が中心となりますが、災害が発生したときすぐに消防や自衛隊、警察などが来てくれるとは限りません。
いち早く避難所を立上げ、多くの被災者の安全を確保するには、地域の人々の協力「共助」が重要となるのです。
災害直後に必要な共助が「避難所立上げ」

近年、災害の多発化・激甚化が懸念される日本。
「南海トラフ巨大地震」や「首都直下地震」の危険性が叫ばれる昨今、避難所の重要性はますます高まっています。なかでも災害時における避難所開設・運営を理解することが大事になってきます。
しかし、これまでの避難所マニュアルは、避難所ができたあとの運営の仕方について記述したものが多く、災害直後に直面する「避難所の立上げ」にフォーカスしたものはあまり見かけなかったように思います。今回研修で指導する株式会社ネクセライズは、知識を伝えるだけではなく、実際に避難所立上げを疑似体験させることで、初動対応を柔軟に対応できるようになることを狙いとしているとのことです。
私たちひとりひとりが取り組み、協力できることの一つとして、災害発災直後から必要とされるのが避難所の開設です。避難所の開設は、通常、行政と施設管理者が中心となって行われますが、災害時は自治体職員もまた被災者。これまでにも自治体職員の被災により、十分な支援ができなかったこともあるとか。
参照:内閣府 防災情報のページ 「平成26年版 防災白書|特集 第2章 1 大規模広域災害時の自助・共助の例」
過去の教訓からもわかるように、困難な局面を乗り越えるためには地域のみんなで協力することが重要だと言えるでしょう。
ではさっそく、避難所立上げ研修を体験していきましょう。
【避難場所開設の流れ】

今回は大規模地震が発生したことを想定しています。発生直後は自分自身の身を守り、揺れが収まった後に一時避難場所へ向かうという状況です。被災した住民も続々と避難所に集まっていますが、まだ混乱した状況にあり、避難所はできあがっていないようです。
ここから、避難場所立上げが始まります。
避難場所は大きく下記のような流れで開設していきます。
避難所立上げ研修の流れ
- 避難所を解錠
- 避難所の安全を確認
- 避難所開設の準備
- 避難者の受入れ開始
避難所は解錠から受け入れ開始まで約3時間で行うことが理想だそうです。避難してきた被災者たちは、屋外で待機しています。その状況は真夏の炎天下かもしれませんし、真冬の夜かもしれません。お年寄りや小さなこども、持病のある人に限らず、過酷な環境は被災者の体力を刻々と奪っていきます。そのため、避難所はスムーズかつ迅速に立上げることが求められるんですね。
では次に、それぞれの対応について詳しく学んでいきましょう。
【避難所立上げ研修①】グループに分かれ、施設の解錠を行う
 画像提供:株式会社ネクセライズ
画像提供:株式会社ネクセライズ
最初に行うのが避難所の解錠です。避難所開設まで目標は3時間!グループに分かれ役割を分担することで効率的に進めていかなければなりません。
(※実際は鍵の場所、解錠の仕方を、あらかじめ地域の人々で話し合い、共有しておくことが必要だそうです。)
避難所に集まってきた人々のなかから、避難所立上げの協力者を募り、集まった協力者を下記のグループに振り分けていきます。
リーダー・本部・・・被災状況の確認、被災者の人数を把握、災害対策本部との連絡、グループへの活動の指示など
施設グループ・・・避難所の安全性の確認など
受入グループ・・・物資の搬入・搬出、避難者の受入など
みながそれぞれに動くのではなく、グループにわかれてそれぞれの役割を持ち、それを全うすることが重要なんですね。
【避難所立上げ研修②】避難所の安全を確認する
 画像提供:株式会社ネクセライズ
画像提供:株式会社ネクセライズ
施設グループは、避難所として使用する場所の安全を確認します。
本来であれば、被災した建築物を調べ、人命に関わる二次災害を防止する判定を行うそうです。「応急危険度判定士」がその作業を行いますが、災害発生直後、応急危険度判定士がその場にいない場合は、一時的に一般の人が自治体のマニュアルやチェックリストに沿って建物やその周辺の安全性をチェックするとのことです。問題なければ避難所として使用することができます。
自治体によってチェックリストはやや異なるそうですが、柱のひび割れや、建物周辺の地割れ、地盤沈下、建物の窓ガラスの破損などをチェックしていきます。
受入グループは避難者を校庭などに誘導します。並行して、避難者待機場所に物資を配備します。最初に配備したいのは、避難所の衛生のために必須な仮設トイレ。こうした物資がどこに保管されているのかは、あらかじめ確認しておくことが必要なようです。また、避難者のなかにはペットを連れている人もいるので、ペットのスペースも確保しておくことも大事だそうです。
仮設トイレの設置が大切というのはもちろん頭では理解していますが、非常時に優先して設置すべき事柄ということは、この研修を受けるまではっきりと認識していませんでした。こうした段取りを確認し、しっかりと認識しておくことが、非常時の行動にも大きく関わってくるんだなと思いました。
【避難所立上げ研修③】避難所開設の準備をする
施設の安全確認ができたら、施設グループが避難所受入場所の物資を配置します。避難スペースの区分け、ついたて(パーテーション)は、後々の避難所生活のストレスを大きく軽減できそうです。スペースの確保が早いもの勝ちということになると、あとから来た避難者にはスペースが残されていませんし、ついたてがないとプライバシーが保たれず、特に避難所生活が長期にわたる場合、多大なストレスになります。

一般の部屋以外にも、妊産婦・乳幼児部屋、介護などが必要な要配慮者部屋、また昨今では新型コロナウイルス感染症対策として発熱者待機部屋や、濃厚接触者待機部屋といったものも必要になってきます。避難所の大きさやレイアウトに合わせて、どのような区分けができるかあらかじめ自治体、地域ごとに考えておく必要がありそうです。
受入グループは仮本部を設置し、受付を作ります。受付は、避難者の名前などを確認するだけでなく、避難者の状態をチェックし、適切な部屋に振り分けていくことが必要だそうです。
昨今では、新型コロナウイルス感染症を拡大させないために、一般受付以外に、発熱者受付や感染者受付などを別に設置するほうが良いそうです。高齢者、妊婦、持病や障害の有無に加え、コロナ禍下では、発熱や自覚症状があるかということもチェックします。
また、一般の人と発熱者、濃厚接触者の導線をしっかり分けることも大切だそうです。誘導員を配置し、導線を確保できると良いですね。
少し前までは感染症への対策はそうそう意識してこなかったはず。避難所の立上げは、一度流れを作成したら終わり、というわけではなく、時代に合わせて柔軟に変えていくことが大事だなということに気づきました。
【避難所立上げ研修④】避難者の受入開始
避難所の準備ができたら、いよいよ受け入れ開始です。施設グループは、避難者に飲料水や食料、毛布などを配布します。
受入グループは、受付と誘導係に分かれます。受付で避難者の状態を判断し、誘導係が適切な部屋に案内します。
無事、避難者を避難所に案内することができました!
研修前は避難所の立上げなんて、どうしていいかさっぱり分からなかったですが、きちんとステップを踏んで、チェックリストに基づいて進めていけば、ちゃんと避難所が立上げられるんだということがわかりました。
地域の人々と話し合うことが災害対策の第一歩
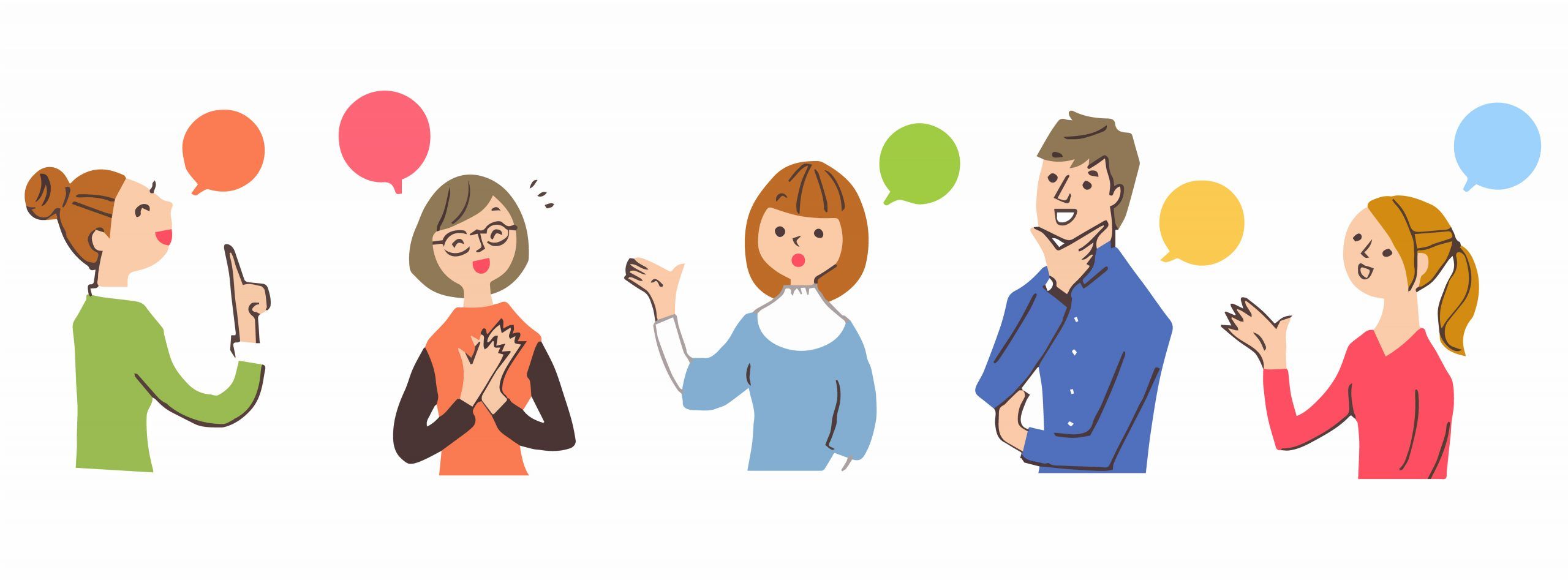
以上が、今回の研修の大まかな流れです。研修を体験してみて、被災後に避難所がどのように開設されるのか、シミュレーションを交えて体系的に理解することができました。
もちろん、避難所の大きさや状況により異なる部分はありますが、全体を通して流れを体験することにより、いざというときに冷静に先を見据えて行動することができそうです。
また、避難所立上げ研修を体験してみると、自分の住む地域の避難所について様々な疑問が湧いてきます。どこにあるのか、どのような建物なのかといった基本的な情報に加え、どのような非常用物資があるのか、食料や備蓄はどの程度なのか、建物などの安全を判断するチェックリストや避難者の受入チェックリストはどのような内容なのか。
そうした疑問を地域の人々と話し合い、明確にしたり改善していくことが、地域の一員としてわたしたちにできる防災対策の第一歩ではないかと思いました。この避難所立上げ研修は、そうした気づきを与えてくれます。
この記事の情報は公開日時点の情報です
KEYWORD
#人気のキーワード
RECOMMENDED
#この記事を読んだ人におすすめの記事
-

【洗濯表示マークの一覧表】正しい意味や注意ポイントを解説
-

【種類別に比較】乾燥機の電気代はいくら?1回・月間の光熱費を解説
-

洗濯機の買い替え時期はいつ?寿命サインとおトクなタイミングを解説
-

冷蔵庫マットのメリット・デメリット!後悔しない選び方を解説
-

マンションの騒音対策!騒音の種類やトラブル解決手順を解説
-

レーヨンは家で洗濯できる?洗い方や縮んだときの対処法を解説
-

お風呂の追い焚きのガス代は?入れ替え・足し湯は安い?節約方法も解説
-

引越しの挨拶はしない方が良い?マナーや女性の一人暮らしの注意点
-

ガス代を節約するには?ガス代の平均額や高くなる原因も解説
-

一人暮らしに必要なものリスト!最低限必要なものを男女別で紹介
-

カーペットは洗濯できる?自宅で簡単に洗う方法や注意点を解説
-

2025年:家電が安い時期はいつ?安く買うコツや製品別の買い替え時期を解説
-

ガス給湯器の水漏れは放置NG!リスクや原因、対処法を解説
-

換気扇のフィルターの掃除方法は?簡単にできる手順を紹介
-

スーパーでも非常食を揃えられる?選び方のポイントを紹介
-

ティッシュを洗濯してしまったときの対処法は?取り方を解説
-

暖房20℃では寒い?暖かくするコツ・電気代節約術も紹介!
-

防災士監修:地震対策で備えておくべき物リストを紹介!
-

暖房の平均設定温度は22.6℃!目安の温度や電気代の節約方法も解説
-

医師監修:部屋の乾燥対策9選!寝るときに手軽にできる対策も





